日本の食品添加物数が世界一というのは本当?海外との違い
日本は「海外よりも食品添加物の使用が多い」と聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「日本は食品添加物大国」「危険な物質が多く使われているかも・・・」という話を耳にすると、不安に感じてしまいますよね。
本記事では、海外との違いや安全性など、そうした疑問にお答えしながら、日本の食品添加物事情について解説します。
目次
日本の食品添加物は海外と比較してなぜ多いのか

日本の食品には食品添加物が多いと聞くと、「なんだか心配だな…」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、この「多い」というイメージには、いくつか理由があります。
まずはその背景から見ていきましょう。
日本と海外では食品添加物の定義や審査が異なるから
日本と海外を比べると、そもそもの定義や認可の仕組みが違っているのをご存じですか?
たとえば日本では、同じ物質でも用途ごとに名称が異なる場合があったり、成分を細かく分類することで「登録数が多く見える」という側面があります。
一方、アメリカやヨーロッパでは、包括的な分類で一括管理されることが多く、見かけ上の数は少なくなりがちです。
実際には日本の厚生労働省も、国際的な基準や審査の指針をしっかり参考にしています。
そういった状況なので、海外の規制が厳しく日本が緩いとは一概にはいえません。
参考:日本と海外の食品添加物規制の違い|(一社)日本食品添加物協会 松村雅彦,(参照2025-07-18)
アメリカの食品添加物事情
具体的にアメリカの例を見てみましょう。
アメリカではFDA(食品医薬品局)が食品添加物を管理しており、GRAS(一般に安全と認められる物質)というリストに多種多様な物質が記載されています。
一部食品添加物と認められているものもありますが、GRAS 物質は食品添加物の定義外とされています。
さらに州によっても異なる規制があるため、注意が必要です。
つまり、「数が多い=危険」というわけではなく、そもそも分類や管理の方法が異なるため、単純に数字だけで比較するのは難しいのです。
参考:食品添加物規制調査 米国|日本貿易振興機構(ジェトロ)ロサンゼルス事務所 農林水産・食品部 農林水産・食品課,(参照2025-07-18)
日本の食品添加物について
日本の食品添加物は具体的にどういうものがあって、どんなふうに分けられているのでしょうか。
ここからは、日本での食品添加物の概要を、わかりやすく整理していきます!
そもそも食品添加物とは

「食品添加物」というと、なんだか怖いイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、実際には食品を製造するうえで「必要に応じて」使用されています。
たとえば酸化を防いだり、色を鮮やかにしたり、長期保存を可能にしたり・・・。
現代の食生活には欠かせない役割を担っています。
厚生労働省が安全性や使用基準をしっかりと確認しているため、必ずしも危険というわけではありません。
参考:食品添加物 よくある質問(消費者向け)|厚生労働省,(参照2025-07-18)
食品添加物の分類について
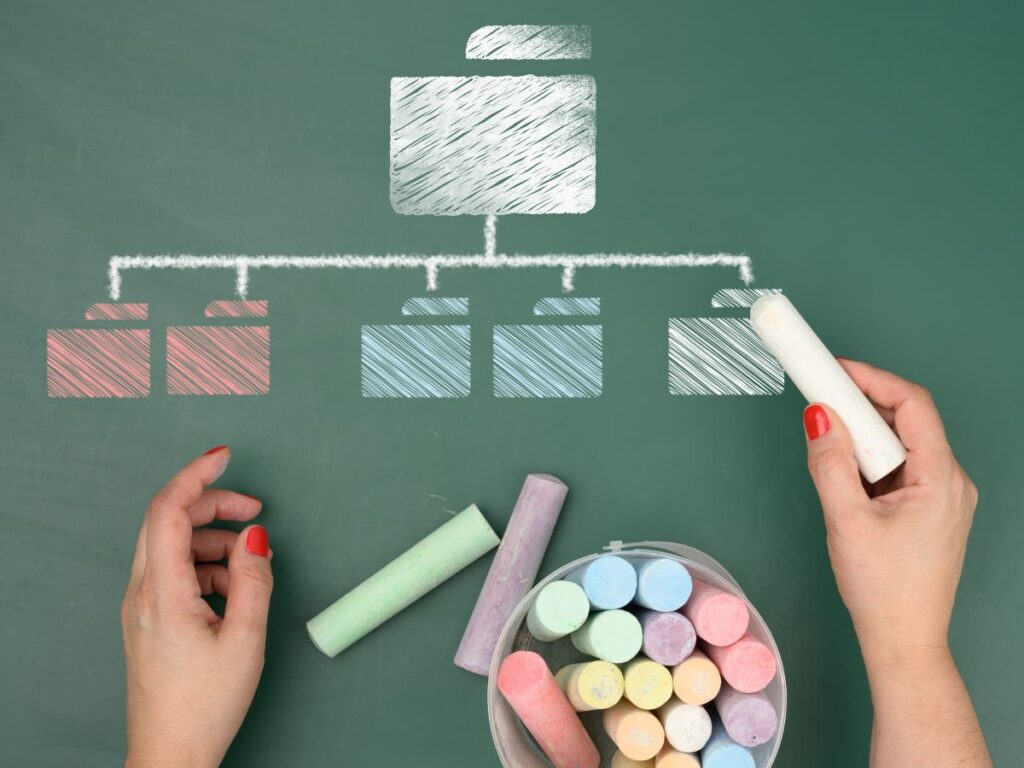
日本では、食品添加物を大きく4つに分類しています。
- 指定添加物:内閣総理大臣が使用してよいと定めたもの
- 既存添加物:長い食経験があって、広く使用されているもの
- 天然香料:植物や動物などから得られる天然由来の香り成分
- 一般飲食物添加物:普段から食品として食べているものを加工に応用するケース(例:いちごジュースなど)
分類が細かく分けられていることが、食品添加物が多く見える一因にもなっています。
食品添加物の代表的な種類

代表的な食品添加物を紹介します。
- 甘味料:甘みを付けるために添加され、砂糖より低カロリーなものが多い
- 着色料:見た目を華やかにしたり、色落ちを防止
- 保存料:カビや菌の繁殖を抑えて、食品を長持ちさせる役割
- 酸化防止剤:油の酸化や変色を防いで、品質を保つ
この他にも、乳化剤、膨張剤、発色剤などがあり、こうした成分のおかげで、安定した供給や保存が可能になっています。
食品添加物の役割

食品添加物には主に以下の役割があります。
- 腐敗を防ぐ:保存料や酸化防止剤を添加することで、食中毒のリスクが抑えられたり、食材が長持ちすることも。
- 見た目をよくする:着色料や増粘剤などが、食品をよりおいしそうに演出
- 味を調える:甘味料や調味料によって、かんたんに味のバリエーションが広がる
食品添加物は厚生労働省によって使用が認められた物質です。
ただし、過度な摂取には注意し、体質やアレルギーが気になる方は成分表示を確認するようにしましょう。
世界の食品添加物の使用状況
「じゃあ海外では、いったいどのように使われているの?」という疑問が出てくるかもしれませんね。
ここでは、主な国や地域の事例をご紹介します。
アメリカ

アメリカではFDAが食品添加物を管理し、GRASリストを運用しています。
日本よりも多くの物質が登録されているうえ、表示方法も異なるので、消費者からは「何が使われているのかわかりにくい」という声も。
とはいえ、安全性を確保するための審査は行われており、ルール自体が緩いというわけでもありません。
参考:食品添加物規制調査 米国|日本貿易振興機構(ジェトロ)ロサンゼルス事務所 農林水産食品部 食品課,(参照2025-07-18)
ヨーロッパ

ヨーロッパではEFSA(欧州食品安全機関)が評価を担当し、E番号というコードをつけて食品添加物を管理しています。
EU域内で共通のルールがある一方、国ごとに独自の制限を設けている場合もあります。
オーガニックや自然志向が強いこともあり、食品添加物自体を避けようとする消費者意識が高い傾向にあります。
参考:食品添加物規制調査 EU|日本貿易振興機構(ジェトロ)ブリュッセル事務所 農林水産・食品部 食品課,(参照2025-07-18)
中国

中国は中国食品薬品監督管理局(CFDA)が施行した法律に基づいて管理。
2024年に食品添加物使用基準(GB2760-2024)を公布し、2025年から施行がはじまりました。
加工品の市場規模が大きく、管理が十分に行き届いていないという課題も指摘されています。
しかし、輸入の際には他国と同様、届け出を義務付けており、違反の可能性に応じたモニタリング検査や検査命令等を実施。
令和5年度の違反率も、全体と比較して特に高いわけではないようです。
参考:中国の食品添加物データベース|農林水産省,(参照2025-07-18)
参考:輸入食品監視業務FAQ|厚生労働省,(参照2025-07-18)
韓国

韓国では食品医薬品安全処(MFDS)が管理を行い、日本と似たような基準が定められています。
キムチや調味料など、発酵食品文化が盛んなこともあり、風味を損なわないような添加物の使い方が重視されています。
また、健康志向の高まりから、食品添加物に頼らない商品に注目が集まることも増えてきました。
参考:韓国 食品添加物の基準および規格 |日本貿易振興機構(ジェトロ)農林水産・食品部 農林水産・食品課,(参照2025-07-18)
日本の食品添加物の安全性と誤解を解説
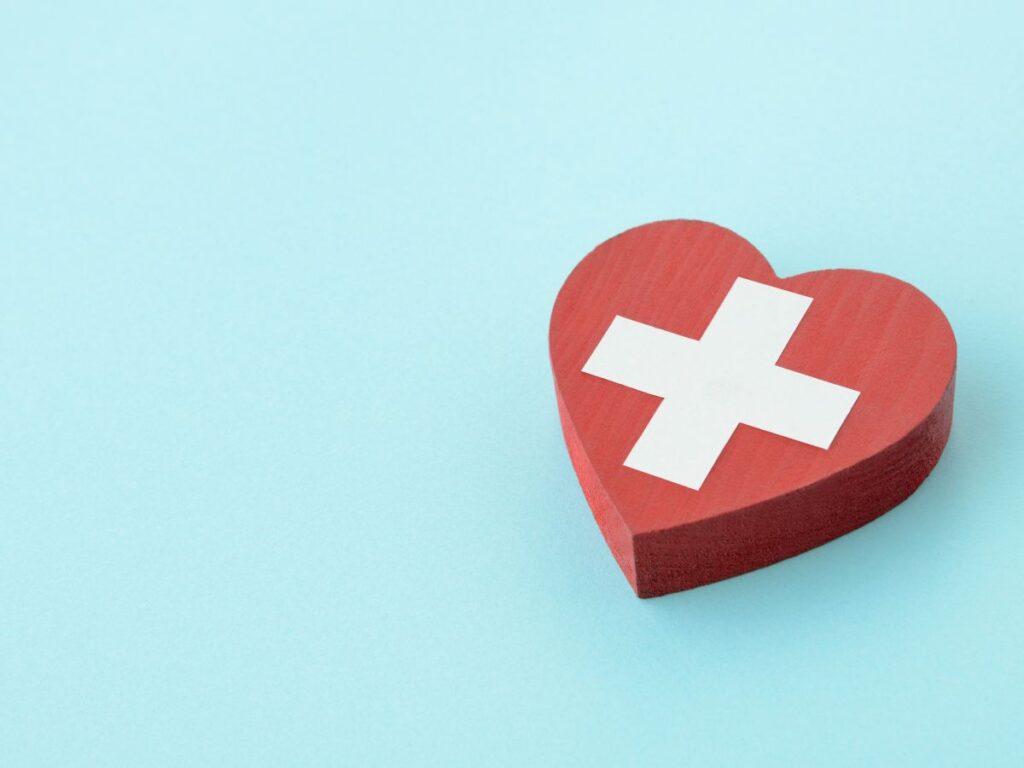
さまざまな国で使用されているので、安全性はある程度保証されているのだろうと思う一方で、やはり不安な気持ちが残る方もいらっしゃるかもしれません。
日本では、食品衛生法や各種ガイドラインに沿って、毒性試験や許容量(ADI)の設定などが行われています。
そうした厳格なプロセスを経て認可されているため、通常の食生活で過剰摂取しない限り、すぐに健康被害が生じることはありません。
「日本は緩い」というより、むしろ定期的に見直しや改正があり、疑わしい食品添加物は使用禁止になるケースもあるんですよ。
日本の食品添加物のメリットとデメリット
食品添加物は「悪者扱い」されがちですが、実は良い面と注意すべき点の両方があります。
ここではメリットとデメリットをわかりやすくまとめてみました。
日本の食品添加物のメリット

日本の食品添加物の主なメリットは以下の6つです。
- 食品の製造または加工時に役立つ
消泡剤やpH調整剤などで製造の効率や生産性をあげることができる
- 食品の形を作ったり、独特の食感を持たせる
増粘剤や膨張剤などで食品の形状や食感をよくすることができる - 見た目をよくする
着色料などで発色をよくして食品の見た目を整えて食欲を高める - 味と香りをよくする
香料や調味料で香りや味を調整でき、食品のおいしさを維持・向上できる - 栄養成分を補える
ビタミン類やアミノ酸の添加によって不足しがちな栄養素を補える
食品の品質を保つことができる
日本の食品添加物のデメリット

日本の食品添加物の主なデメリットは以下の5つです。
- 摂取し過ぎると、塩分・糖分・脂質過多になる
いくつもの加工食品を併用して食べると、許容量を超えやすい - アレルギー物質が含まれている場合がある
中にはアレルギー源になりうる添加物もあるため、表示の確認は欠かせない - 栄養を摂り過ぎる可能性がある
容易に栄養素を摂取できるので過剰摂取により生活習慣病のリスクもある - 複合影響のリスクが不明確である
複数の食品添加物の摂取によるリスクや症例が解明されていない場合がある - 安全性が十分に確認されていない既存添加物が存在する場合もある
2004年に禁止となった「アカネ色素」のように安全性が見直される可能性がある
参考:食品添加物「アカネ色素」及びこれを含む食品の取り扱いについて,(参照2025-07-18)
日本の食品添加物の表示方法

パッケージの原材料欄を確認すると、食品添加物の内容を知ることができます。
表示方法は以下3パターンです。
- 原材料と「食品添加物」欄を見出しで分ける
- スラッシュ「/」で区切る
- 改行・段で区切る
共通しているのは、「原材料の後に添加物が記載される」という順番です。
基本は物質名表記ですが、場合によっては以下の表示方法もあります。
- 簡略名・類別名
- 用途名+物質名
- 一括名
反対に、表示しなくてもよい場合もあります。
気になる方は、以下の食品表示に関する解説記事も参考にしながら、食品添加物について確認してみてください。
日本の食品添加物についてよくある質問

食品添加物にまつわる疑問は本当に多いですよね。
ここからは、よく寄せられる質問をいくつか取り上げてお答えします。
日本の食品添加物は外国の何倍ですか?

参考:食品添加物 よくある質問(消費者向け)|厚生労働省,(参照2025-07-18)
日本で認められている食品添加物はいくつありますか?
日本で使用が認められている食品添加物は以下に分類されます。
● 指定添加物
● 既存添加物
● 天然香料
● 一般飲食物添加物
この分類の合計として、831品目(香料含む)が食品添加物として認可されています。
(令和4年10月26日時点)

日本人は食品添加物を多く摂取していますか?
厚生労働省では、食品添加物を実際にどの程度摂取しているか調査しており、実際の摂取量は健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)を大きく下回っています。厚生労働省で食品添加物を実際にどの程度摂取しているか調査しており、実際の摂取量は、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)を大きく下回っています。
ただし、加工食品には食品添加物が多く含まれている可能性もあるため、食品表示を確認することを心がけましょう。

参考:食品添加物 よくある質問(消費者向け)|厚生労働省,(参照2025-07-18)
日本の食品添加物についてよく理解して誤解のない正しい知識を身につけよう
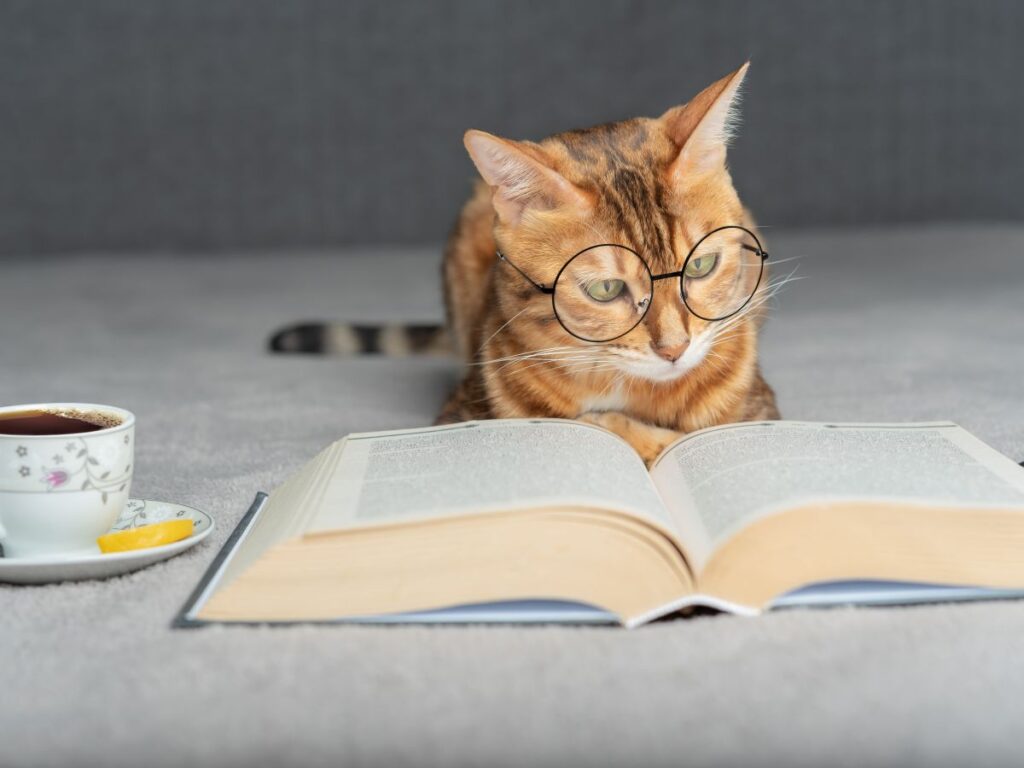
日本の食品添加物は、海外と比べて「多い」といわれるものの、実際は定義や分類の仕方による見え方の違いが大きいです。
また、厚生労働省の厳しい基準や国際機関の評価も取り入れており、必ずしも危険というわけではありません。
もちろん、過剰な食品添加物の摂取やアレルギーなどには注意が必要です。不安に感じる方は、原材料表示をしっかり確認したり、食品添加物に頼らない商品を選ぶのも一つの方法です。
正しい知識を身につけることで、日々の食品選びがより安心・安全なものになります。
アイチョイスでは食品添加物に頼らない商品を数多く取り扱っており、おためしボックスで実際の商品を食べてみることができます。
この機会にぜひお試しください!









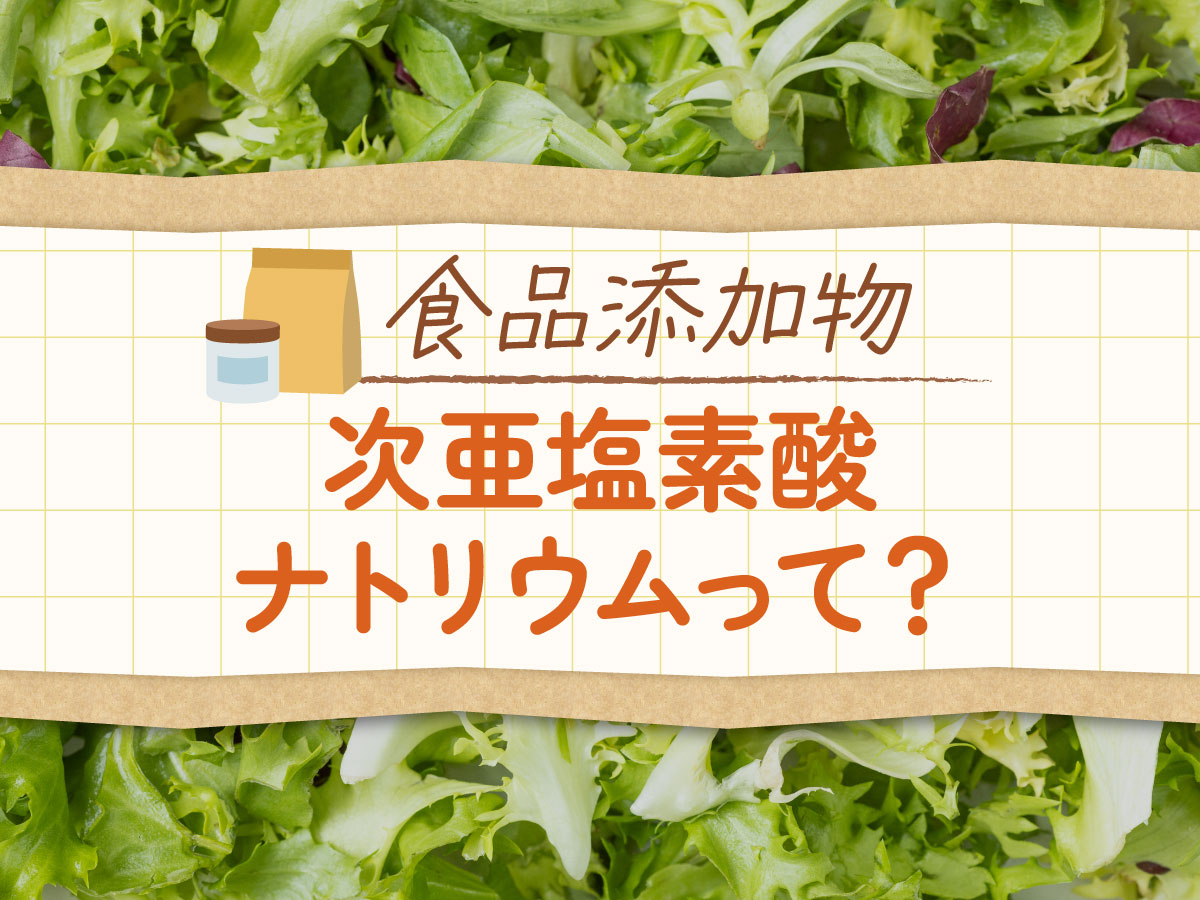
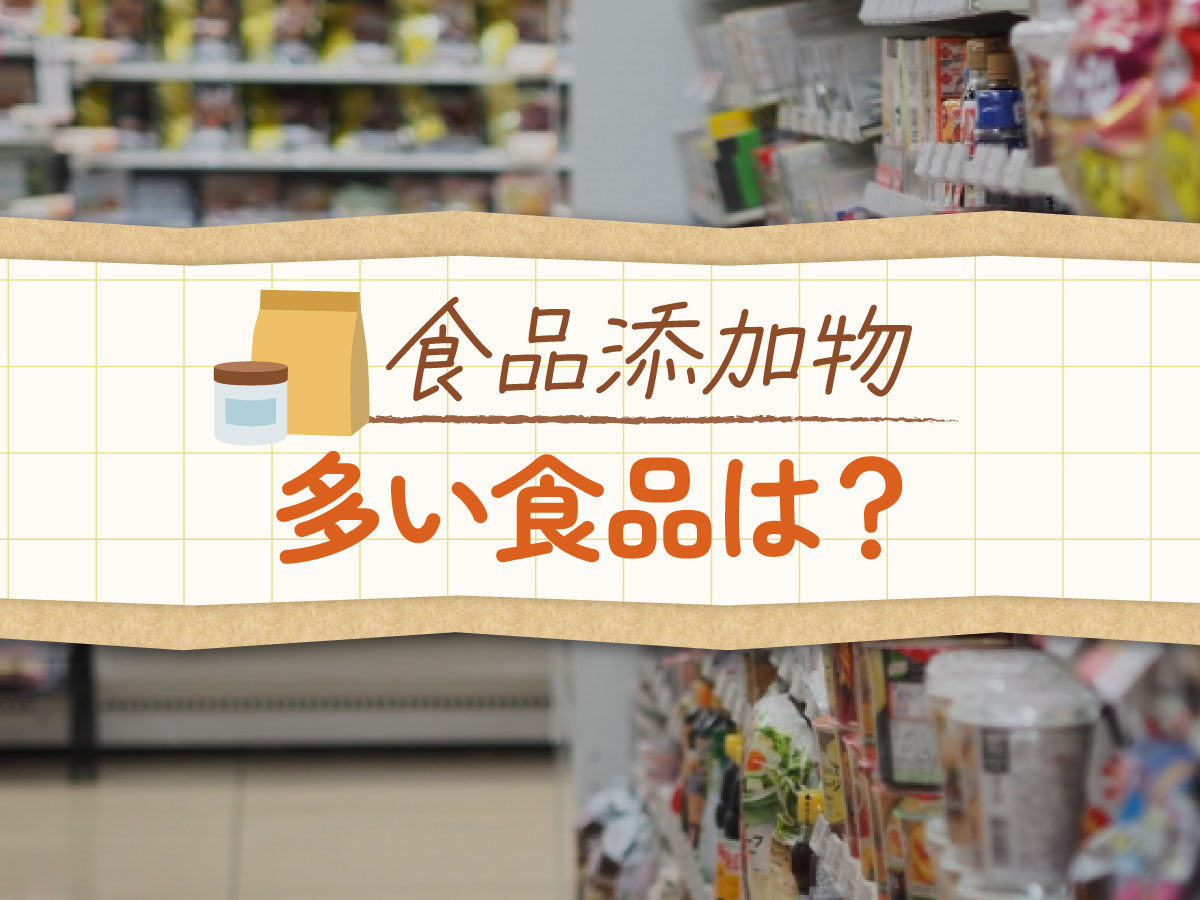


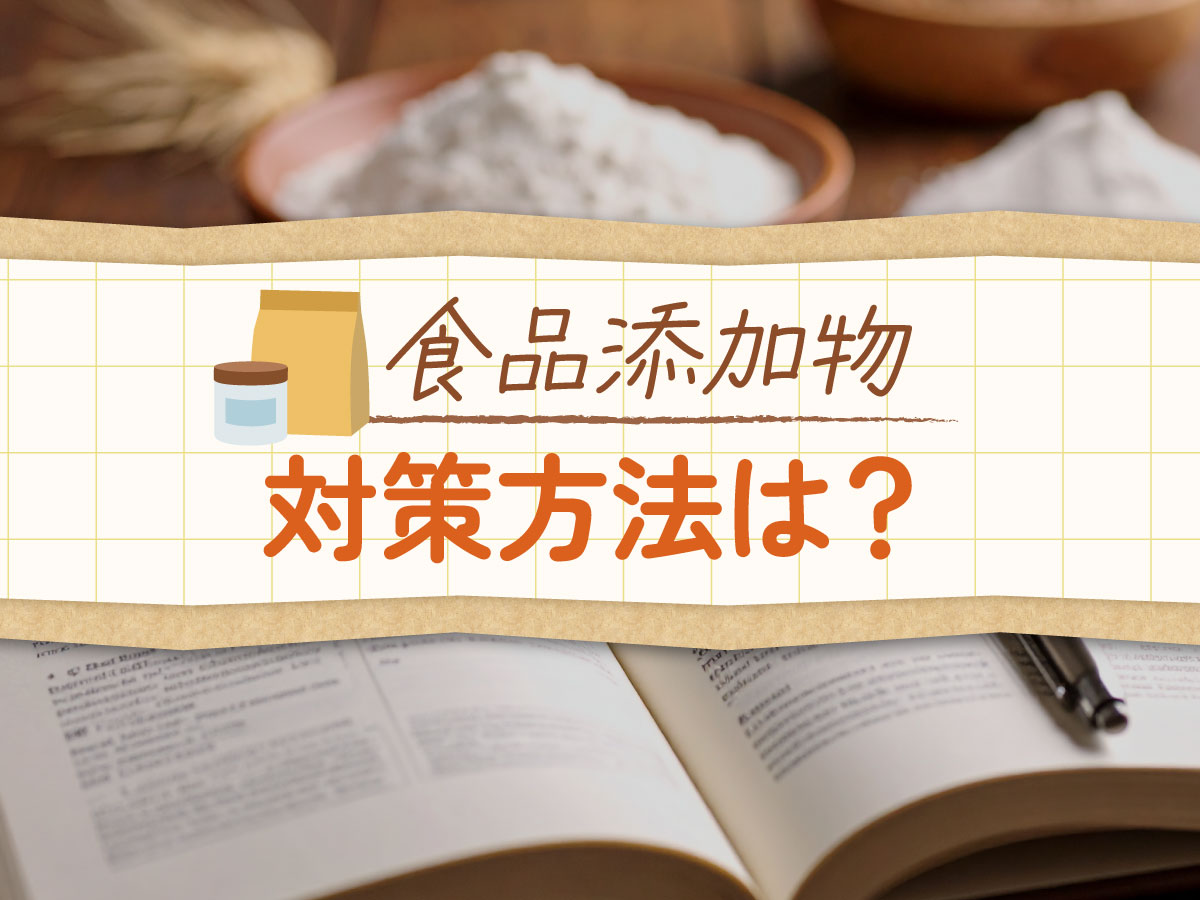



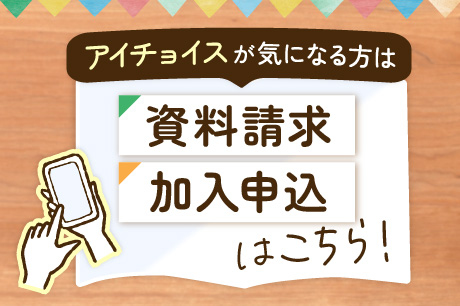




アメリカの認可数は約1600品目(2013年2月時点)で、日本は831品目(2022年10月26日時点)と、アメリカと比較すると2分の1ほど。
一方で世界的に見ても日本は食品添加物が多いと見られがちですが、その背景には、日本では同じ物質でも用途別に名前が違うケースがあったり、成分を細かく分類することで「登録数が多く見える」からです。