食品添加物のリスクと正しい対策まとめ|危険といわれる理由やデメリットとは?
食品添加物は安全性に配慮しながら利用されていますが、懸念されている点も存在します。
本記事は、食品添加物についての不安やデメリット、そして安心して摂り入れるための方法について解説したものです。
日々の食生活で意識しておきたいポイントを押さえ、安心して食事を楽しむための知識を深めましょう。
目次
食品添加物が危険と言われる理由とは

食品添加物は、食品の保存性を保ち味や見た目を向上させるために幅広く利用されています。
しかし、食品添加物による健康リスクについてテレビやネット上で話題となったことで、食品添加物=危険というイメージをもつ人もいるでしょう。
食品添加物が危険視される背景には、健康リスクへの懸念や複数の食品添加物を併用することによる影響が関わっています。
また、体質によってはアレルギーなどの反応が起こることも。
こうした背景を踏まえ、食品添加物については慎重に向き合うことが大切です。
食品添加物の安全性については以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はぜひ読んでみてください。
そもそも食品添加物とは?
以下では、食品添加物の概要や分類について解説します。
食品添加物の概要

食品添加物とは、食品の製造過程や保存、品質保持などの際に使用される物質のこと。
主に保存料、着色料、香料といった種類で知られていますが、用途や性質に応じた多様な種類が存在します。
国内では食品衛生法に基づき、食品添加物を4つのカテゴリーに分け、厚生労働省の認可が下りたもののみが使用可能になるのです。
参考:食品添加物 よくある質問(消費者向け)|厚生労働省,(参照2025-07-18)
食品添加物の分類

日本では、食品添加物は大きく以下4つの種類に分類されます。
- 指定添加物:厚生労働省から使用が認められたもの
- 既存添加物:国内で長年使用され続け、例外的に使用が認められたもの
- 天然香料:動植物から抽出した香料
- 一般飲食添加物:一般の食品を添加物として使用しているもの
目的や原料の違いによって分類されており、指定された範囲や基準の中で使用されるよう管理されています。
食品添加物は本当に危険?

食品添加物の危険性は以前からさまざまな議論がなされてきました。
一部では問題視される報告がある一方で、国や国際的な機関の安全評価を通過したものも多く存在。
日本では、以下のようなリスク分析によって科学的な根拠をもとに食品添加物の安全性を確保するよう義務付けられています。
| リスク分析の方法 | 内容 |
リスク評価 | 人の健康に害を及ぼす影響を科学的に評価 |
| リスク管理 | リスク評価の結果を踏まえて、食品の安全性を確保するための具体的な措置を検討・実施 |
| リスクコミュニケーション | リスク分析の全課程において、すべてのリスク要因について関係者間で情報や意見を交換 |
食品添加物に対する正しい知識を身につけて、自分なりの食品を選ぶ基準を考えることが大切です。
そのような中でこれまでに報告されたリスクについて以下で解説します。
参考:食の安全のための仕組み|厚生労働省,(参照2024-08-02)
リスクが報告され、登録上削除されたものもある

過去には、一旦は指定されていたものの安全性に疑問が生じ、のちに削除された食品添加物が存在しています。
たとえば、2004年7月に使用禁止となった既存添加物の「アカネ色素」は、過去にハムなどの食肉加工品、かまぼこなどの水産加工品、菓子類と私たちの身近な食品に使われていました。
しかし、ラットへの発がん性が確認され、使用禁止となったのです。
参考:食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除することについて|厚生労働省,(参照2024-08-02)
認証された食品添加物で健康被害が報告されたケース

すでに指定を受けている食品添加物でも、稀に健康被害の報告が出る場合があります。
多くの場合は過剰摂取や体質的な要因が絡んでいますが、アレルギー症状を発症したという報告も。
たとえば、コチニールカイガラムシから得られる着色料の「コチニール色素」では、急性アレルギー反応の報告があります。
また、防腐剤として使われる「安息香酸ナトリウム」は気管支喘息のリスクが報告されました。
複数の食品添加物で健康被害が報告されているのが現状です。
表示を確認し、体調に合わないと感じた場合には医療機関に相談するなど、自主的な対処が求められます。
参考:コチニール色素を含む食品によるアレルギーについて|厚生労働省,(参照2024-08-02)
参考:医薬品添加物と気管支喘息 (呼吸と循環 44巻6号) | 医書.jp,(参照2024-08-02)
複合的リスクについては不透明な点がある

食品添加物を1種類だけ取り上げて安全性評価を行うのと、実際に生活の中で複数の食品を摂取するのでは状況が異なります。
食品添加物の組み合わせは無数にあり、複数の添加物が同時に体内に取り込まれた場合の相互作用については、すべてが解明されているわけではありません。
複合的リスクについての研究は進んでいますが、引き続き注意深い検証が必要です。
基準値超過等による違反例

食品添加物の使用基準は厳格に定められていますが、基準値を超過したり、表示が正しく行われなかったりする違反事例が確認されています。
多くは生産・流通過程での管理ミスや表示ミスに起因し、回収や行政指導が実施されてきました。
消費者としては、そうした違反の情報をキャッチし、商品を選択する基準の一つにすることも大切です。
以下の記事では、摂取量に気をつけたい食品添加物の種類について解説しています。
詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
食品添加物を摂取しすぎないための対策

日常的に食品添加物の摂取量を抑えるために、購入時や調理方法で気をつけるポイントがあります。
食品添加物を完全に排除するのは難しいですが、日ごろの食生活を見直すことで過剰摂取を抑えることが可能です。
特に加工食品を頻繁に利用している場合は、できるだけシンプルな原材料の製品を選ぶことで、食品添加物の摂取量を減らすことができます。
さらに、自炊の際に加熱や素材選びを意識することで、食品添加物対策につなげられるのです。
食品添加物の種類を知っておく

普段目にする着色料、保存料、乳化剤、香料などの食品添加物は、用途によって特徴が異なります。
よく使用される食品添加物を把握しておけば、自身や家族の体質や食の好みに合わせて商品を選びやすくなります。
知らずに摂取しすぎるのを避けるうえでも、まずは食品添加物の種類を意識することが重要です。
食品表示を確認する

原材料表示欄には、どんな食品添加物が含まれているかが書かれています。
名称だけでなく、食品添加物の用途まで記載されているものもあるので参考にしましょう。
気になる食品添加物が多い製品は控えるなど、ラベルを丁寧にチェックすることが対策として大切です。
加熱する

一部の食品添加物は熱によって分解されるものがあります。
調理の過程で加熱することで、食品添加物の濃度や影響を低減できる場合があるのです。
例えば、ハムやソーセージに使用される亜硝酸ナトリウムは、加熱温度が高く、加熱時間が長いほど分解されるという実験結果が出ています。
ただし、すべてが分解されたり減ったりするわけではないため、あくまで補助的な対策として活用しましょう。
参考:食肉の塩漬に関する研究(第1報) 塩漬における亜硝酸塩 の添加量について,(参照2025-08-02)
オーガニックや旬の食材を選ぶ

加工食品を多用する代わりに、できるだけ旬の野菜やオーガニック栽培の食品を採り入れると、食品添加物を抑える効果が期待できます。
旬の食材は自然な甘みや旨味が強く、調味料や添加物に頼らずに美味しく調理できるためです。
また、新鮮な食材を使えば味や栄養価も高く、健康的な食生活に直結します。
少し手間はかかりますが、無理のない範囲で取り組むことで食品添加物の過剰摂取を避けられます。
食品添加物のメリット6つ

食品添加物はリスクばかりが注目されがちですが、食の安全や品質向上に寄与するメリットもあります。
安全性の基準に合格した食品添加物の多くは、私たちが同じ品質で食品を楽しむために欠かせない存在です。
食品添加物がもつ6つのメリットを解説します。
食品製造・加工に役立つ

食品添加物により製造が効率化し、大量生産が可能になりました。
必要量だけを化学的にコントロールしやすいため、ばらつきが少なく品質が保たれた食品を手頃な価格で提供できます。
このように、食品添加物の恩恵によって、消費者は安定した品質と経済的なメリットを享受できるのです。
なお、食品添加物の原料は国内だけでなく、海外で製造されるものも多く存在します。
「食品添加物の生産量統計調査を基にした摂取量の推定に関わる研究」によると、食品の粘度を高める増粘安定剤の一種であるペクチンは、国内での製造がほとんどなく、輸入に依存していることが明らかになりました。
このほかにも、日本で使用される食品添加物の中には、国内生産よりも輸入量が多いものがあり、安全性や管理体制を十分に確認したうえで選択することが重要です。
参考:諸食品添加物の生産量統計調査を基にした摂取量の推定に関わる研究,(参照2024-08-02)
食品の形状や食感づくりに活かせる

ゲル化剤や安定剤を使うと、ゼリーなど独特の食感をもつ製品を実現できます。
限られた食材だけでは出せない舌触りや固さのバリエーションを生み出せるため、消費者に多彩な食体験を提供することが可能に。
幅広い製品開発にも貢献しているのが特徴です。
食品の見た目を良くする

着色料や発色剤は、商品の外観を華やかにし、購買意欲につながる効果があります。
食品の自然な色合いを補うだけでなく、見た目の統一感や高級感を演出することも可能です。
視覚的に楽しめる要素が加わることで、食の満足度が高まります。
食品の味や香りを良くする

調味料や香料などの食品添加物は、味や香りを強化し、多様な嗜好に対応する助けとなります。
うま味や風味が向上することで、子どもから大人まで幅広く楽しめる製品づくりが可能に。
海外の味を再現する際にも、風味を調整しやすくなるのがメリットです。
栄養成分を補える

強化剤としてビタミンやミネラルを添加することで、不足しがちな栄養素を手軽に補給できます。
忙しい現代社会では、自然に近い食材だけで十分な栄養を摂るのが難しい場合もあるため、食品添加物が役立つ場面は少なくありません。
もちろん、過剰摂取にならないようにバランスを考えることが大切です。
食品の品質を保てる

保存料や酸化防止剤の利用により、食品が長期にわたって鮮度を維持できるように。
特に、輸送や陳列を経て消費者が手に取るまでの間に劣化しにくいため、食品ロスの削減にもつながります。
衛生面での安全確保に寄与するのも大きな利点です。
食品添加物のデメリット5つ
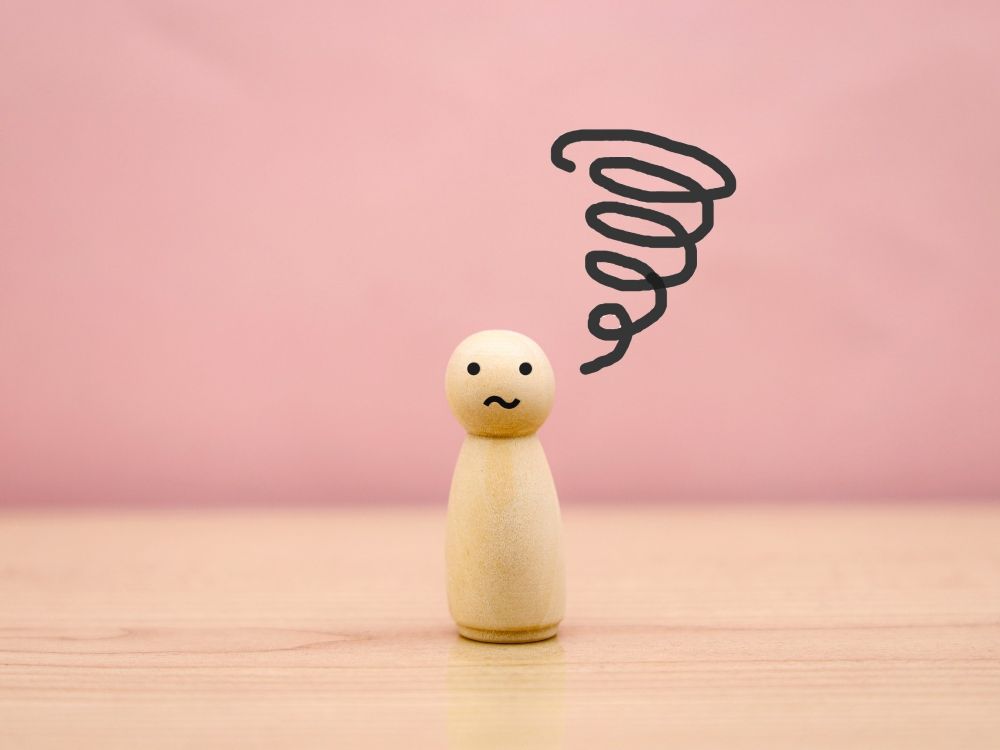
一方で、安全性の問題や過剰摂取による健康リスクなど、デメリットも考慮すべきです。
メリットがある反面、長期的な影響の不明確さやアレルギーのリスクなど、さまざまな懸念が指摘されています。
ここでは代表的な5つのデメリットをご紹介。
過剰摂取すると塩分・糖分・脂質過多になりやすい

一部の加工食品は、味を引き立てるために多くの調味料や油分を含む場合が。
その結果、無意識に塩分や糖分、脂質を摂りすぎ、生活習慣病のリスクを高める可能性があります。
食品添加物による影響だけでなく、食品自体を選ぶ際に栄養バランスを考慮することが大切です。
アレルギー物質が含まれている場合もある

着色料や保存料の中には、アレルギー物質として報告される成分が含まれているケースも確認されています。
体質によっては少量でも反応する場合があるため、表示の確認が欠かせません。
アレルギー症状が疑われる場合は、医療機関で検査を受けることが安全です。
栄養素を摂りすぎてしまう場合がある

ビタミンやミネラルが強化されている食品を大量に摂取すると、かえって栄養素の過剰摂取になってしまう恐れがあります。
健康によいとされる製品でも、摂り過ぎは必ずしも望ましくありません。
必要量を上回らないよう、日常的な食事やサプリメントとの兼ね合いを見極めましょう。
複合影響のリスクが不明確である

多種多様な食品添加物が一度に体内に入ったときの相互作用や長期間にわたる影響は、完全には証明されていません。
研究が進められているものの、公的機関の評価やデータにはまだ限界があります。
安全マージンを見込んで設定された基準値を守ったうえで、できる範囲で過剰摂取を避ける意識が重要です。
安全性の十分ではない既存添加物が存在する場合もある

過去から慣習的に使用されてきた既存添加物の中には、詳細な安全データが不十分なものがあるとされます。
長年使われているため大きな問題はないと考えられていますが、今後の研究によって新たな知見が得られる可能性も否定できません。
常に最新の情報をチェックしながら、自分や家族に合った選択を心がけましょう。
日本と海外の食品添加物の違いとは?

各国で規制や許可基準が異なり、日本独自の食品添加物や海外で使用禁止のものも存在します。
以下に、各国の食品添加物について表でまとめました。
| 国名 | リスク評価機関・管理機関 | 特徴 |
| 日本 | 厚生労働省 | 食品安全委員会が動物実験に基づきADI(一日摂取許容量)を設定 天然/合成の区別なく規制対象 JECFA(国際専門家会議)の評価を反映 |
| アメリカ | FDA (食品医薬品局) | GRASという一般に安全と認められている物質のリストで管理 安全性審査が実施 日本より登録物質数が多い |
| ヨーロッパ(EU) | EFSA (欧州食品安全機関・リスク評価) 欧州委員会・欧州議会(リスク管理) | E番号(例:E100)で添加物を一元管理 域内共通ルールだが、国ごとに独自制限も存在 オーガニック志向が強く添加物回避の消費者意識が顕著 |
| 中国 | CFDA (中国食品薬品監督管理局) | 2024年「食品添加物使用基準(GB2760-2024)」公布、2025年施行 加工品市場規模が大きく管理課題も指摘されるが、輸入時のモニタリングで違反率は0.02%(令和5年度)と全体平均(0.03%)並み |
| 韓国 | MFDS (医薬食品安全省) | 日本と類似した基準を採用 キムチなどの発酵食品文化を重視し、風味維持の添加物使用が主流 健康志向の高まりで添加物に頼らない食品が注目されている |
日本では食品衛生法に基づき、指定添加物を中心に詳細な使用基準や表示義務が定められています。
一方、海外では同じ食品添加物が禁止されていたり、使用量の上限が異なる場合があるのです。
これは食文化の違いだけでなく、科学的根拠や行政の方針の違いも背景にあります。
海外製品を購入する際や旅行先での食事では、その国のルールを理解しておくと安心です。
以下の記事では海外と日本の食品添加物事情について解説しています。
参考:諸外国における食品添加物の規制等に関する調査 報告書|厚生労働省,(参照2024-08-02)
食品添加物の対策に関するよくある質問

食品添加物対策には何がありますか?

避けるべき添加物は?
リスクが示唆され、国内外で問題視された食品添加物はできるだけ控えたいですね。
ただし、絶対的な「悪」とは言い切れないものもあるため、最新の情報を収集しながら柔軟に対応することが大切です。
以下の記事では気をつけて摂取したい食品添加物について解説していますので参考にしてください。

食品添加物との付き合い方を工夫し、安心して楽しめる食卓を整えよう

食品添加物は日々の食事に役立ちますが、摂取バランスに配慮していきましょう。
購入時に表示を確認し、調理時には加熱や食材選びを工夫するなど、小さな行動の積み重ねが大切です。
定期的に食品添加物の情報を確認しながら、より安全な選択肢を選び、毎日の食生活を安心して楽しみましょう。
本メディアを運営している生協「アイチョイス」では、食品添加物を控えた商品を多く取り扱っています。
より安心・安全な食品や食材を選びたい方には、実際の商品を味わえる「おためしボックス」もご用意していますよ。
この機会にぜひお試しください。






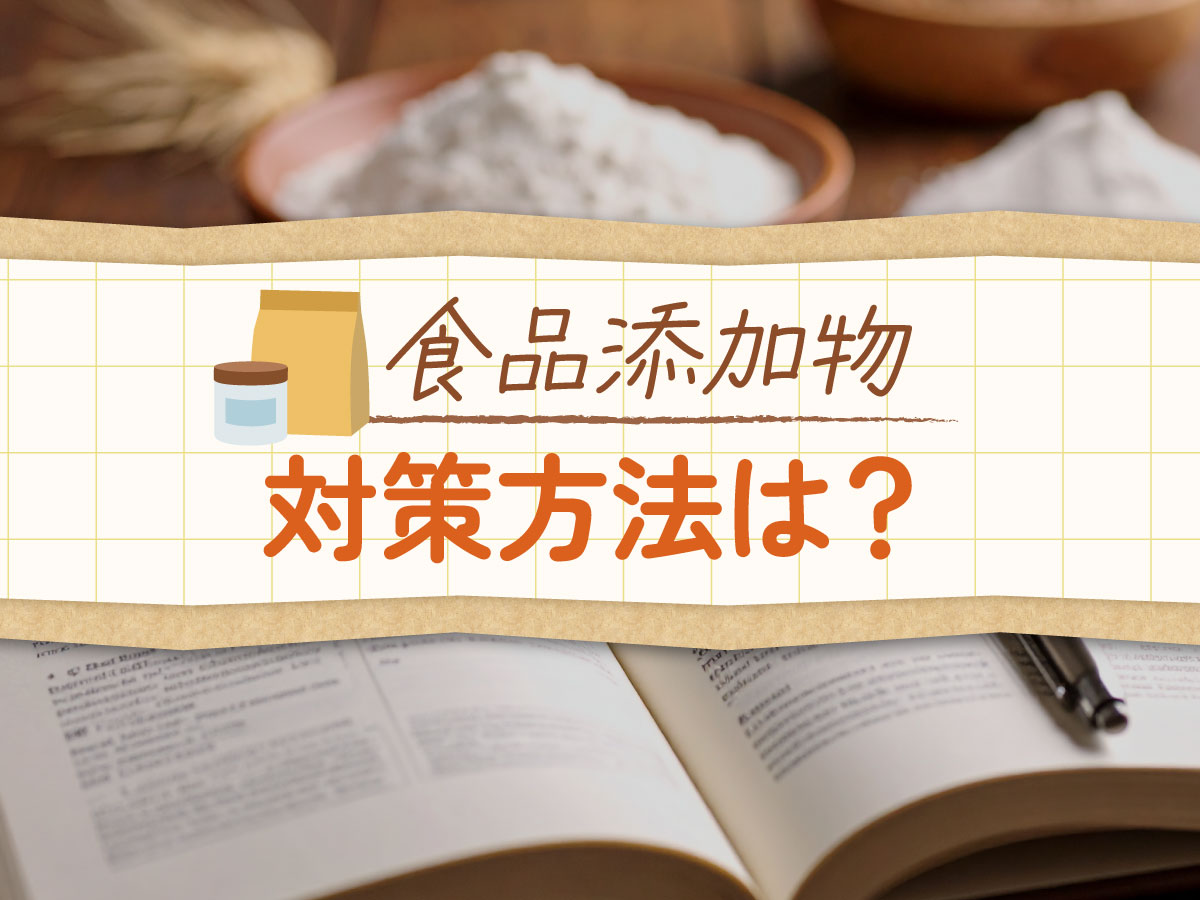

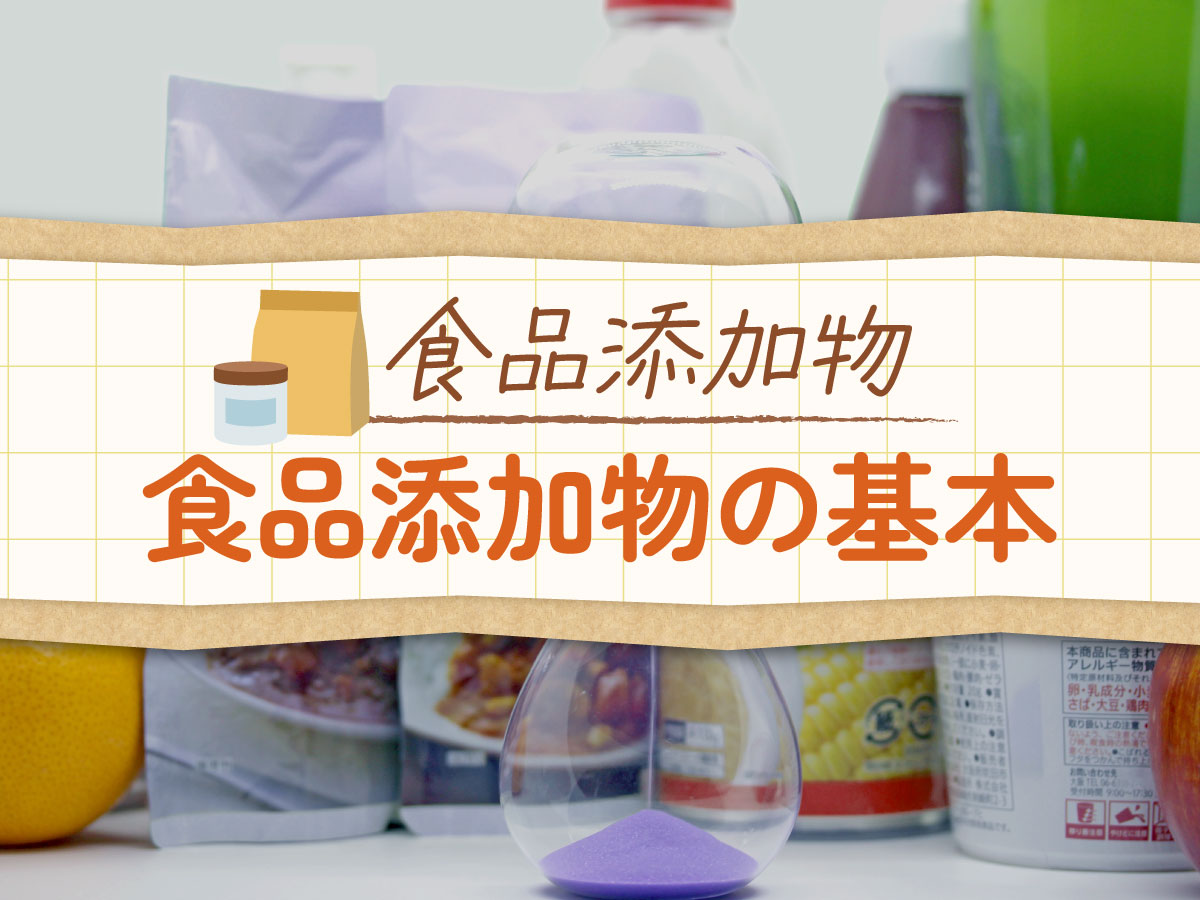


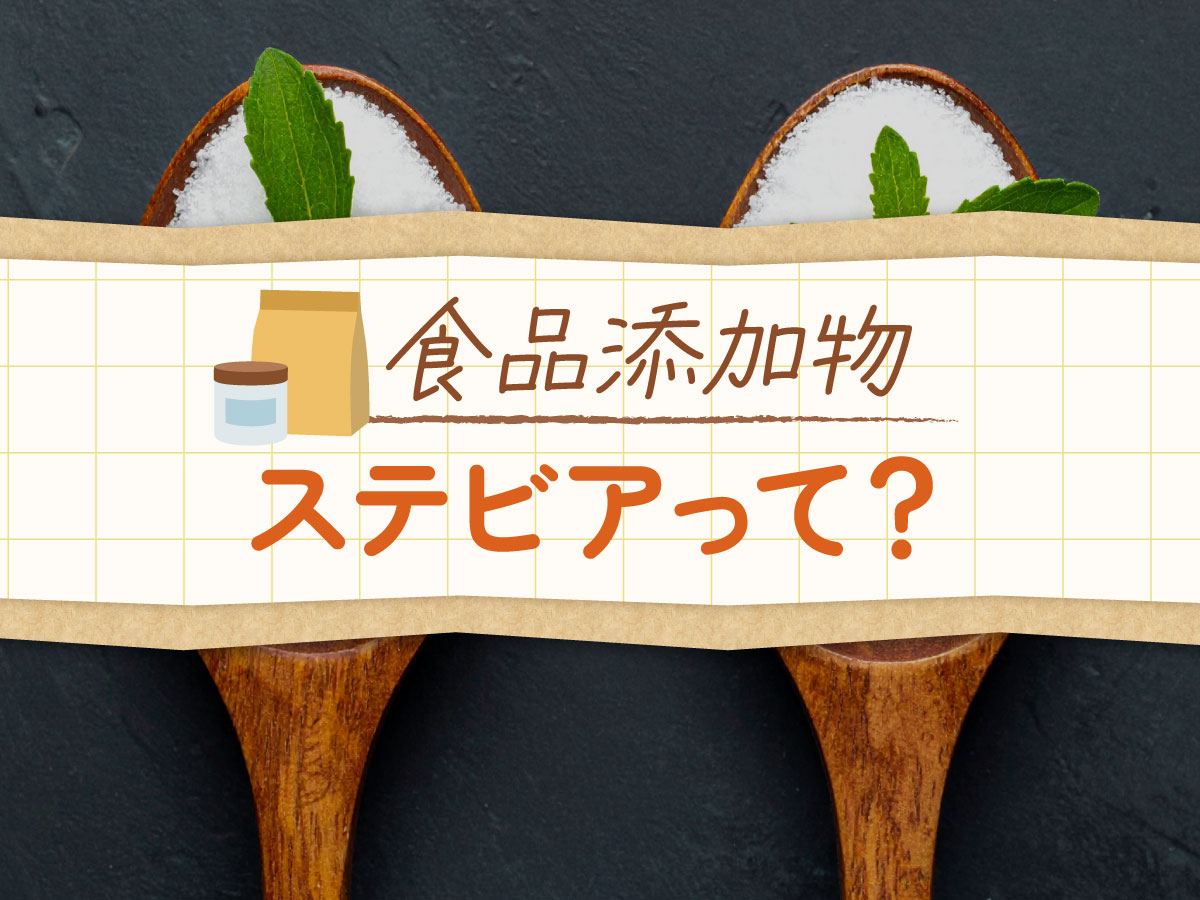

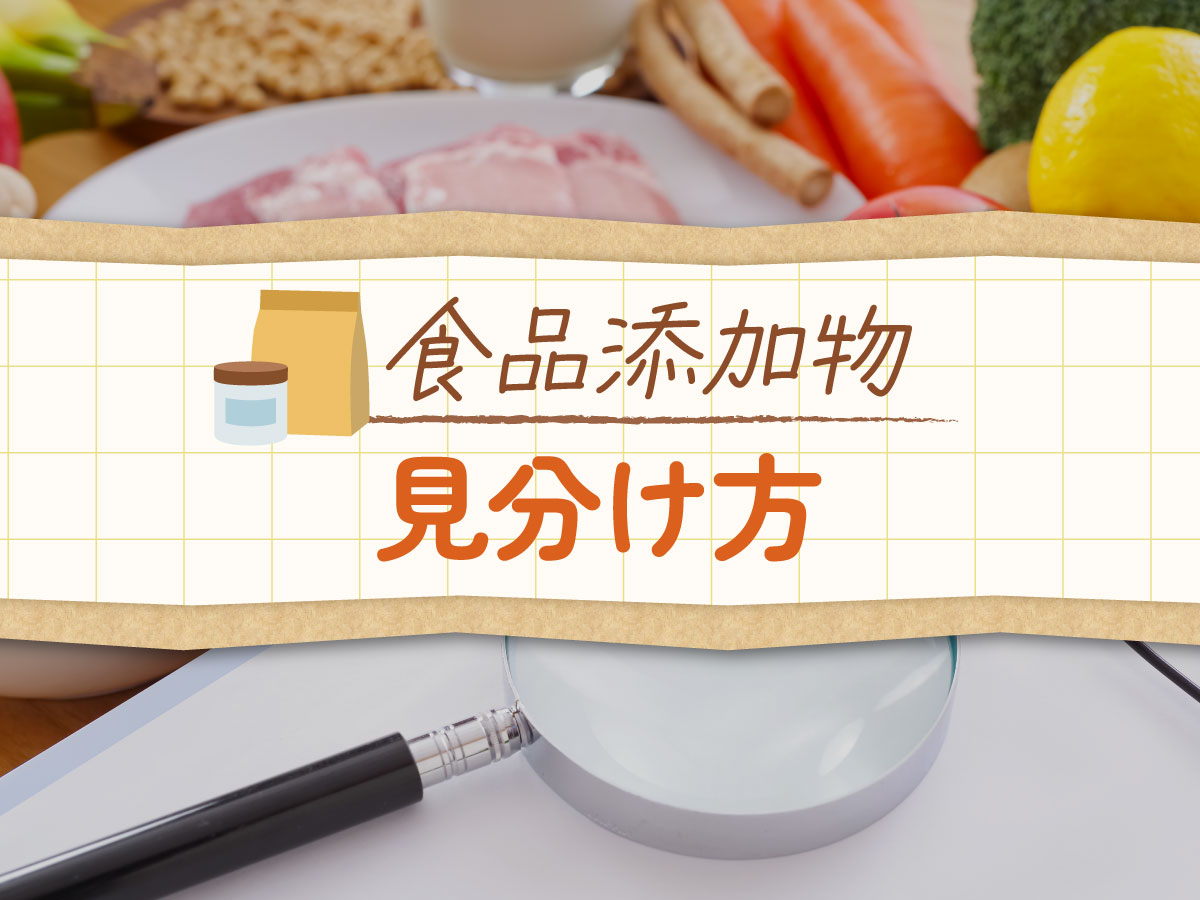



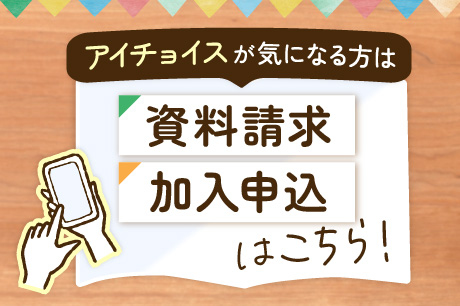




まずは表示をチェックすることが基本です。
さらに、自炊の頻度を上げて新鮮な素材を使うことで、食品添加物を含む加工食品の利用を減らせます。
オーガニック食品や食品添加物に頼らない食品を選ぶのも有効ですが、費用とのバランスを考えながら無理のない範囲で続けることが大切です。