食品添加物のビタミンCの危険性とは?安全性や用途などを解説
食品添加物としてよく使われるビタミンC(アスコルビン酸)。
用途や安全性、体への影響、表示の読み方などを、厚生労働省や食品安全委員会など信頼できる情報に基づいてわかりやすく解説します。
ビタミンCの知識を身につけて、安心して食生活を送りましょう。
目次
食品添加物としてのビタミンCとは

食品添加物のビタミンCについて、以下では概要や役割や酸化防止剤との違いを解説します。
食品添加物のビタミンCとは

ビタミンCとは、デンプンを加水分解して得られるブドウ糖を原料にし、発酵によって製造される食品添加物。
栄養素として知られるビタミンC(アスコルビン酸)を食品の品質保持などの目的で食品添加物として使用されています。
工業的に合成されたものでも、果物など天然由来のものでも化学的に同一のアスコルビン酸であり、体内での作用もまったく同じだそう。
ビタミンCは人にとって必須の水溶性ビタミンで、多くの野菜や果物に含まれていますが、食品添加物としても指定されて以来、幅広く使用されているのです。
参考:L-アスコルビン酸カルシウムの食品添加物の指定に関する添加物部会報告書|厚生労働省,(参照2025-05-21)
食品添加物としてのビタミンCの役割

ビタミンCは食品添加物としてさまざまな用途に使われています。
その主な役割は、食品の劣化を防ぐ酸化防止剤、不足しがちな栄養を補う栄養強化剤、そして食品の品質を向上させる品質改良剤などです。
ビタミンCは酸性で強い還元作用を持つため、食品中で酸素と反応して起こる変色や風味の劣化を抑え、保存性を高める働きがあります。
また不足しがちなビタミンCを補給する目的で添加されることも。
さらにパン製造時に生地を安定させてふくらみを良くするなど、食品の品質改良にも役立っているんです。
食品添加物のビタミンCと酸化防止剤の違い

「ビタミンC」と「酸化防止剤」は別物のように聞こえますが、食品添加物のビタミンC自体が酸化防止剤の一種です。
つまり、ビタミンCは酸化防止剤として食品に添加されるので、表示上は「酸化防止剤(ビタミンC)」のように記載されることがあります。
栄養的にはビタミンですが、食品添加物としては食品の酸化を防ぐ保存料的な役割を担っているのです(詳しくは後述の表示の章で解説します)。
名前の違いこそあれ、中身は同じアスコルビン酸であり、安全性や作用に違いはないといわれています。
食品添加物のビタミンCによる体への影響と危険性

食品添加物としてのビタミンCは安全性が高く、通常の摂取量で健康への悪影響の心配はほとんどありません。
厚生労働省の食品安全委員会による評価でも、アスコルビン酸(ビタミンC)には発がん性や遺伝毒性などは認められず、繰り返し摂取による有害な影響もとくに確認されなかったと報告されています。
ビタミンCは水溶性で体に蓄積しにくく、必要以上に摂取した分は尿中に排泄されるため、過剰摂取による急性の中毒症状も起こりにくいです。
実際、人で大量にビタミンCを摂取した試験でも重篤な副作用は報告されていません(大量に一度に摂ると一時的に下痢など軽い症状が出る場合があります)。
科学的な安全性評価に照らしても、食品添加物のビタミンCが通常の食生活で体に害を及ぼす可能性は極めて低いと考えられます。
参考:L-アスコルビン酸カルシウムの食品添加物の指定に関する添加物部会報告書|厚生労働省,(参照2025-05-21)
食品添加物のビタミンCが使われる場合がある食品

- 果実加工品
- 漬物
- 惣菜パン
- 清涼飲料水 など
ビタミンCは、その酸化防止作用や栄養強化の目的から、さまざまな食品に添加されています。
果実の加工品では、缶詰フルーツやジャム、ドライフルーツなどで変色防止のために添加。
また、カットフルーツ(カット済みのリンゴやパイナップルなど)に塗布して酸化による褐変を防ぐ用途もあります。
惣菜パンや菓子パンなどパン類では、生地改良や保存の目的でビタミンCが使われることがあるのです。
清涼飲料水(ジュース類やペットボトル茶、炭酸飲料など)にもよくビタミンCが添加。
これは飲料中の成分の酸化を防ぎ、風味や色の劣化を防止するためです。
その他にも、ハムやソーセージなどの食肉加工品で色調を保つ目的や、マヨネーズ・ドレッシング類の油の酸化防止など、幅広い食品でビタミンCが利用されています。
身近なさまざまな食品に実はビタミンCが添加されており、食品の保存や品質維持にひと役買っていることが多いのです。
食品添加物のビタミンCの表示について

食品を購入するときの原材料表示欄では、ビタミンCが添加されている場合にその旨が記載されており、表示方法にはいくつかポイントがあります。
一般に知られた名称を持つ食品添加物は、正式な化学名ではなく簡略名や別名で表示できるルールがあるのです。
たとえばビタミンCの化学名「アスコルビン酸」やその塩である「アスコルビン酸カルシウム」は、表示上は「ビタミンC」と書かれることが認められています 。
複数の酸化防止剤を併用している場合などは、「酸化防止剤(ビタミンC、○○)」のように用途名(酸化防止剤)と具体的な添加物名を併記する形で表示。
たとえば、いちごジャムの表示例では「原材料名 いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)」といった具合です。
ビタミンCは添加物欄に明記されますので、購入時に確認できます。
表示名が「ビタミンC」であれば、食品添加物の「アスコルビン酸」を指していると理解しておきましょう。
参考:簡略名又は類別名一覧表|消費者庁,(参照2025-05-21)
食品添加物のビタミンCの危険性に関するよくある質問
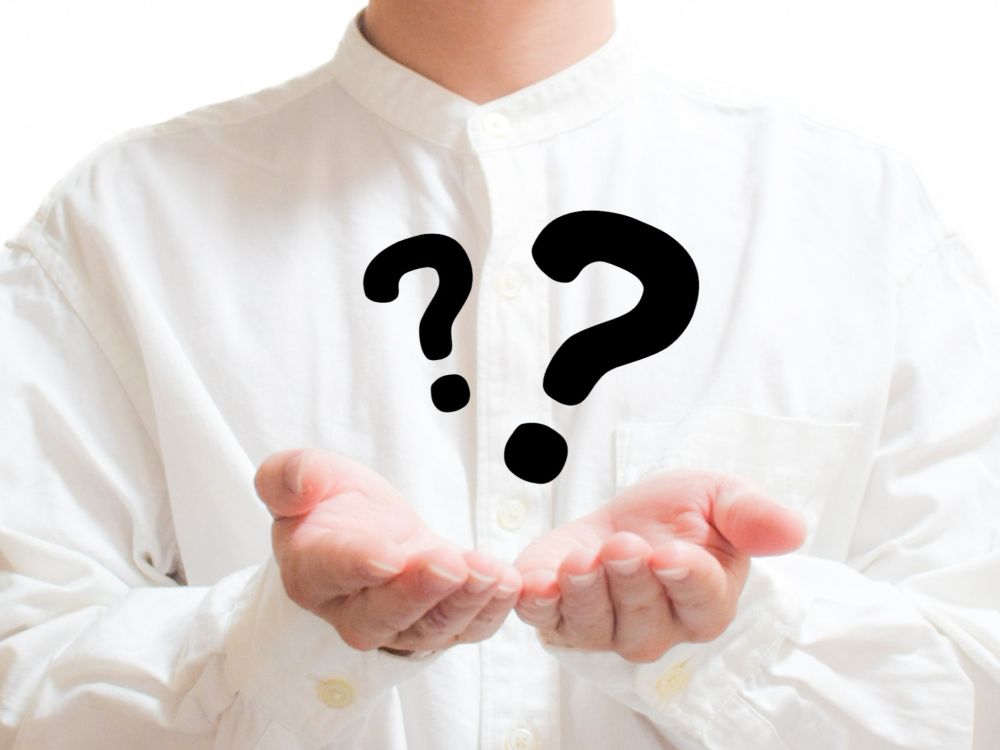
食品添加物としてのビタミンCは発がん性がありますか?

参考:食品や食品成分によるがん予防の難しさ|内閣府食品安全委員会,(参照2025-05-21)
なぜ飲料にビタミンCが添加されているのか?
飲料にビタミンCを添加する一番の理由は、酸化防止のため。
お茶や果汁飲料の成分は時間とともに酸化してしまい、色が変わったり風味が落ちたりします。
ビタミンCにはその酸化を防ぐ働きがあるため、製品の色や風味が変わらないように加えられているのです。

食品添加物のビタミンCの知識を身につけて安心して食生活を送ろう!

ビタミンC(アスコルビン酸)は食品の酸化を防いで保存性を高めたり、栄養を補ったりする食品添加物です。
厚生労働省や食品安全委員会によってその安全性が評価・確認されており、適切に使われる限り健康への悪影響を心配する必要はないとされています。
果実に多く含まれているビタミンCと体内での働きは同じで、安全性に違いはないといわれているのです。
アイチョイスでは、食品添加物に頼らない商品や詳細な原材料表示にこだわった商品をご提供しています。
まずはおためしボックスでお試ししてみませんか。
ハムやソーセージなど人気の商品が12点入っています!
ぜひお試しください。












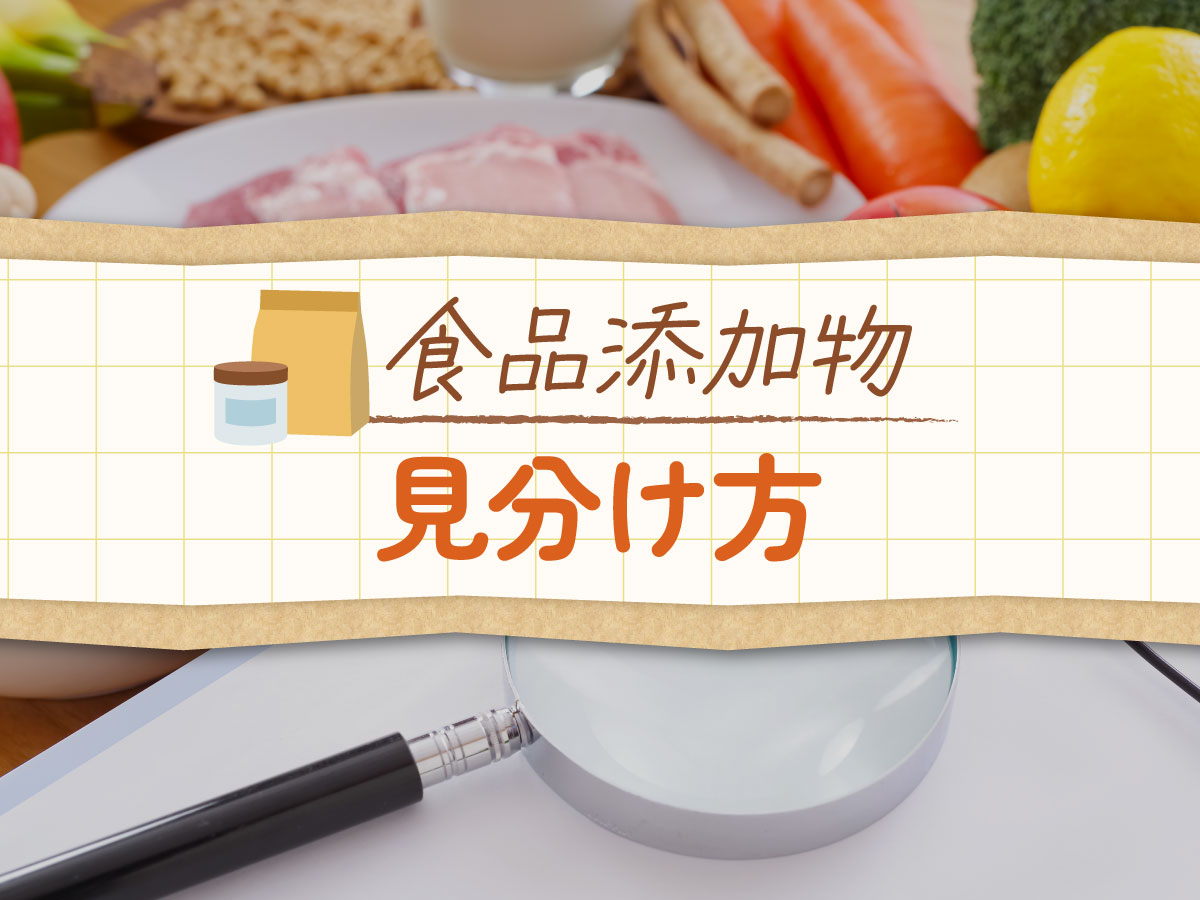
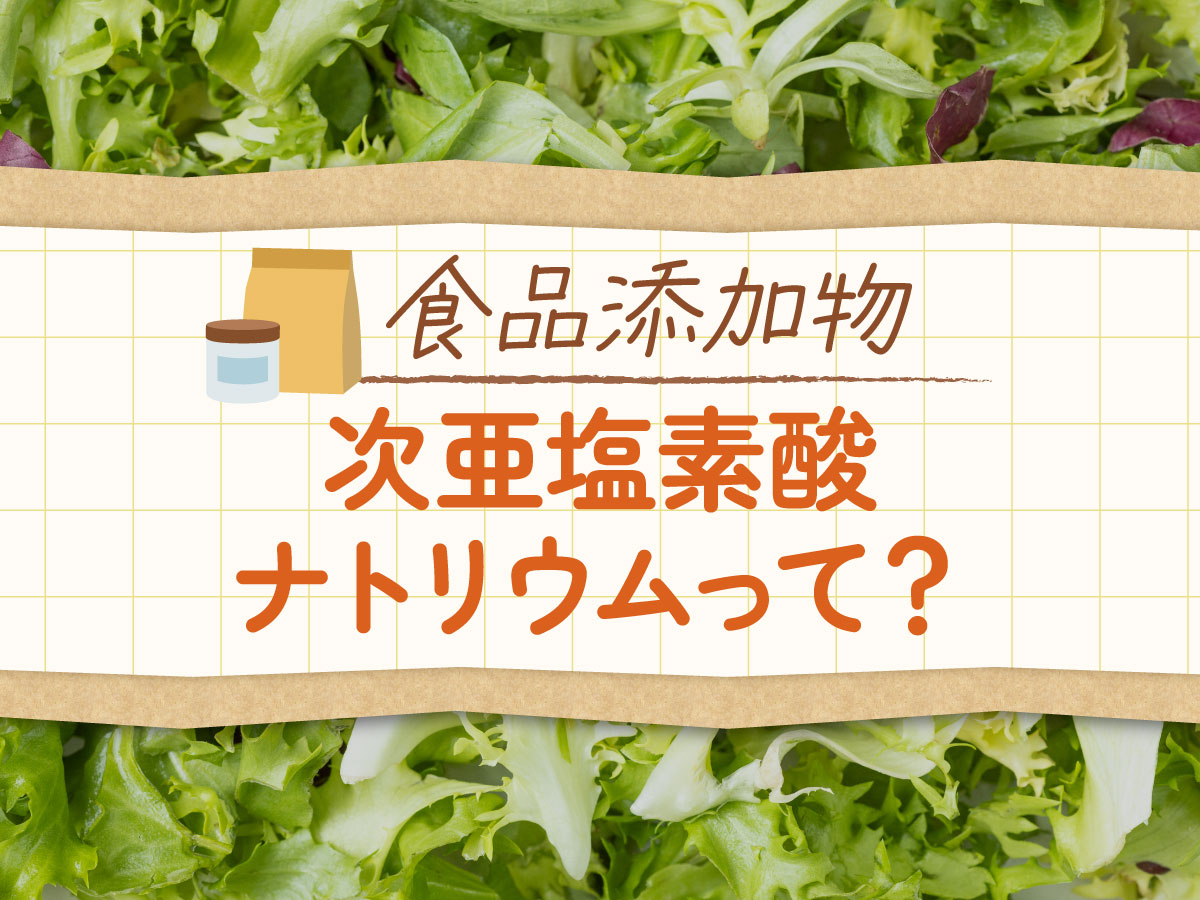



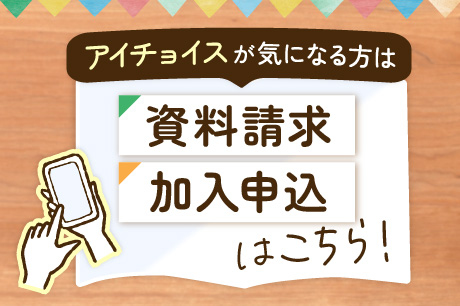




ビタミンC自体に発がん性はありません。
食品安全委員会の評価書でも、食品添加物として使用されるビタミンC(アスコルビン酸およびその塩類)に発がん性や生殖毒性・遺伝毒性は認められないと結論づけました。
むしろビタミンCは抗酸化作用により、発がん物質の一種であるニトロソアミンの体内生成を抑制する働きがあることも知られています。