食品添加物の役割とは?種類と用途についても解説!
スーパーで商品を手に取る際に食品表示を見て、不安になったりしませんか?
食品添加物には「安全性を確保する役割」や「食品をおいしく保つメリット」もある一方で、過剰摂取や特定の食品添加物にはリスクも。
食品添加物の役割、メリット・デメリット、そして体への影響についてわかりやすく解説します。
目次
食品添加物の役割
食品添加物は「体に悪い」というイメージがある人も多いと思いますが、実際には食品を安全に長持ちさせたり食感や味を向上させたりと、私たちの食生活を支える役割も担っています。
安価で入手できたり、大量生産を可能にしたりと、効率を重視して食品添加物に頼っている食品が多いのが実態です。
そもそも食品添加物とは?

食品添加物とは、食品の製造・加工・保存の過程で使用される物質のこと。
食品添加物は日本では食品衛生法によって厳しく規制されており、安全性の審査を経て認可されたものだけが使用可能です。
しかし、「認可されていること=長期的な健康への影響がないこと」ではありません。
具体的には、以下のような目的で使用されます。
- 保存料:微生物による食品の腐敗や変敗を防ぎ、食中毒の発生を防止する(例:ソルビン酸、安息香酸)
- 着色料:食品の色調を改善する(例:タール色素、カラメル色素)
- 甘味料:食品の甘味を付ける(例:アステーパルテーム、サッカリン)
- 酸化防止剤:食品の変質を防ぐ(例:ビタミンC、BHT・BHA)
- 乳化剤:乳化・分散・浸透・消泡などの目的で使用(例:グリセリン脂肪酸エステル、レシチン)
- 増粘安定剤:食品の食感向上(例:加工デンプン、グァーガム)
食品添加物の種類
食品添加物には、使用目的によっていくつかの種類があります。
種類 | 役割 | 代表的な添加物 |
| 保存料 | 食品の腐敗や細菌の繁殖を防ぎ、保存期間を延ばす | ソルビン酸、安息香酸 |
| 着色料 | 見た目をよくする | カロテン、クチナシ色素 |
| 甘味料 | 甘みをつける | アスパルテーム、スクラロース |
| 酸化防止剤 | 油脂の酸化を防ぐ、品質を守る | ビタミンC(アスコルビン酸)、BHA、BHT |
| 乳化剤 | 水と油を均一に混ぜ合わせ維持する | レシチン、グリセリン脂肪酸エステル |
| 増粘剤・安定剤 | 食品の食感や見た目をよくしたり、品質を保持したりする | キサンタンガム、グァーガム |
| pH調整剤 | 食品の酸性・アルカリ性を調整 | クエン酸、乳酸 |
食品添加物の役割とは?

食品添加物の主な役割は、食品の品質を維持し、安全性を高めることです。
パンにカビが生えたり、ジュースの風味が変化したりすることを防ぐ役割があります。
食品添加物の役割におけるメリット

食品添加物には、主に以下6つのメリットがあります。
- 食品の製造時や加工時に役立つ
- 食品の形状を保たせ独特の食感を持たせる
- 味と香りをよくする
- 栄養成分を補える
- 食品の品質を保つことができる
- 見た目をよくする
詳しいメリットは以下で解説します。
食品の製造時や加工時に役立つ

食品を製造・加工する際には、品質を均一に保ち、大量生産を可能にするために食品添加物が使われます。
添加物を使用すると、安定した品質の食品を効率よく製造することが可能に。
以下、具体例です。
- 豆腐を固める:にがり(塩化マグネシウム)が使われ、豆腐の形を保つ
- パンをふんわり仕上げる:膨張剤(ベーキングパウダー)を使用
- チーズをなめらかに加工:乳化剤が均一な状態を作り、クリーミーな口当たりに
このように、食品添加物は「工場での安定生産」と「消費者にとって均一な品質の食品を提供する」ために大きな役割を果たしています。
食品添加物の働きにより流通コストが抑えられる半面、わたしたちは知らず知らずのうちに多くの食品添加物を摂取しているのです。
食品の形状を保たせ独特の食感を持たせる

食品の形を整えたり、食感を向上させるために、乳化剤や増粘剤などの添加物が使用。
そのため、食材の組み合わせが可能になり、より多様な食品が作られます。
以下、具体例です。
- アイスクリームがなめらかになる:乳化剤や増粘剤を使用
- ゼリーやプリンのぷるぷる感を出す:ゲル化剤(ゼラチン・カラギーナン)を使用
- ソースやドレッシングが均一に混ざる:増粘剤や乳化剤で分離を防ぐ
これらの食品添加物を使用しないと、食感が悪くなったり、油と水が分離してしまったりすることも。
見た目や食べやすさの面を整える役割を担っています。
味と香りをよくする

食品の味や香りを引き立てるために、調味料や香料が使われます。
そのため、食品本来の風味を強調したり、よりおいしく感じさせたりすることがが可能に。
素材本来の味を楽しむために、これらの食品添加物を使用しない食品も販売されています。
以下、具体例です。
- ポテトチップスの「うま味」:グルタミン酸ナトリウム(MSG)が使用される
- フルーツジュースの香り:天然香料や合成香料で風味を強化
- お菓子の甘さを調整:人工甘味料(アスパルテーム・スクラロース)でカロリーオフ
栄養素を補完できる

一部の食品添加物は、栄養素の補完や強化目的で使用されるものもあります。
具体的には、以下のような使用方法です。
- パンやシリアル:ビタミンB1、B2、B6などを添加し、エネルギー代謝を助ける
- 牛乳:ビタミンDを添加して骨の健康をサポート
- プロテインバー:必須アミノ酸を含む添加物を使用して筋肉修復や成長をサポート
食品添加物を効果的に活用すれば、食事から効率よく健康維持に必要な成分を摂取することが可能になります。
食品の品質を一定に保ちやすくできる

食品の製造と供給において、毎回同じ品質を維持するのはとても重要です。
食品の品質を一定に保てる食品添加物を使用しなければ、味・見た目・食感を均一に保てなかったり、製造コストがかさみ物価高になったりする可能性があります。
たとえば、pH調整剤を使用すると、食品の酸性やアルカリ性のバランスを維持し、味や保存性を安定させられます。
他にも、ベーキングパウダーに含まれる膨張剤は、市販のパンやお菓子を製造するのに必須です。
カット野菜や果物の品質を保つためにも、酸化防止剤が使用される場合も。
しかし、アイチョイスでは、食材セット(ミールキット)を製造する際に、次亜塩素酸ナトリウムではなく、炭酸電解次亜水を使用するなど、食品添加物に頼らない方法を選択しています。
見た目を良くする

着色料や乳化剤、増粘剤などは食品の見た目や食感を良くするために使われます。
五感の中で、食品を前にしたときに一番影響するのが「視覚」だといわれているように、色合いだけで美味しそうに見えたり、不味そうに感じたりするんだとか。
食品の魅力を高めるために着色料などを使用しますが、必ずしも健康に必要なものではありません。
素材本来の色を活かした商品の販売も広がっています。
食品添加物の役割におけるデメリット
食品添加物には多くのメリットがある一方で、以下のような過剰摂取や一部の添加物の影響によるリスクも指摘されています。
- 過剰摂取になりやすい
- 一日の摂取許容量が明確に定まっている
- 食品添加物にアレルギー物質が含まれている可能性がある
- 人体に悪影響をおよぼす可能性がある
- 食品添加物以外の用途では使用できない
過剰摂取や特定の成分へのアレルギー反応、健康リスクなど、食品添加物を正しく理解しながらの利用が重要です。
過剰摂取になりやすい

食品添加物は便利な反面、過剰摂取のリスクがあります。
とくに、加工食品を頻繁に摂取すると、知らないうちに食品添加物の摂取量が増えてしまう可能性が。
たとえば、インスタント食品やコンビニ食品ばかり食べていると、保存料やpH調整剤、着色料など多くの食品添加物を摂取してしまうのです。
1日の摂取量を意識せずに食べ続けると、結果として肥満や高血圧などの生活習慣病につながる恐れも。
バランスのよい食事を意識することが大切です。
一日の摂取許容量が明確に定まっている

食品添加物は一日の摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake)が設定されています。
ADIとは「一生涯毎日摂取し続けても健康に影響をおよぼさない量」として、厚生労働省や世界保健機関(WHO)、国連食糧農業機関(FAO)などが基準を定めている指標です。
ADIは体重1kgあたりの摂取量で示され、たとえば体重50kgの人の場合、ADIが0.06mg/kgであれば、1日あたりの安全な摂取量は3mgとなります。
食品添加物は過剰摂取すると健康リスクがあるため、ADIが厳格に管理。
摂取量の目安を超えないように、食品の選択にも注意が必要です。
食品添加物にアレルギー物質が含まれている可能性がある
食品添加物の一部はアレルギーの原因となる場合も。
たとえば、以下の食品添加物が報告がされています。
| 分類 | 種類 | 影響 | 食品例 |
| 甘味料 | サッカリン・アスパルテーム | じんましんが起こることが報告されている | 菓子類 |
| 着色料 | 黄色4号 | 喘息が報告されている | ジャム、バター、チーズ、アイスクリーム、ケーキ |
| 保存料 | 安息香酸ナトリウム | 喘息が誘発されたり、アトピー性皮膚炎への関与が言われている | 醤油、マーガリン、シロップ、清涼飲料水 |
子どもやアレルギー体質の人は注意が必要です。
食品ラベルを確認し、アレルギーの原因となる添加物を摂取しないよう確認を行いましょう。
参考:ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、二酸化硫黄と亜硫酸塩(Sulfite)を対象とした欧州食品安全機構(EFSA)の最新の評価に関する情報(Nr. 039/2022)を公表|食品安全委員会,(参照2024-08-02)
参考:医薬品添加物と気管支喘息|榊原博樹 他,(参照2024-08-02)
人体に悪影響をおよぼす可能性がある
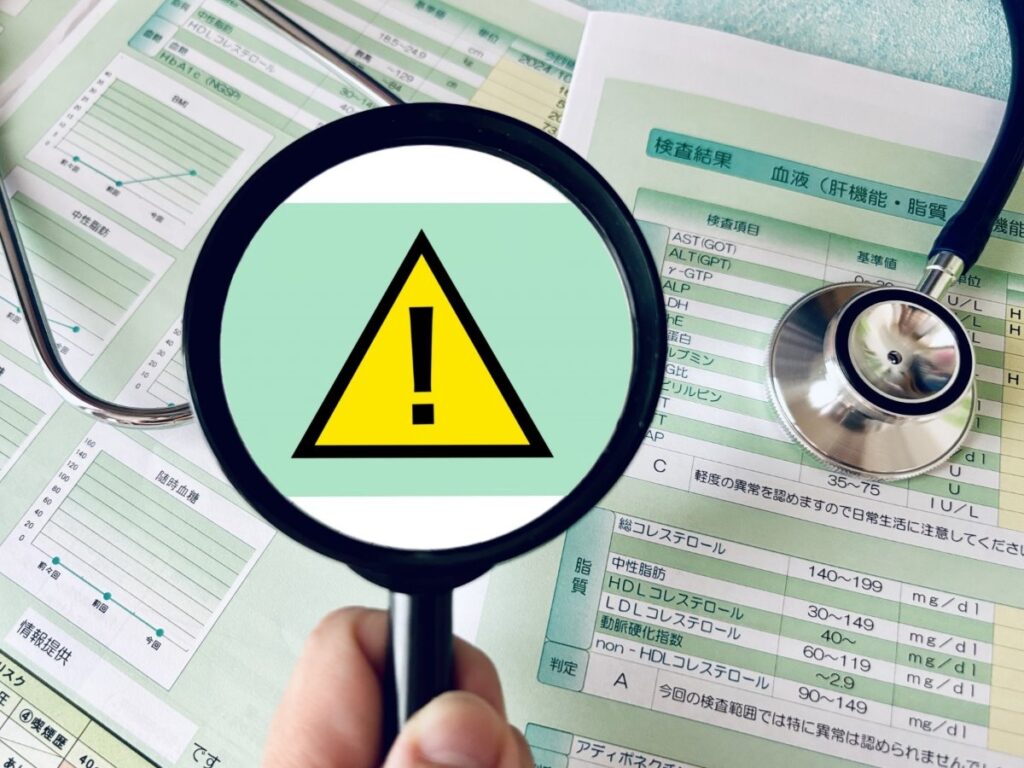
食品添加物の中には、長期的に摂取すると悪影響をおよぼす可能性があると指摘されているものもあります。
- 安息香酸ナトリウム:高濃度で摂取するとビタミンCと反応し、発がん性物質(ベンゼン)を 生成する可能性
- タール色素(赤色102号、黄色5号など): アメリカなどの一部の国では使用禁止
- BHA・BHT(酸化防止剤):アメリカで乳幼児用食品への使用が禁止
日本では基準を設けて使用が許可されていますが、体に影響がある可能性についての意識が大切です。
参考:清涼飲料水中のベンゼンについて|厚生労働省,(参照2024-08-02)
参考:海外食品添加物規制早見表|JFIA,(参照2024-08-02)
食品添加物以外の用途では使用できない

食品添加物は、食品のみに使用が許可され、医薬品や化学製品としては使用できません。
これは、食品添加物が特定の環境下で予期せぬ影響をおよぼす可能性があるためです。
日本では食品衛生法によって厳格に管理されており、安全性が確認されたもののみが許可されています。
食品添加物の役割とリスク分析について
日本で使用されている食品添加物は厳格な安全基準のもとで管理されており、一定のルールに従って使用されています。
日本だけでなく海外の機関でも、科学的根拠に基づくリスク分析によって安全性を評価し、危機的な基準を設けているのです。
食品添加物は食の安全を守る役割がある

食品添加物は、「食品の安全を守るために必要なもの」という側面があります。
保存料や酸化防止剤がなければ、食品の腐敗や劣化が早まり、食中毒のリスクが増してしまうことも。
以下のような食品添加物は、食中毒や食品の劣化を防ぐ役割を果たしています。
- 保存料(ソルビン酸・安息香酸):微生物等による食品の腐敗・変敗を防止し、食中毒 のリスクを軽減
- 酸化防止剤(ビタミンC・BHT・BHA):食品の変質を防ぐ
- pH調整剤:食品を適切なpH領域に保つ
「リスク分析」によって安全性が守られている

日本で使用される食品添加物は、厚生労働省と食品安全委員会が科学的なデータをもとに厳しく審査し、安全性を確認したものだけが認可されています。
リスク分析には、以下の3つのステップがあります。
リスク評価(科学的評価)
「ハザードの特定・ハザードの特性評価・ばく露評価・リスクの判定」の4つの段階 を含む評価を行うこと。
リスク管理(適切な企画や基準の設定)
リスクを低減するために適切な企画や基準の設定について、科学的な妥当性をもって検討・実施すること。
リスクコミュニケーション(関係者との情報・意見交換)
検討すべきリスクの特性やその影響に関する知識を深め、その過程で関係者間の相互理解を深め、信頼を構築し、リスク管理やリスク評価を有効に機能させること。
これらの手順を通じて、食品添加物のリスク分析は食品の安全性を確保し、消費者の健康を守るために重要な役割を果たしているのです。
食品添加物のリスク分析は、各国ごとに基準が異なるため均一に比較することはできません。
参考:用語集検索(リスクアナリシス(リスク分析)の考え方) | 食品安全委員会 – 食の安全、を科学する ,(参照2025-02-24)
食品添加物の役割に関するよくある質問

食品添加物のメリットとデメリットは?

食品添加物がないとどうなる?
食品添加物が一切使用されない場合、食品の保存性や品質が大幅に低下する可能性があります。

加工食品における食品添加物の役割は?
加工食品は、食品添加物を活用して保存性・汎用性・味の均一化を実現しています。

食品添加物の役割を正しく理解して、食生活をより楽しく安全に送ろう!

食品添加物には、「保存性の向上」「食感や味の調整」「栄養価の補完」など、私たちの食生活を支える重要な役割があります。
一方で、過剰摂取や特定の食品添加物の影響についても注意が必要です。
すべての食品添加物を避けることは難しいですが、意識して選択することで摂取量を減らすことができます。
アイチョイスでは、下記のような食品添加物に頼らない食品を取り扱い中です。
- リン酸塩・発色剤・保存料不使用のハム・ソーセージ
- 着色料・香料・増粘剤不使用のジャム
- 化学調味料・乳化剤不使用の冷凍食品
その他にも食品添加物に頼らない商品を多数取り扱いしています。
毎週約800商品がカタログに掲載され、全原材料の公開を実施。
もちろん全ての商品が化学調味料不使用です。
まずはおためしボックスでアイチョイスの商品を試してみませんか?
※「化学調味料」は「調味料(アミノ酸等)」を端的に伝える用語として使用しています。






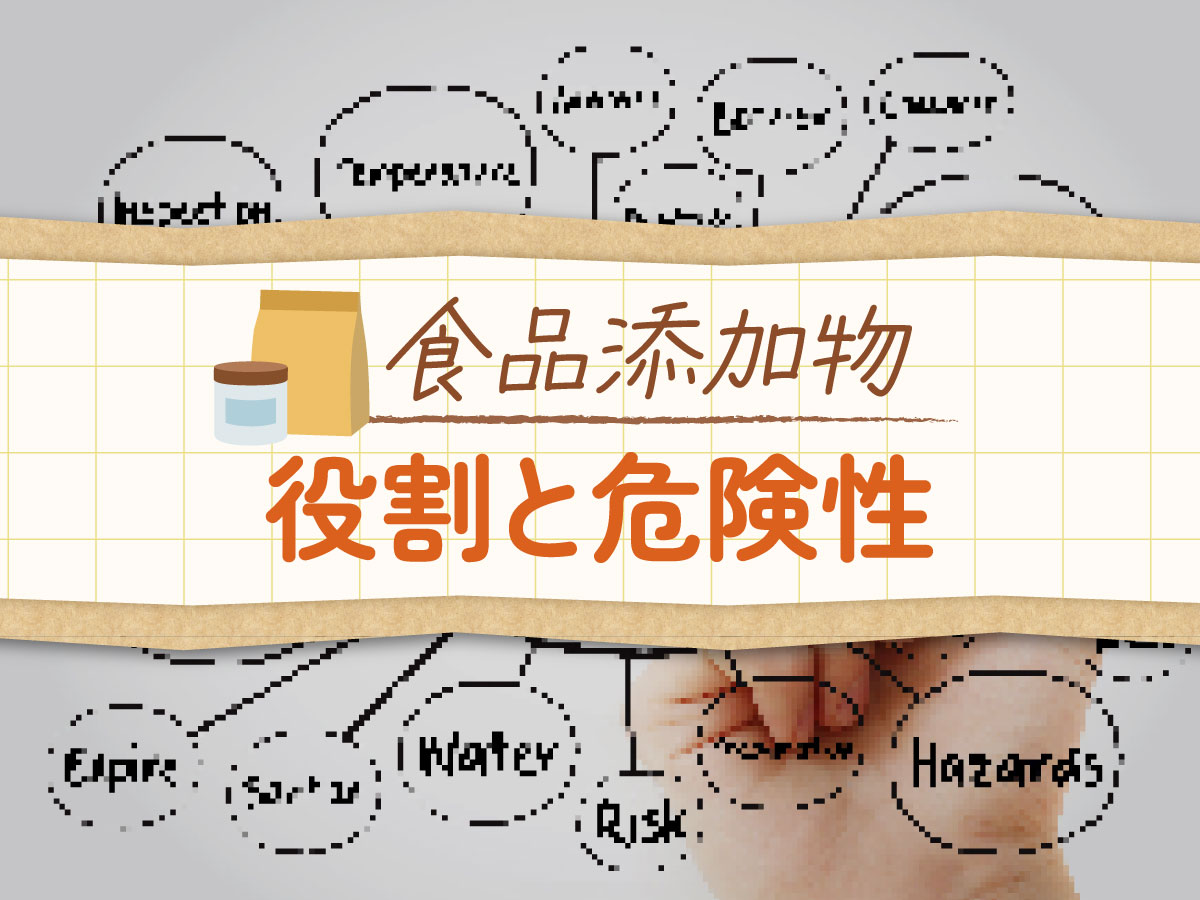

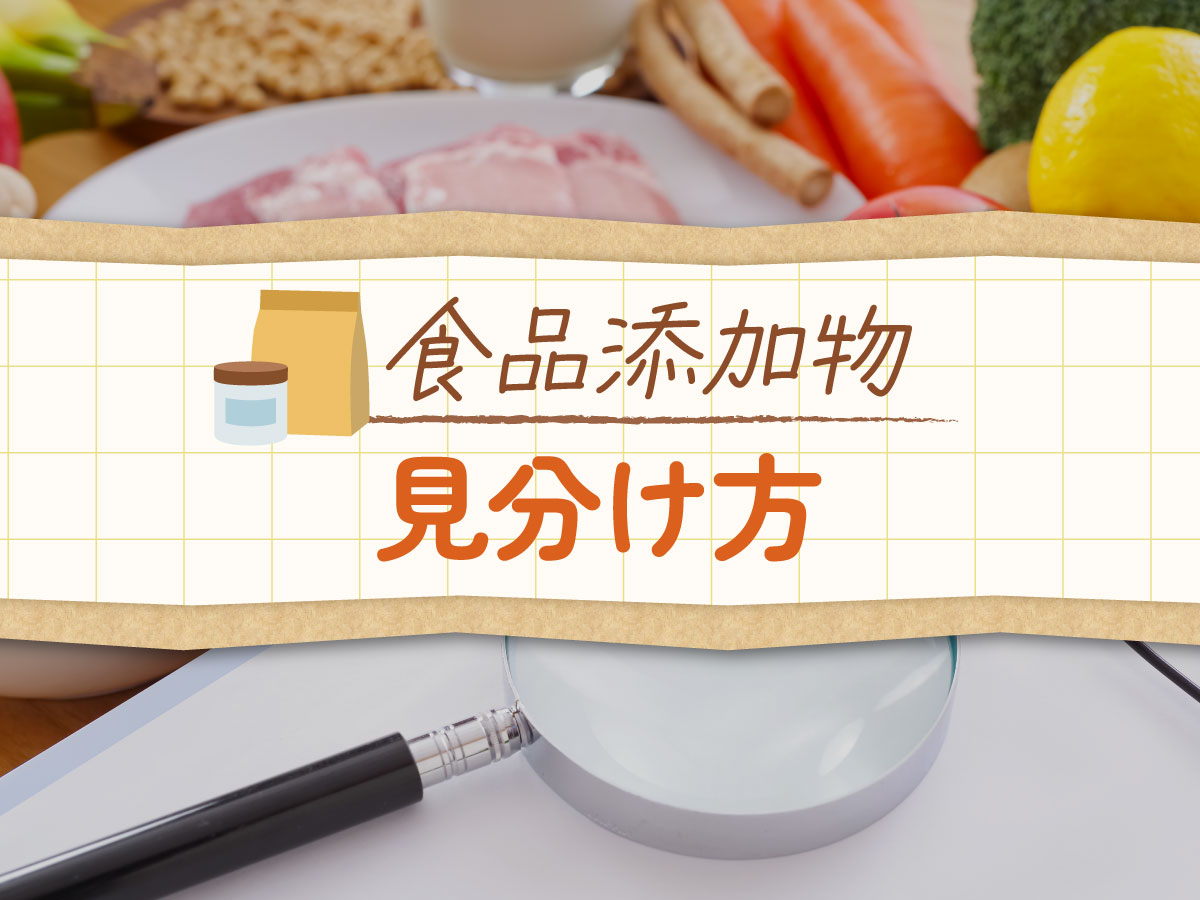

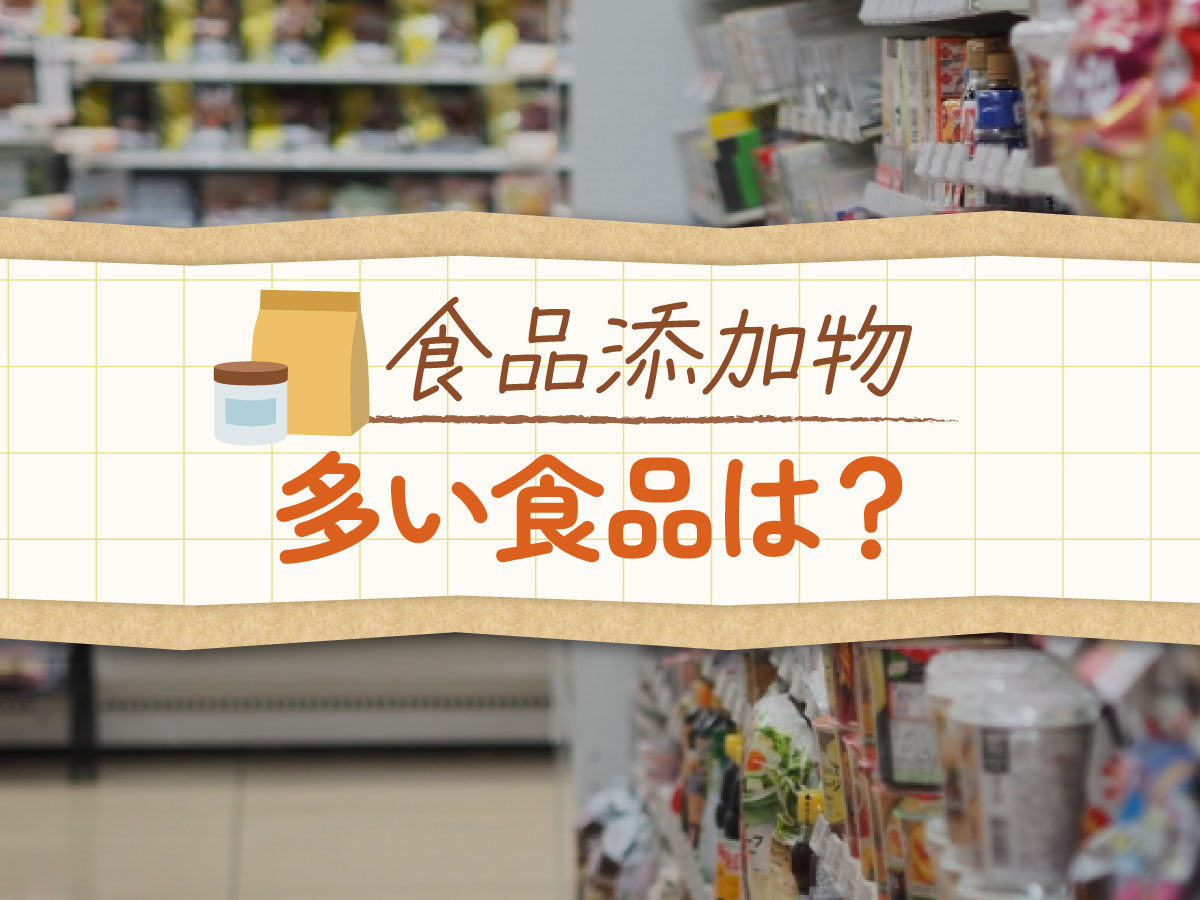
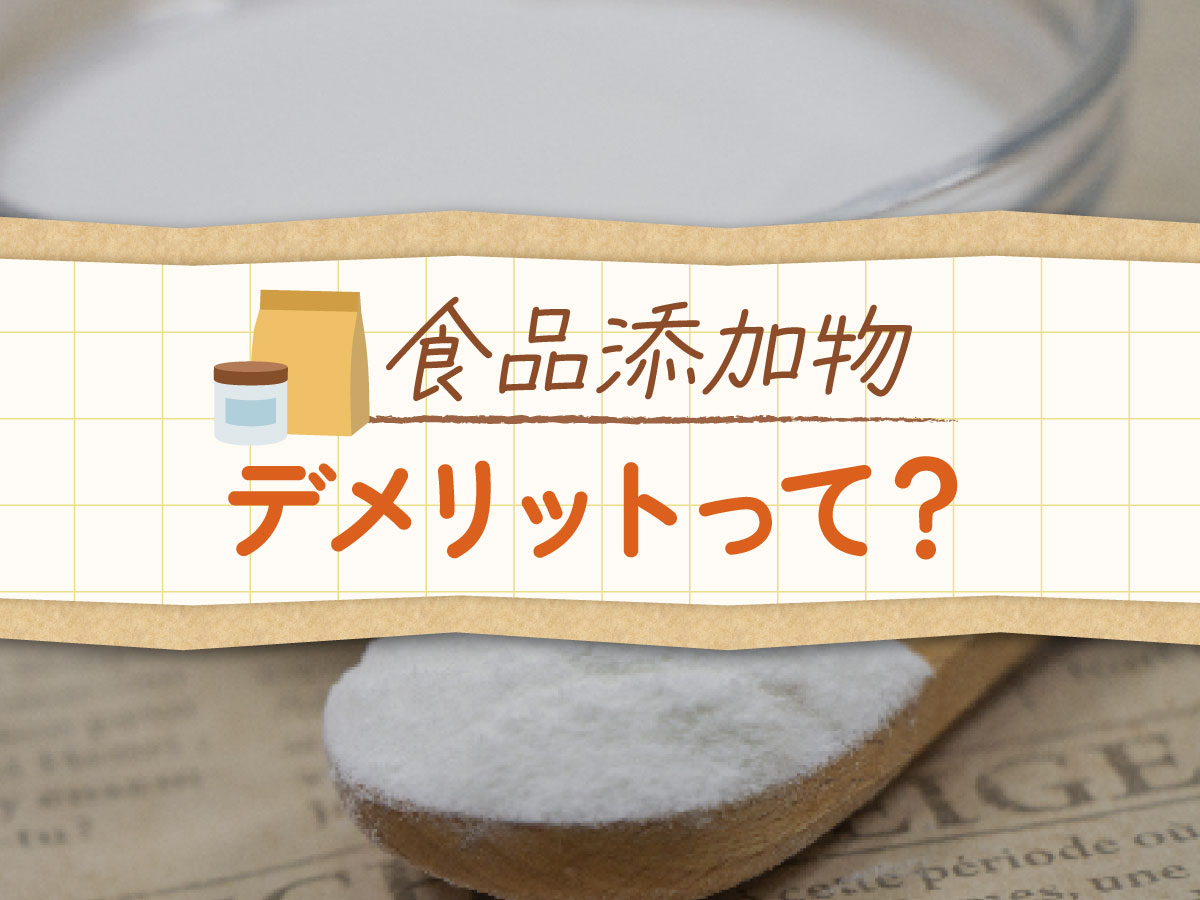
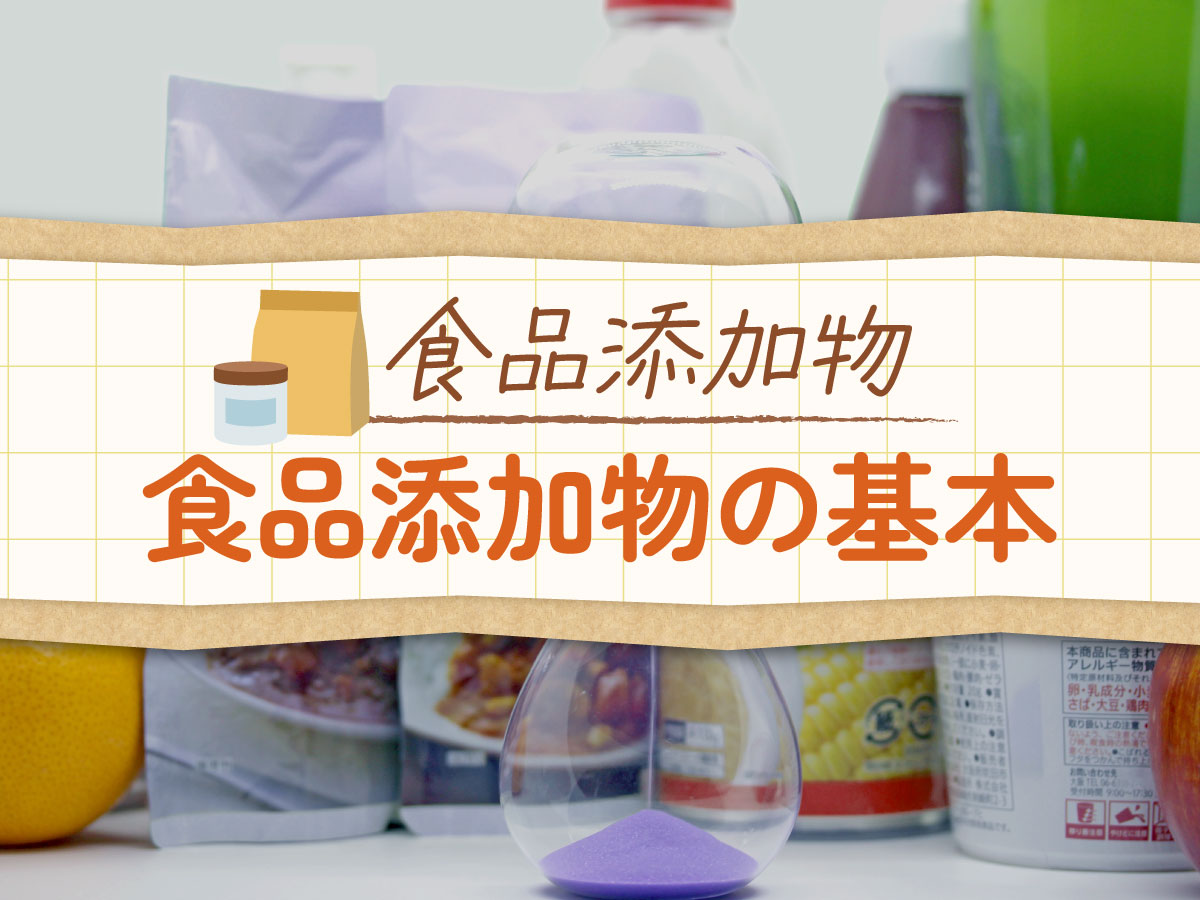




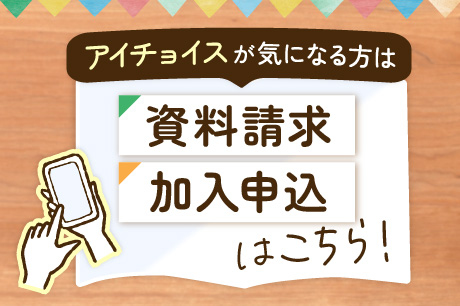




大量生産のコスト削減や食品の品質を維持させること、見た目や味・香りを整えることなどがメリットとして挙げられます。
デメリットとしては、知らず知らずのうちに過剰摂取してしまったり、アレルギーや人体に悪影響を及ぼしたりする可能性も。