有機栽培の野菜が栄養価が高くなりやすい理由|オーガニックとの違いやメリットデメリット
目次
そもそも有機野菜とは?

有機野菜は魚粉や油粕など植物性、または動物性由来の有機物肥料を主として、栽培された野菜のことです。
おもに化学的に合成された肥料や節減対象農薬を使っていないのが特徴。
農林水産省が定めた「有機JAS規格」の基準に適合した農産物のみが認証を得られ、代表的な基準としては次の3点が挙げられます。
- 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じている
- は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しない
- 組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わない
有機野菜は自然がもつ力を活かして、環境に配慮した手法で栽培されている野菜といえます。
しかし、有機野菜とはいえ農薬を一切使っていないわけではありません。
有機JAS規格で認められた節減対象農薬は、栽培において使用可能となります。
引用:【有機農業関連情報】トップ ~有機農業とは~:農林水産省(参照2025-04-11)
有機野菜・オーガニック・無農薬との違い

まず有機野菜は、農林水産省が定めた「有機JAS規格」の条件を満たすことが必須です。
条件を満たせば有機野菜として認定され、その証明として「有機JASマーク」を表示できます。
オーガニック野菜については有機野菜と同義です。
無農薬野菜とは、栽培期間中に農薬を使わずに栽培した野菜を指します。
ただし、土壌や野菜そのものにまったく農薬がない状態で栽培されたとはいい切れないため、消費者に誤解を与えてしまう可能性も。
農林水産省は「栽培期間中農薬不使用」と表示することを推奨しています。
参考:生き物にやさしい日本を残したい|農林水産省(参照2025-04-11)
参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン:農林水産省(参照2025-04-11)
有機野菜が栄養価が高いと言われる理由
化学肥料や農薬を使わずに作られた有機野菜は、一般的な野菜よりも栄養が豊富なイメージがありますよね。
ある実験では、慣行栽培の野菜よりも有機野菜のほうが栄養価が高い、というデータも出ています。
しかし、有機野菜のすべてにそのようなデータが出ているわけではなく、野菜の種類や、栽培方法によって栄養価は違うよう。
有機野菜の栽培方法や、調査・論文の観点から有機野菜が高栄養価といわれる理由は以下の通りです。
化学肥料を使わない自然由来の栽培方法だから

化学肥料や農薬を使わない有機野菜は、野菜自体が害虫や病気から身を守ろうとする性質が強いといわれています。
生長の過程で、有機野菜は「ファイトケミカル(※)」を生成。
ファイトケミカルとは第7栄養素と呼ばれるほど注目を集めており、とくに野菜の皮に多く含まれています。
有機野菜は皮ごと食べられるため、これらの高い栄養価を効果的に摂取できるのです。
ファイトケミカルの含有量は、有機野菜のほうが一般的な野菜と比較して多いことが報告されています。
また、良質な土の養分を吸収して育った有機野菜は、栄養価が高くなるとの見方も。
自然本来の土壌で、肥料やミネラルを適切に施して栽培された有機野菜は、大量生産された野菜に比べると、ゆっくりとしたスピードで生育。
その分、有機野菜は豊かな土壌成分をしっかりと吸収するため、栄養価の高まりが期待できるのです。
※ファイトケミカル・・・大きく5種類の栄養素に分けられ、代表的なものとして、ポリフェノール(例:アントシアニン、イソフラボン)やカロテノイド(例:リコピン、β‐カロテン)などが挙げられる。
参考:ファイトケミカルとは | 健康長寿ネット(参照2025-04-11)
有機野菜の栄養価が優位に高いという調査報告も

有機野菜の栄養価は本当に高いのでしょうか。
さまざまな調査結果が出ていますが、今回はイギリスの調査結果をご紹介。
有機栽培は、病害虫や雑草を化学農薬で防除しないので、一般的な栽培よりも農産物がさまざまなストレスを強く受けやすい状況にあります。
そのストレスを回復させるために、抗酸化物質や二次代謝産物が増加するため、有機野菜の栄養価が高いとされるのです。
作物本来の持つ、栄養を蓄えようとする力を引き出すことで、有機野菜の栄養価が高くなるといわれています。
参考:有機と慣行の作物で、抗酸化物質、カドミウム、残留農薬含量に 有意差を確認|Alan Dangour 他(参照2025-04-11)
有機野菜のメリット・デメリット
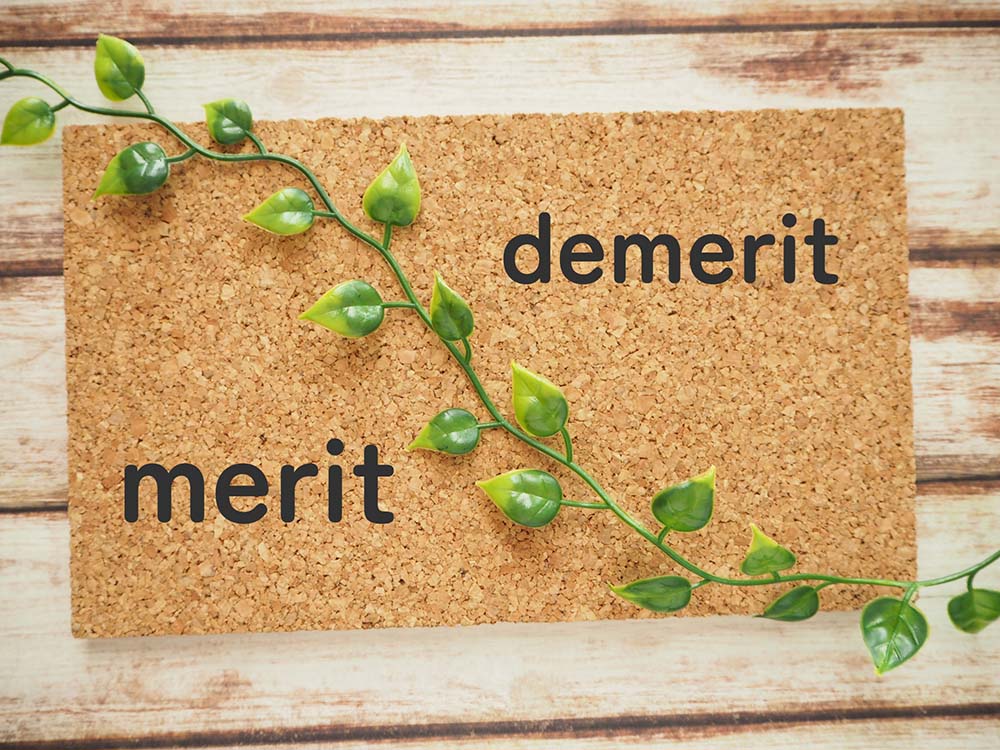
「安全そう」「環境に配慮されている」などのイメージをもたれている有機野菜ですが、メリット、デメリットの両面があります。
まず、メリットとしては「有機JASマーク」のついた付加価値の野菜であること。
化学肥料や節減対象農薬を使わないため、土壌環境や生物多様性を守りながら環境にやさしい農業をめざせます。
デメリットとして、一般的な栽培方法に比べて病害虫や雑草対策が大変です。
それゆえに手間のかかる一方で収量を上げるのが難しい傾向にあります。
有機野菜のデメリットはおもに「高価格」「見た目の不揃い」「出荷量の少なさ」です。
以下、具体的に解説します。
有機野菜のメリット

有機野菜のメリットは下記の4点です。
- 健康面における農薬リスクの低減
- 有機野菜がもつ栄養価の高さ
- 環境に配慮された栽培方法
- 味と品質のよさ
化学的に合成された肥料や節減対象農薬を使っていない有機野菜を摂取することで、体内への化学物質の取込みが低減されます。
同時に、有機栽培は土壌や水質の汚染が少なく、生き物の住みやすい環境、生物多様性が保たれて持続可能な農業が実現可能に。
有機農産物は栄養バランスの取れた土壌で作物本来の力を引き出す栽培方法のため、一般野菜よりも高栄養価です。
なんといってもアミノ酸系の有機質肥料を使用した作物は、野菜本来の旨味が向上。
硝酸イオン(※)の量が抑えられ、苦みやえぐみの少ない野菜が育ちます。
※硝酸イオン・・・野菜の成長に不可欠な窒素成分だが、過度に吸収すると苦みやえぐみの原因に。
有機野菜のデメリット
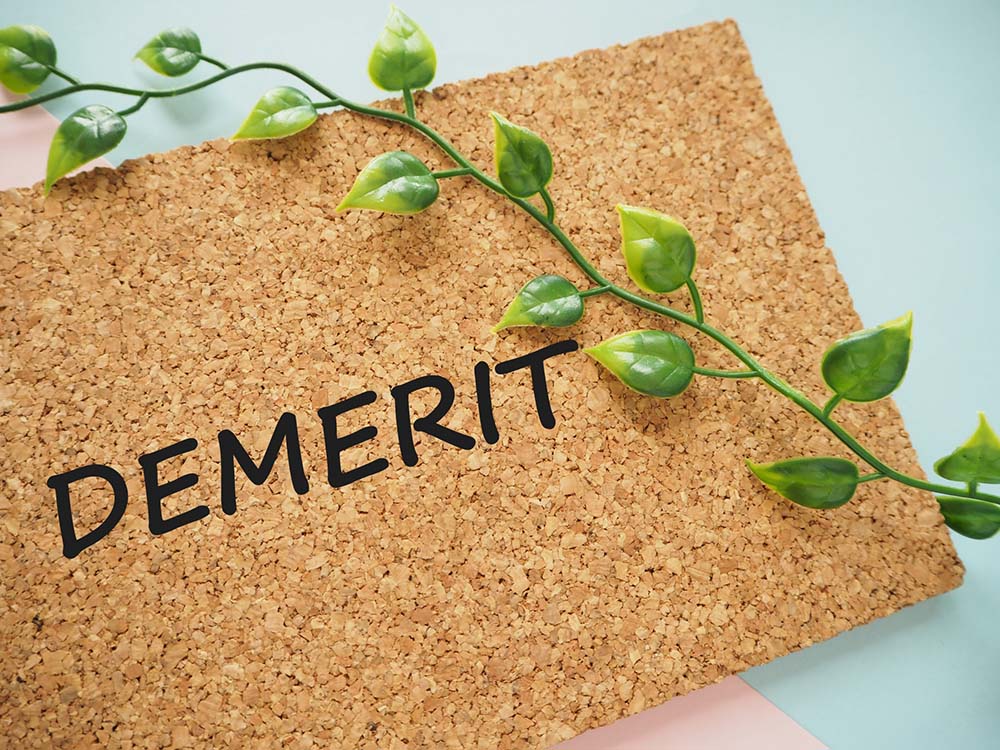
栽培の観点から、有機野菜のデメリットは以下の6点が挙げられます。
- 高価格
- 安定供給の難しさ
- 不揃いな見た目
- 病害虫対策の課題
- 不安定な収穫量
- 認証コストの負担
高温多湿な日本で、農薬を使用せずに野菜を栽培することは効率的な栽培方法ではないため、供給も不安定になります。
一般的な野菜に比べると、自然由来の栽培は生育が不安定になるため、色や形などが不揃いになることも。
病害虫被害や見た目の不揃いにより、品質規格に合わない場合は一般流通に不適合な野菜が多くなります。
有機JAS規格内で決められた農薬しか使えないことにより、病害虫を防げないケースもああるのです。
害虫や雑草対策には手間や時間、労力がかかります。
そのため、価格も高くなってしまいがちです。
有機JAS認証取得は、審査費用などが高額です。
取得を諦める農家さんもいるため、有機野菜の栽培にはさまざまなハードルがあることがわかります。
アイチョイスでは、栽培履歴を明確にし、有機JAS認証を取得していなくても、有機栽培と同等の栽培を行った農産物に対して「有機栽培レベル」と表記。
取り扱っている50%以上の農産物が「有機栽培レベル」なのです。
有機野菜が体に悪い・リスクが高いといわれる理由

「有機野菜が体に悪い、リスクが高い」という理由には以下の3つがあります。
- 有機栽培でも使用できる農薬があること
- 有機質肥料に含まれる硝酸態窒素の影響
- 病害虫発生や拡大のリスク
まず、有機栽培だからといって農薬をまったく使わないわけではありません。
有機栽培でも自然由来の農薬などは使用が可能。
次に、有機質肥料に含まれる硝酸態窒素(※)ですが、野菜の成長には必要なもので、健康への悪影響がある可能性は低いです。
生産者側のリスクとして、農薬を使用しない除草は時間がかかるため、農家さんの負担も大きく、さらに農産物に病害虫が発生しても農薬を使用できないので、大変なリスクに。
以上のことから、「有機野菜が体に悪い、リスクが高い」などといわれています。
買う側ではなく、生産者側にデメリットがあるといえるでしょう。
※硝酸態窒素・・・肥料に含まれる成分で、作物の茎葉の成長を促す。
栄養価の高いおすすめ野菜を7つ紹介!

野菜は、ビタミンやミネラルなどの栄養素が豊富に含まれているため、バランスのよい食事には不可欠です。
特定の種類だけを食べ続けるより、いろいろな種類の野菜を食べるのがおすすめ。
今回は、栄養価の高い野菜を7つご紹介します!
それぞれ旬の時季になると店頭などで見かける機会も増えるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
クレソン:栄養価が高く、ピリッとした風味で料理が引き立つ

ピリッとした辛味が特徴的なクレソン。
ステーキやハンバークによく添えられていて、料理の脇役的存在のようなイメージがありますよね。
実はクレソンには17種類もの栄養素が含まれており、さまざまな効果が期待できるんです。
具体的にはビタミンC、カルシウム、鉄分、カリウム、マグネシウム、葉酸など。
中でもβカロテンには抗酸化作用が含まれ、がんや老化を防ぐ効果が期待されています。
白菜:低カロリーながら栄養価が高い冬の定番野菜

白菜は冬の代表的な野菜の一つです。
成分の95%は水分で栄養価が低めの野菜だと思われがちですが、ビタミンCやカリウム、カルシウムなどが豊富に含まれています。
白菜100gあたりのカロリーは13kcalで、糖質は2.0g。
低カロリー・低糖質で、ダイエットにもおすすめの野菜です。
白菜は加熱したり長時間ゆでたりすると、ビタミンCやカリウムなどがゆで汁に流出してしまいます。
しっかりと栄養素を摂るには、煮汁ごといただく鍋物やスープなどのメニューがおすすめです。
参考:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年:文部科学省(参照2025-04-11)
ほうれん草:栄養バランスに優れた万能野菜

おひたしや炒め物、みそ汁の具など使い道が豊富なほうれん草。
葉先から根元まで多くの栄養素が含まれており、残さずすべて食べられます。
ほうれん草にはたんぱく質やビタミンA、C、K、鉄分、カルシウムなど約20種類の栄養素が豊富に含まれており、まさに万能野菜。
中でも、血圧抑制の効果があるカリウムの含有量が高く、100gあたり690mg含まれています。
ブロッコリー:茎まで栄養の宝庫、無駄なく食べられる

野菜の中でも、ビタミンA、C、K、葉酸、カリウム、鉄分の含有量が多いブロッコリー。
中でも、スルフォラファンという抗酸化成分が多く含まれており、がんの予防、免疫力の強化、老化防止にも効果が期待されるため、こまめに摂取したい野菜です。
実は、ブロッコリーは茎や芯も食べられます。
茎にも、ビタミンCやポリフェノールが花蕾(からい)と同等に含まれており、抗体産生増強効果があると示唆されたという報告も。
独特の食感と甘さが特徴で、硬い周囲をむいてから薄切りにすると調理しやすくなりますよ。
参考:ブロッコリーのビタミン C,S-メチルメチオニン,ポリフェノール 含有量の部位別解析と細胞機能への影響|上田京子 他(参照2025-04-11)
ビーツ:鮮やかな色と豊富な栄養価が特徴的

料理を華やかにしてくれる色鮮やかなビーツ。
特徴的な赤色には、抗炎症作用のあるポリフェノールの一種が含まれています。
このほか、ビーツには、葉酸、鉄分、亜鉛、マグネシウムなど、私たちの健康を支えるうえで重要な栄養素が豊富に存在。
中でもカリウムは、体内から塩分の排出を促して血圧を下げる効果が期待されています。
参考:Think and GrouRicci|機能性成分に注目集まる野菜「ビーツ」(参照2025-04-11)
モロヘイヤ:栄養価が高く、夏バテ予防にも効果的

栄養価の高さからスーパーフードとしても注目を集めているモロヘイヤ。
刻むとネバネバとした粘り気が出てくるのが特徴的です。
モロヘイヤはエジプト原産で、免疫力アップに寄与する栄養素が豊富。
βカロテンやビタミンB2はほうれん草の約2倍、カルシウムは約5倍含まれています。
その他、夏バテ予防に効果が期待できるビタミンC、血圧上昇を抑制するカリウム、貧血予防に効果的な鉄分も豊富です。
参考:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年:文部科学省(参照2025-04-11)
にんじん:βカロテンが豊富で、栄養価の高さが際立つ野菜

にんじんは野菜の中でも栄養価の高さが際立っています。
とくにβカロテンが豊富で、体内でビタミンAに変換され目の角膜を正常に保ち、眼精疲労の予防や皮膚、粘膜の健康に役立つ野菜です。
また抗酸化物質が豊富で免疫機能の強化および、がんや心疾患リスクの低減が期待されています。
そのほか食物繊維も多く含まれ、消化促進を促し便通の改善や腸内環境を整える働きも。
にんじんは、私たちが積極的に摂取したい野菜のひとつです。
参考:健康栄養支援センター|カロテンの宝庫「にんじん」(参照2025-04-11)
参考:e-ヘルスネット|緑黄色野菜(参照2025-04-11)
有機野菜の栄養価に関するよくある質問
有機野菜の栄養価に関する疑問についてまとめました。
有機野菜の何がそんなにいいの?

有機野菜はなぜ体にいい?
栽培の過程で基本的に化学肥料や節減対象農薬を使わないため、化学物質の体内摂取量が減り、健康への影響も軽減。
また、食品の安全性も増すため、有機野菜は体にいいとされています。

有機栽培の野菜のメリットは?
化学肥料や節減対象農薬を使用していない栽培方法のため、消費者に安心感を与えます。
良質な土壌成分を吸収しながら、農作物の本来の速度でおいしさを蓄えながら成長。
化学肥料不使用のためえぐみや苦みも少なく、野菜の旨味が増します。

栄養価が1番高い野菜は何ですか?
アメリカの研究で高栄養価野菜といわれているのは、クレソンです。
世界で栄養素密度(※)が最も高く、各食品の栄養素密度では合計スコアで100点を獲得しました。
白菜(91.99点)のほかビーツ(87.08点)、ほうれん草(86.43点)よりも高い栄養価であることが証明されています。

※栄養素密度・・・食品の一定のエネルギーあたりに含まれる栄養素の量
参考:慢性疾患の予防 |強力な果物と野菜の定義:栄養密度アプローチ – CDC,(参照2025-04-11)
“有機野菜=栄養価が高い”との報告も!メリットの多い有機栽培

栄養価が高いとのイメージがある有機野菜。
良質な土壌でゆっくり育つ有機野菜は、旨味を十分に蓄えて味と品質が向上し、栄養価が高まります。
また、化学肥料や農薬などを使わずに栽培した野菜を食べることは、体内への化学物質の摂取が減少し、健康に寄与することにもつながるのです。
有機野菜における大きなメリットとしては、厳正な審査を経て「有機JASマーク」が認証されることで、消費者からの高い信用を得られること。
環境にやさしい、持続可能な農業が営めるといったこともポイントです。
以上のことから、有機野菜にはメリットが多いことがわかります。
有機野菜は一般的な野菜と比較して、単価が高くなりがちであるといったデメリットも。
アイチョイスでは、誰もが有機野菜を食べられるよう、生産者と一緒にこれからも取り組んでいきます。
有機野菜を気軽に試してみたいというかたは、加入前の方限定でお申し込みいただける『おためしボックス』をぜひご活用ください。






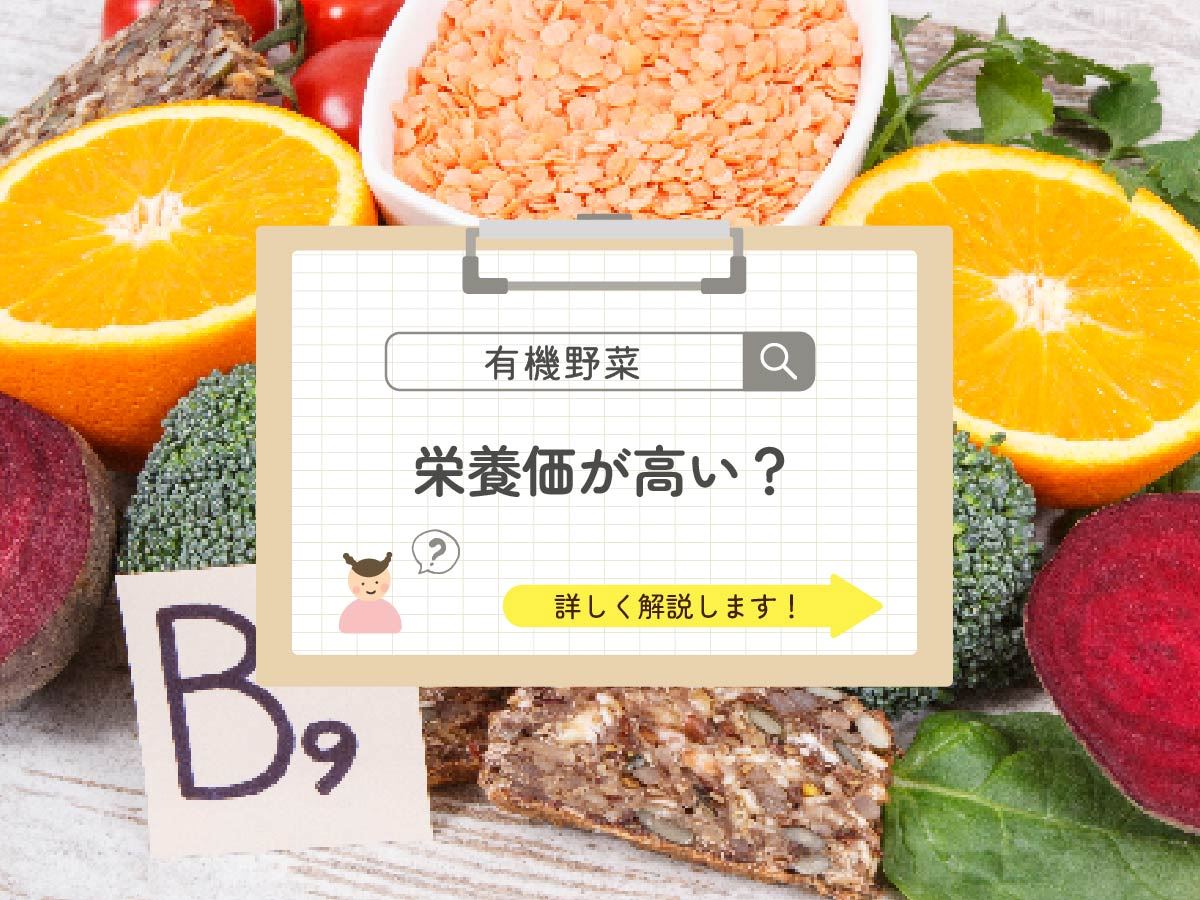

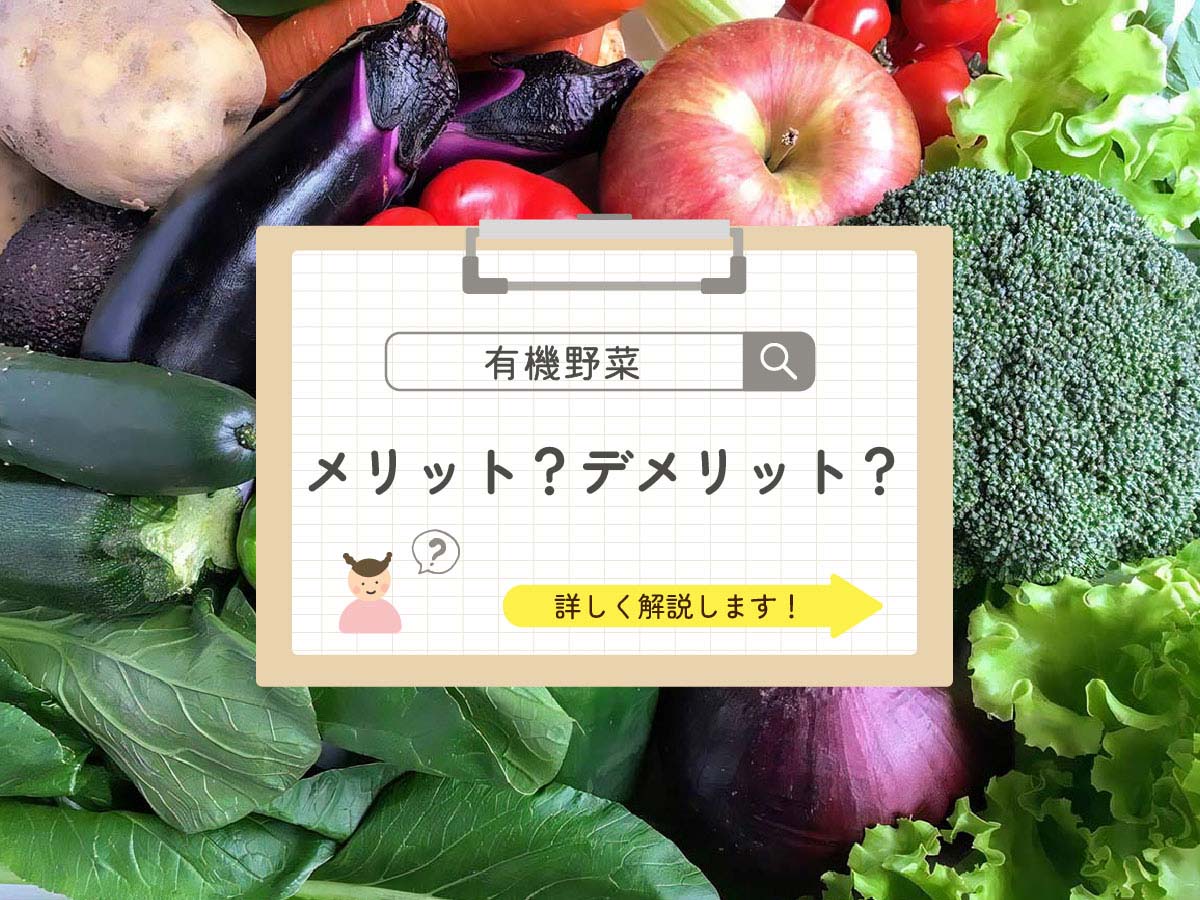
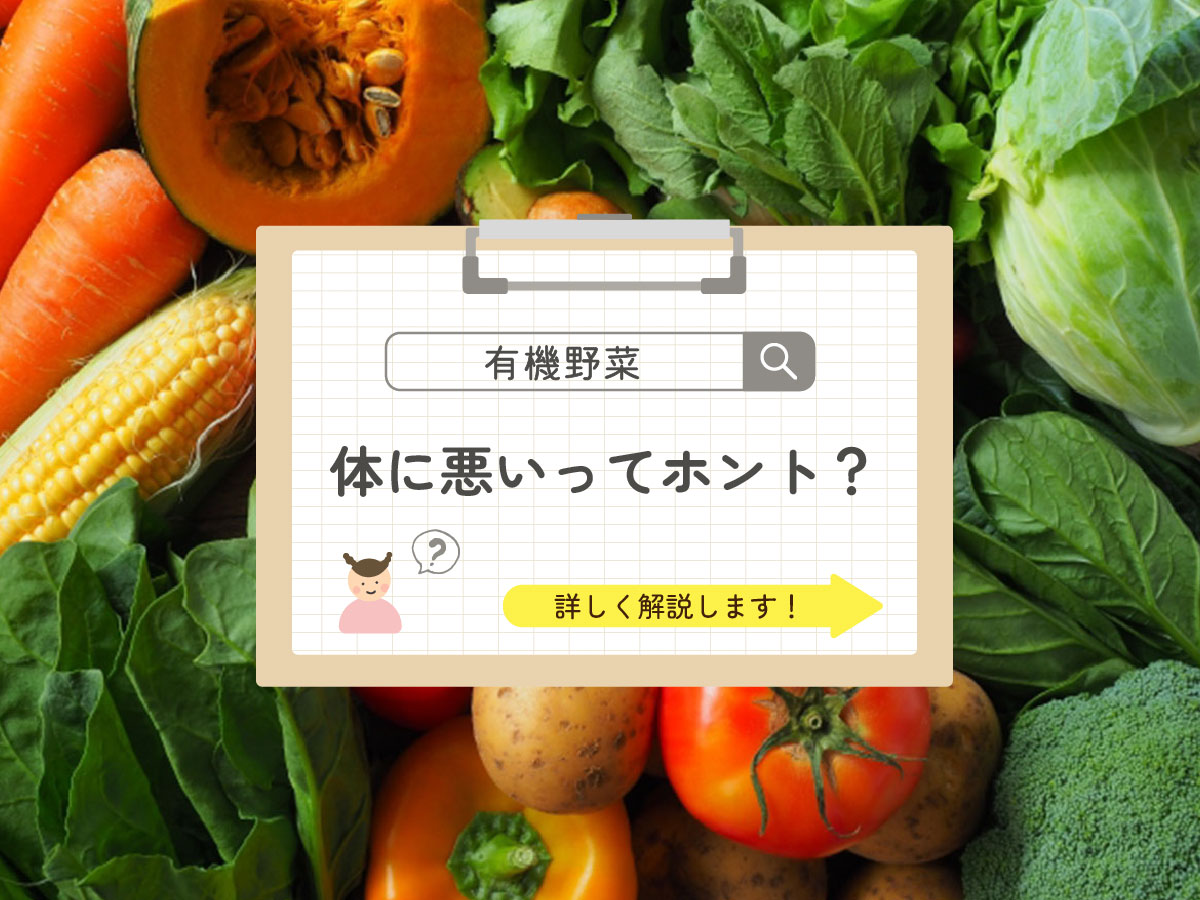
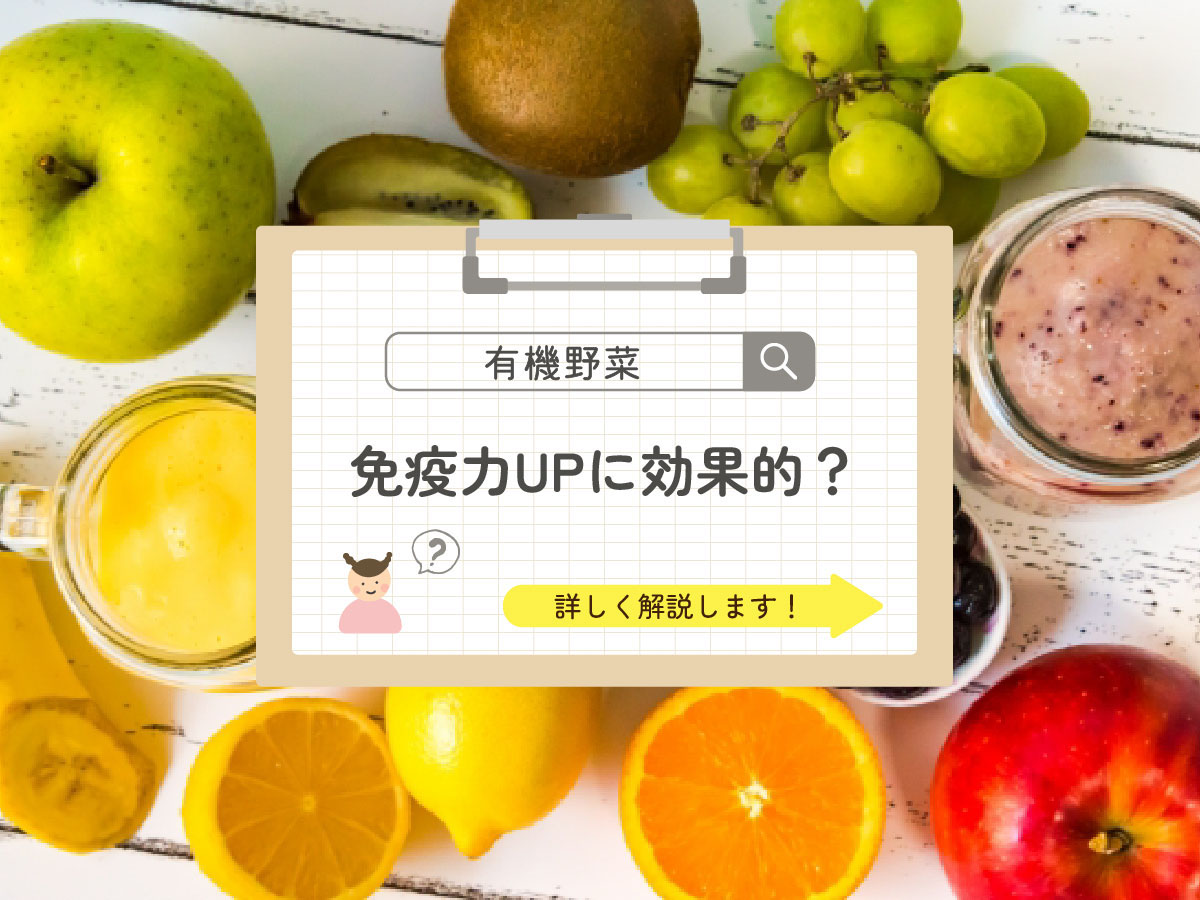
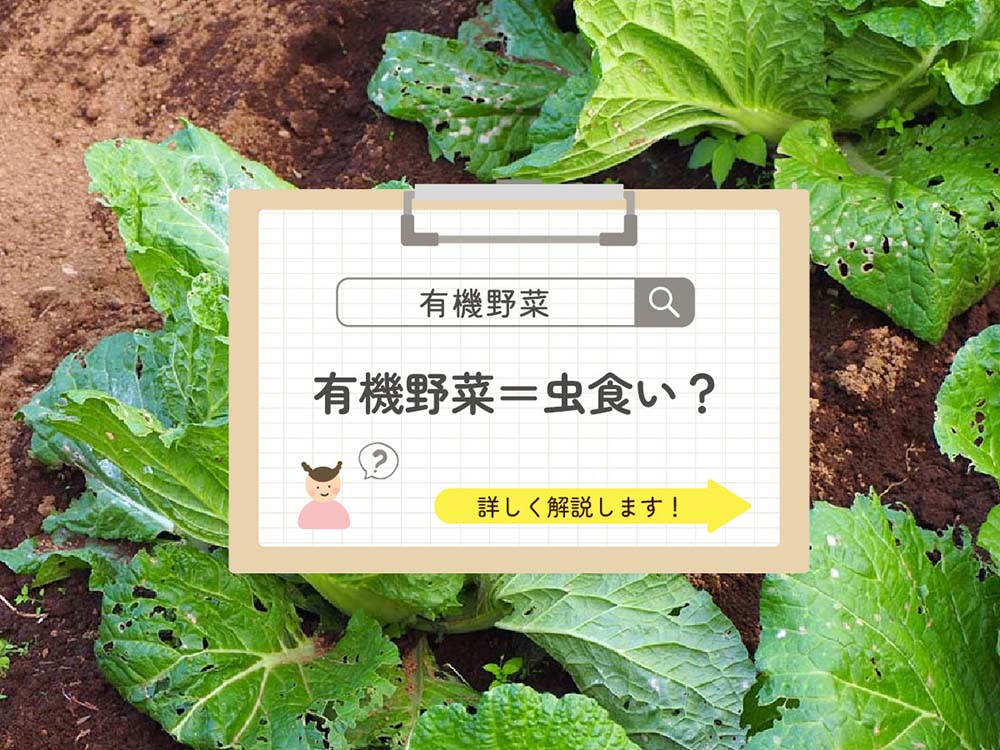

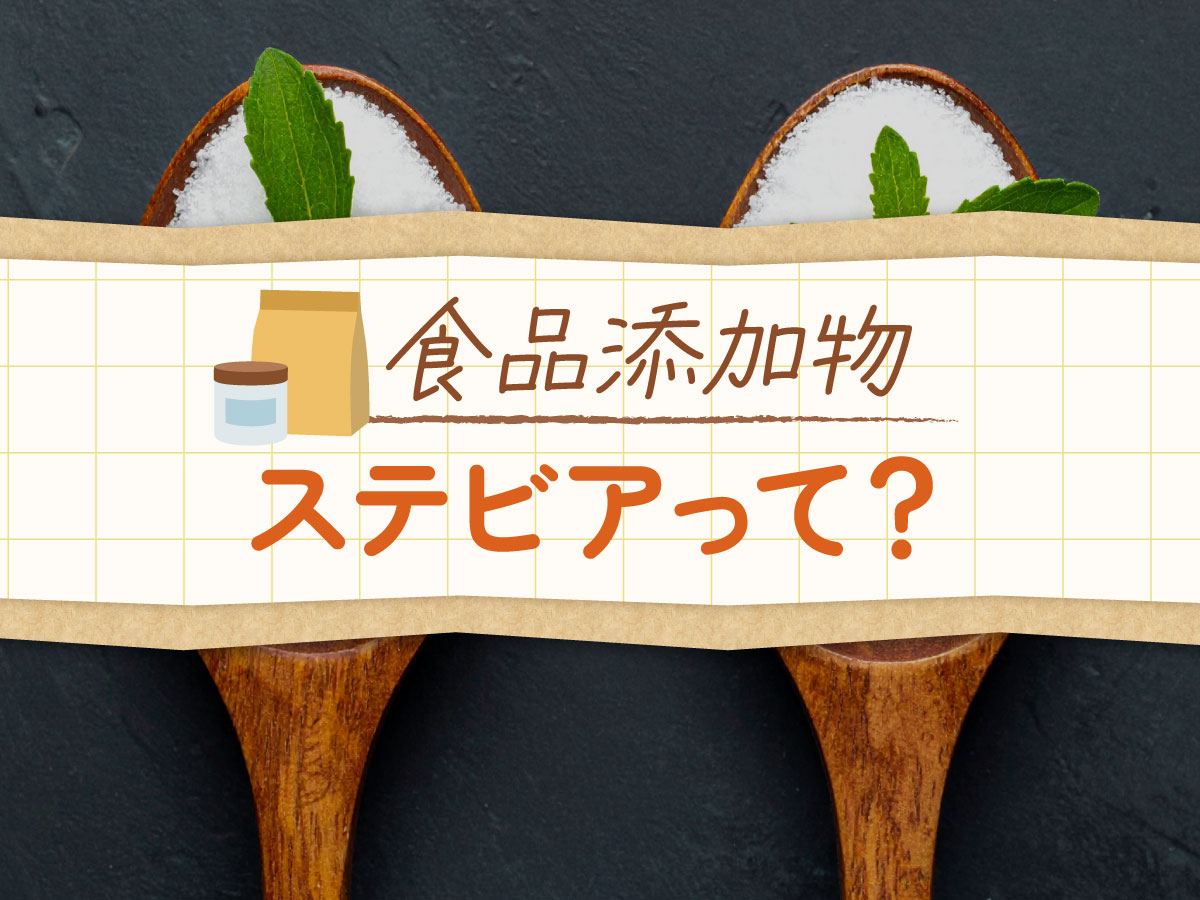



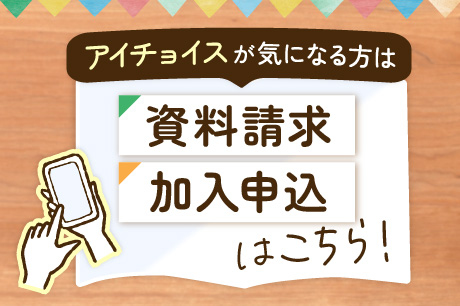




野菜が化学物質の影響をあまりうけていないこと。
一般の野菜と比べて農薬残留量の心配が少なく安心して食べられるので、小さなお子様や妊婦中のかた、化学物質に敏感なかたにもおすすめです。