もやしは生きている!無漂白もやしのパイオニア「サラダコスモ」に行ってみた!
株式会社サラダコスモ(以下:サラダコスモ)は、漂白が当たり前だった時代に無漂白もやしの開発に成功したパイオニア企業です。
今回は、アイチョイスでも取り扱っている、紙袋入りの『緑豆もやし』の製造工程を取材しました!
目次
サラダコスモとは?

サラダコスモの企業理念は「親が子どもに食べさせたい野菜づくり」。
これを合言葉に、安心・安全なもやしづくりに取り組む会社です。
国内最大級の出荷量を誇り、日本全体で消費されるもやしの5~10%はサラダコスモが製造しています。
今回は、全国に6つあるサラダコスモの生産拠点の中で、『緑豆もやし』を製造する岐阜県の養老センターを取材しました。
このセンターは、4年前に完成したばかりの最新&最大級の工場。
工場内も他の生産施設に先駆けた新しい試みが行われています。
無漂白もやしとは?

1973年頃は、見た目を白く保つため、もやし業界では漂白剤を使うのが当たり前でした。
しかし、現在の代表取締役・中田智洋さんは「世のため人のため」という信念のもと、無漂白もやしの開発に乗り出したのです。
当初は茶色い見た目から売れ行きが伸び悩みましたが、生協で高く評価されたことをきっかけに広まり、開発から10年後には業界全体が無漂白へとシフトしました。
もやしの製造現場に行ってみた!
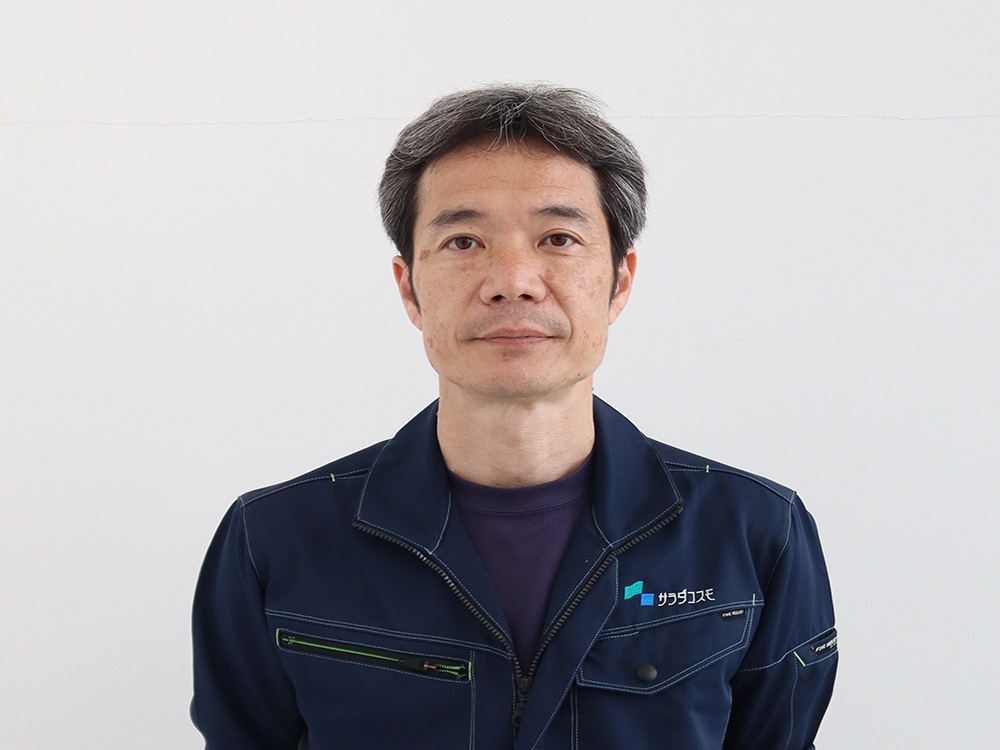
原さん
養老センターのセンター長。
もやしの育て方や養老センター内のことならなんでも知っています。
今回、養老センターについて紹介していただきました!
契約農家が育てた有機種子を使用

アイチョイスで取り扱っている、紙袋に入った『緑豆もやし』には、中国の契約農家が有機栽培で育てた種子のみを使用しています。
生きものである種子は、産地や収穫年度によって性質が異なるため、丁寧な見極めと管理が欠かせません。
保管庫は5〜8℃で管理され、ロット番号で産地や収穫年度がいつでも確認できるようにしています。
栽培直前に行う種子の殺菌には、薬剤を使わず、温湯殺菌を行っています。
このとき、温度が高すぎると「煮豆」状態になり発芽率が低下し、低すぎると土壌由来の菌が残ってうまく栽培できなくなってしまうのだそう。
種子ごとに、50〜90度の範囲で温度と殺菌時間を調整し、最後は井戸水で冷却します。
養老山脈の地下水で栽培

殺菌を終えた種子は100キロずつに分けて栽培容器のコンテナに移され、栽培室へ移動します。
栽培用コンテナはとっても大きく、大人が10人は入れそうなほど。
こんなに大きなコンテナだと、下の方のもやしが潰れてしまうのでは、と心配になりますよね。
案内してくれた原さんによると、もやし同士が互いに支え合う構造になっているので、下のもやしも潰れないのだそう。
もやしは光が当たらない真っ暗な栽培室の中で、養老山脈のきれいな地下水のみをたっぷり与えられて育ちます。
もやし栽培にとってもっとも大事なのが、水の質と量。
水が少ないと、発芽初期にもやし自身が発する「発芽熱」によって豆全体が腐ってしまうのです。
全自動の収穫と品質管理

1週間ほどで、もやしが8cm前後に成長したらいよいよ収穫です。
このとき、コンテナひとつ分のもやしの重さは約1トン、パックに換算すると約5000パック分にもなるんですよ。
収穫方法はとても大胆!
まず、コンテナを専用の車両でけん引して、栽培室から収穫・洗浄ラインがある別室へ移動させます。
定位置につくと、機械でコンテナを持ち上げてそのままひっくり返すのです。
巨大なコンテナを丸ごと揺らし、みっちり詰まったもやしがどさーっと洗浄ラインに落とされていく景色は圧巻でした!
エコフィードシステムで、循環型社会に貢献

収穫直後のもやしは長い根っこや種の殻などがついており、そのままでは袋詰めできない状態です。
洗浄ラインでは表面張力を利用して豆殻を取り除き、根っこの部分をカット。
これらの不要な部分は「残渣(ざんさ)」と呼ばれ、以前はゴミとして廃棄・焼却処分されていたそうです。
しかし、この残渣を何かに有効活用できないか?という試みから取り入れられたのが、「エコフィードシステム」。
もやしの残渣を特別な脱水機械にかけることで、牛の飼料にすることに成功しました。
残渣といえど、根や豆殻には豆の栄養がぎゅっと詰まっています。
飼料の値上がりも懸念されている昨今、国産飼料を安定して得ることができると酪農家の方々にも喜ばれているそう。
さらに残渣処理にかかるコストカットも実現し、循環型社会を実現しています。
正確な計測と徹底した衛生管理

洗浄されたもやしは、ベルトコンベアでそのまま「組み合わせ自動秤」に運ばれます。
この秤は、全自動で200gに計測することができる優れもの。
計測されたもやしは、「組み合わせ自動秤」真下の1階フロアに設置された包装機の中に落とされます。
袋詰めと製造年月日の印字を同時に行い、最後に秤付きの金属検出器を通します。
わずかな異物も計測ミスも、一切見逃さない仕組みになっているんですね。
工場内には、ほとんど人がいません。
原さんによると、機械化によって人が直接行う作業を徹底的に減らしたことで、髪の毛や屋外の汚れなど、異物混入のリスクを減らすことができたとのこと。
食べ物の衛生管理は、企業のたゆまぬ努力と工夫の上に成り立っているのです。
もやしは生きている?紙パッケージの秘密

サラダコスモでは、緑豆もやしに適した通気性を持つ特殊な紙パッケージを採用。
そのため、袋の中でももやしが呼吸しやすく、シャキシャキ感とおいしさを保つことができます。
紙パッケージは製造中に破れやすく、コストも高いという課題があります。
さらに、1分間に35〜40袋という包装速度は、従来のフィルム包装の約半分にとどまり、生産効率の面では大きなハンディキャップ。
それでもなお紙パッケージの採用を続けるのは、お客さんに喜んでもらえる製品をつくり、また、環境への負荷を軽減するという信念に基づいているからです。
この選択には、「世のため人のため」という企業としての姿勢が、確かに表れています。
もやしの種を自社で育てよう!

サラダコスモは、もやしの有機種子を自社で生産するためのプロジェクトを始めました。
しかし、高温多湿の日本の気候は、種子の栽培には不向き。
そのため、肥沃な土壌と乾燥した気候という、種子栽培に理想的な環境を備えた南米アルゼンチンが選ばれました。
現地の農場では、戦後に移民された日本人の2~3世の方が、故郷である日本への思いを胸に、現地スタッフとして働いています。
種子生産はまだ試行錯誤の段階であり、課題も少なくありません。
それでも近年では、品質の高い種子が少しずつ育ち始めているとのこと。
食の未来を支える一歩として、サラダコスモの挑戦が進んでいます。


社員さんに聞いてみた!

野村さん
主に営業部門を担当。
サラダコスモの歴史から最新の取り組みまで、社内を幅広く熟知。
サラダコスモが経営する「ちこり村」のちこり茶は、「ハマる人はとことんハマる」人気商品なので、ぜひ試してみてください!
もやしづくりのこだわり
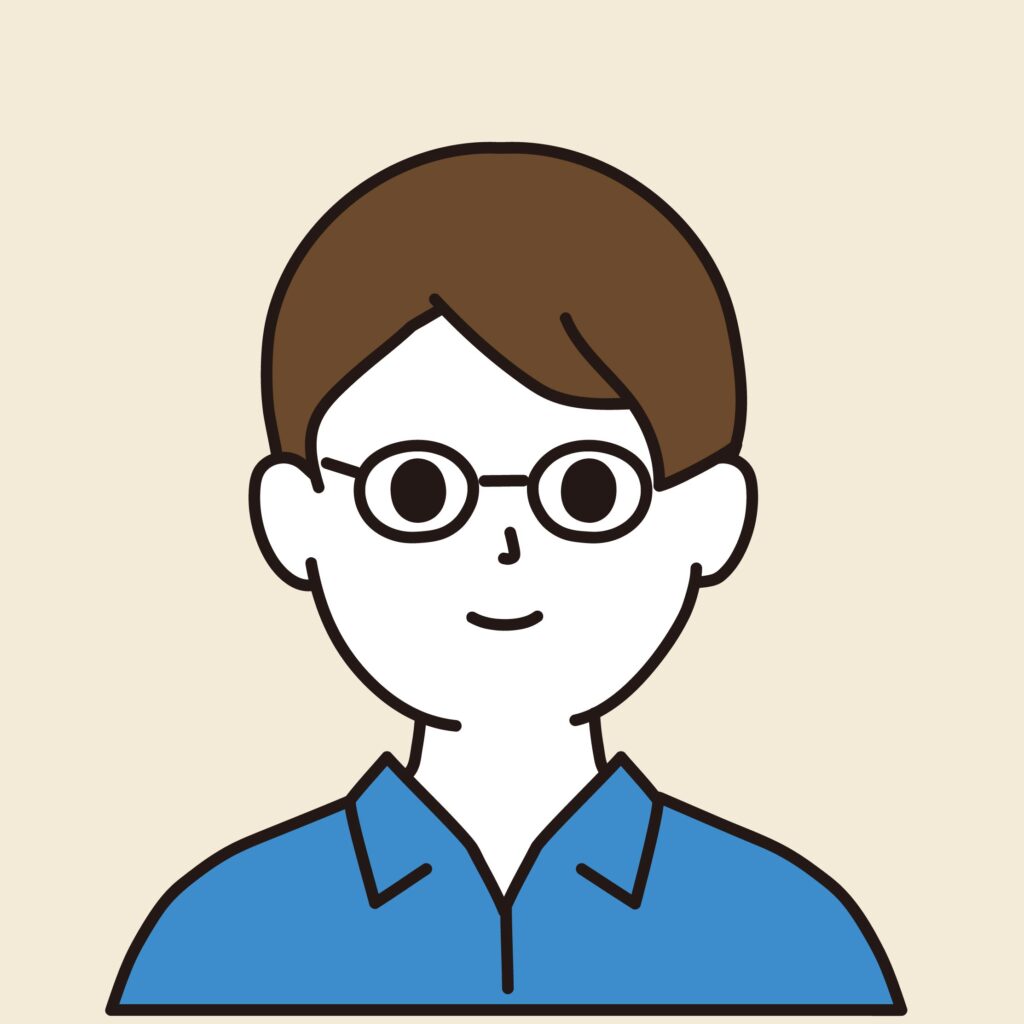
ちえまる
薬剤を使わない栽培方法と、日持ちを良くする紙製のパッケージですね。
創業者の「世のため人のため」という信念をこれからも守り続けたいと考えています。

野村さん
サラダコスモでは徹底した衛生管理を行っています。
人が作業をするとどうしても毛髪などが混入する恐れがありますが、サラダコスモではほとんどの作業を機械で自動化。
異物混入のリスクを最小限にしています。
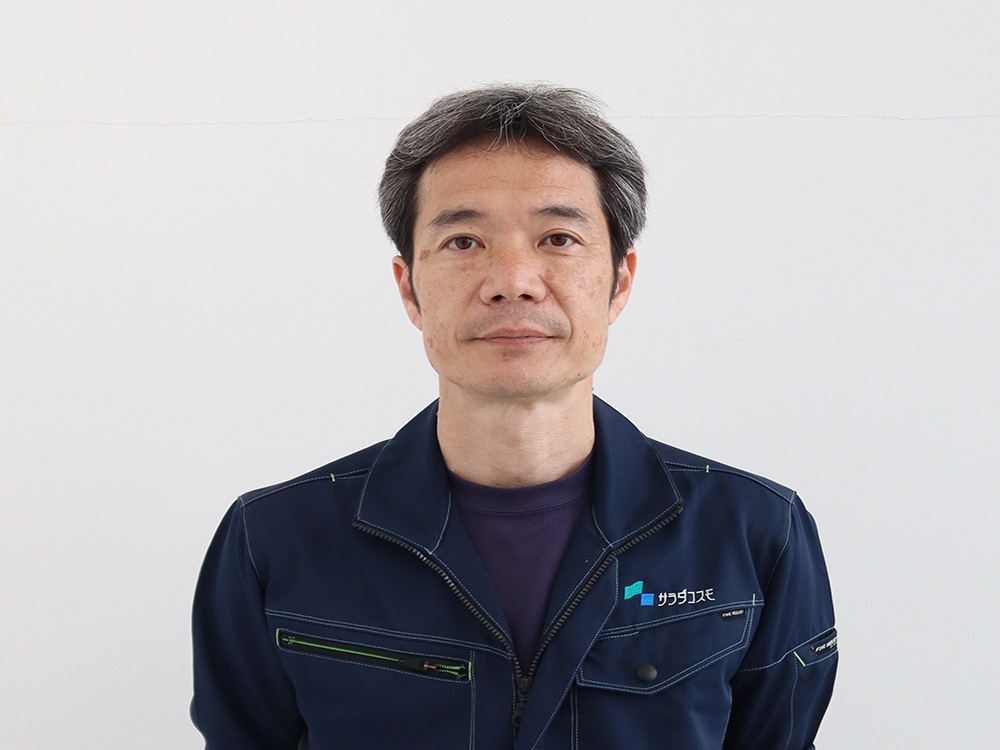
原さん
おすすめの食べ方
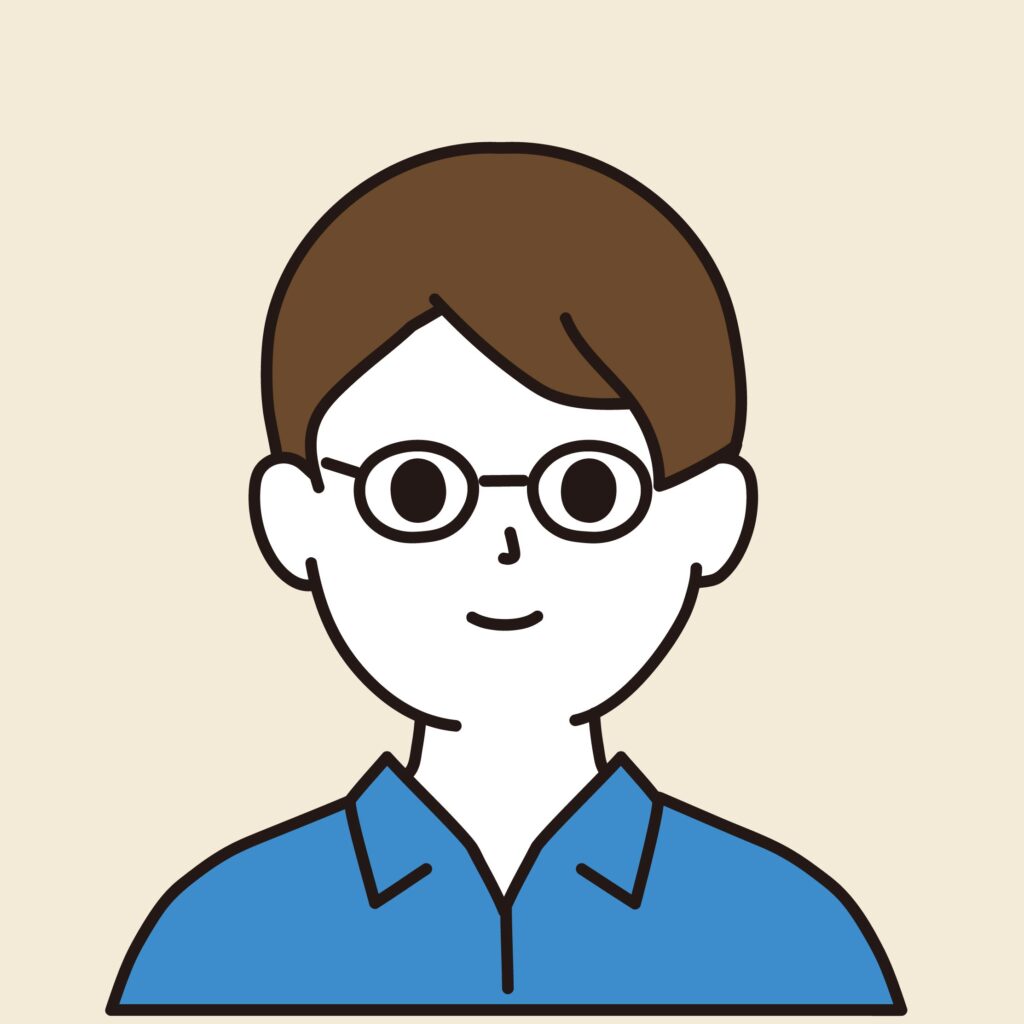
ちえまる
もやしのおすすめの食べ方はありますか?
30秒ぐらいさっと茹でて、白だしとごま油、鷹の爪であえて食べてみてください!
白だしがもやしによく馴染んで、かんたんなのにおいしいんですよ。

野村さん
組合員さんへのメッセージ
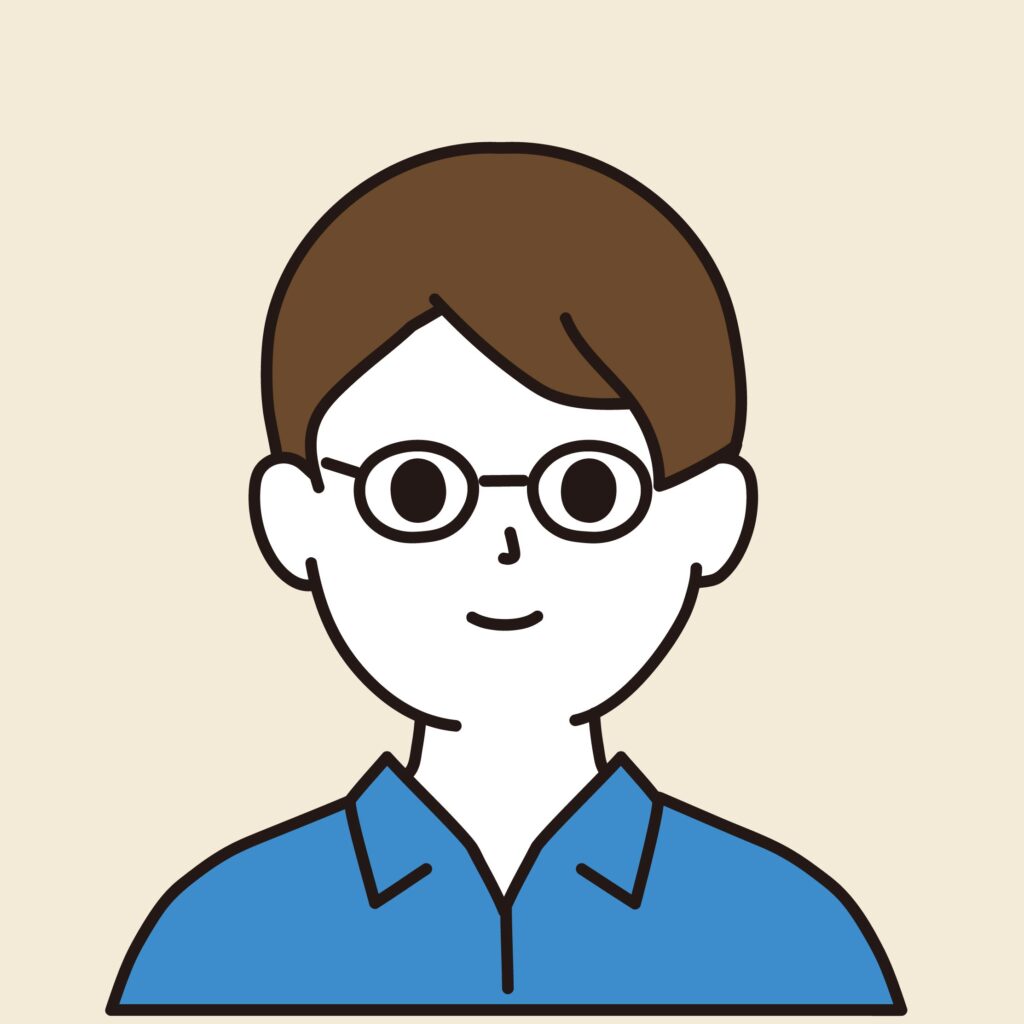
ちえまる
組合員さんへメッセージをお願いします。
これまでと変わらず、安全で新鮮なもやしづくりに取り組みます。
さらに、手軽に使えて、皆さんの健康に貢献できる食材をつくり続けていきます。
今後もご愛顧のほど、よろしくお願いいたします!

野村さん
身近な良品質野菜「無漂白もやし」を後世に

実は私も毎日のようにもやしを食べています。
安価で手軽に調理できる食材という印象が強いですが、その裏には並々ならぬ安心へのこだわりと情熱が詰まっていることを知り、改めて感動しました。
サラダコスモでは、毎晩0時から生産を開始し、午後2〜3時頃まで稼働。
その後は洗浄ラインの清掃を行い、また翌日の準備が行われます。
これが365日休むことなく続いているという事実には、ただただ頭が下がる思いです。
手頃な価格で、さまざまな料理に活用できるもやし。
毎日の食卓に欠かせない存在となっているのは、こうした企業努力があってこそであることを、忘れずにいたいですね。
編集担当はらりん
2019年アイチョイス入協。40代、中学生と小学生の二人の母。
ネット限定商品を見て、お得でおいしいものをゲットするのがひそかな楽しみ。
イチ推しの商品は、クチコミ投稿せずにはいられません。
コーヒーとチョコ大好きの私はヘーゼルナッツ派。







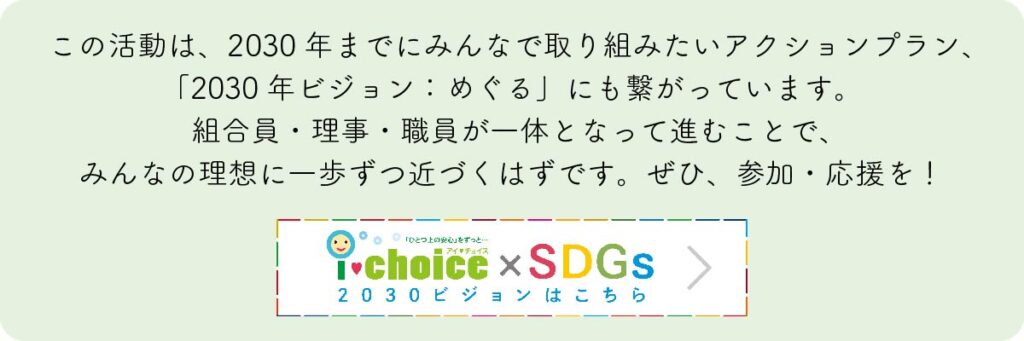
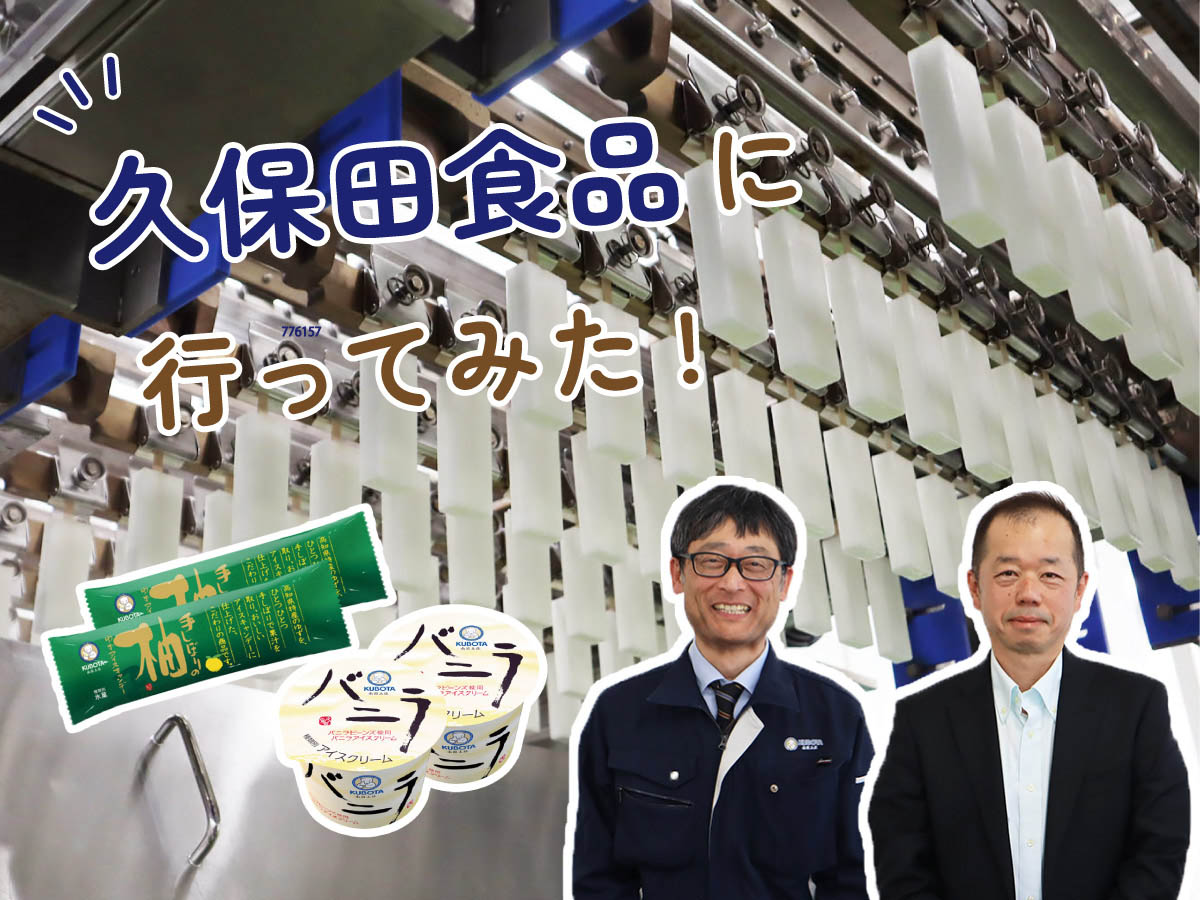








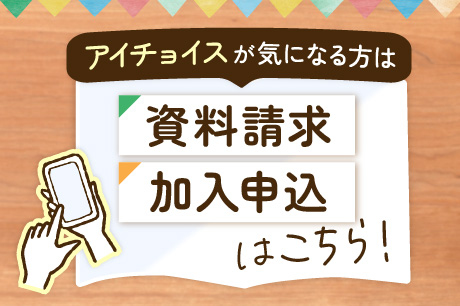




もやしを生産する上でのこだわりは何ですか?