食品添加物の増粘多糖類とは?注意点や安全性、デメリット、体に悪いのかを解説
増粘多糖類は、食品に粘度を与えたり形を崩れにくくしたりするために使われる食品添加物です。
アイスクリームやゼリー、ドレッシングなど、さまざまな商品で見かける成分表に「増粘多糖類」として記載されているのを目にする方も多いでしょう。
本記事では、増粘多糖類の定義や表示上のルールをはじめ、その注意点と安全性、メリットやデメリットまで詳しく解説します。
目次
食品添加物の増粘多糖類とは

増粘多糖類は、水に溶けると食品の粘度を高めたり、ゲル化したりする性質を持った水溶性の高分子物質の総称です。
まずは増粘多糖類がどのようなものなのか、その定義や特徴を確認しましょう。
参考:増粘多糖類|あいち産業化学技術センター,(参照2025-10-24)
増粘多糖類の特徴と主成分

増粘多糖類は、食感の調整や食品の物性を維持するために用いられることが主な特徴です。
粘度を与えたり、凝集やゲル化を支援する性質のみならず、食品の外観や安定性にも大きく貢献します。
主な成分は以下の通りです。
- 海藻由来の多糖類(カラギーナンなど)
- 植物種子由来(グァーガムなど)
- 微生物発酵由来(キサンタンガムなど)
- セルロース系の化学加工物(カルボキシメチルセルロースナトリウムなど)
これらは単独で使われることもありますが、目的や製品との相性によっては、複数を組み合わせて使われる場合もあります。
それぞれが異なる粘度や耐熱特性を持ち、組み合わせることで幅広い食品の品質や食感に対応できる柔軟性を備えているのが増粘多糖類の大きな利点です。
参考:用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-10-24)
増粘多糖類と増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料の違い

増粘多糖類は、食品表示法により、増粘剤や安定剤などの用途名とともに具体的な物質名を記載するのが基本です。
増粘安定剤は、使用方法によって増粘剤、ゲル化剤、安定剤と呼び分けられます。
増粘剤や安定剤、ゲル化剤、糊料のそれぞれの違いを以下の表でまとめました。
| 項目 | 増粘剤(糊料) | 安定剤(糊料) | ゲル化剤(糊料) | 増粘多糖類 |
| 定義・特徴 | 食品に粘りやとろみをつける。 | 食品成分を均一に安定させ、形状を保つ。 | 液体をゼリー状に固める。 | 「増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料」などの機能を持つ多糖類の総称。 |
増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料は、食品をより食べやすくしたり、品質を保ったりする目的で使用される食品添加物の用途名です。
たとえばゼリーではゲル化剤という名称が用いられ、水分と結びついて固形状になるのを助けます。
安定剤の役割は、離水を防ぎ食品の形状を安定させることです。
それぞれの表示方法については、後述します。
参考:用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-10-24)
参考:・食品衛生法に基づく添加物の表示等について(◆平成08年05月23日衛化第56号)(参照2025-10-24)
多糖類とは

多糖類は、多数の糖が鎖のように連結した物質を指します。
代表的な多糖類にはデンプン、セルロース、グリコーゲンなどがあり、甘みがほとんどないか非常に弱いのが特徴です。
食品用途では、粘性や弾力性を付与したり、液体を安定化させたりする役割が重宝されます。
そのためゼリーやプリン、ソース類など幅広い製品に応用されるようになりました。
参考:用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-10-24)
食品添加物の増粘多糖類の食品表示のルール
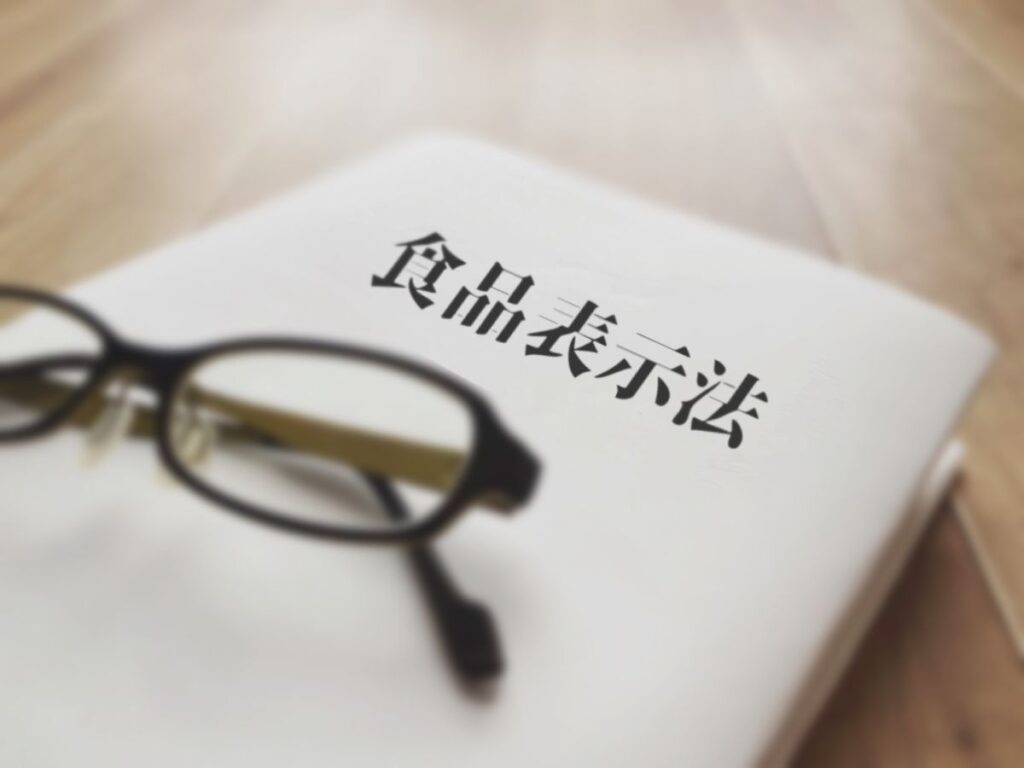
増粘多糖類は食品表示法で、増粘剤や安定剤といった用途名とともに、具体的な物質名を記載されるのが基本です。
以下では、増粘多糖類の役割や表示例を詳しく解説します。
参考:・食品衛生法に基づく添加物の表示等について(◆平成08年05月23日衛化第56号)(参照2025-10-24)
増粘多糖類の役割や用途

増粘多糖類は、食品を目的の粘度に調整し、見た目や食感を向上させるのに使われます。
たとえば、ドレッシングがとろみを保てるのは、この成分が水分と油分を適度にまとめているためです。
また安定剤として働き、時間が経っても水分が分離しにくくする機能も担います。
アイスクリームやゼリー、ドレッシングなどの加工食品で使用されるのは、数種類の多糖類を組み合わせて製品の質を安定化しているためです。
増粘多糖類の表示例
| 項目 | 増粘剤(糊料) | 安定剤(糊料) | ゲル化剤(糊料) | 増粘多糖類 |
| 定義・特徴 | 食品に粘りやとろみをつける。 | 食品成分を均一に安定させ、形状を保つ。 | 液体をゼリー状に固める。 | 「増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料」などの機能を持つ多糖類の総称。 |
| 表示ルール | 「増粘剤(物質名)」または「糊料(物質名)」と記載。 | 「安定剤(物質名)」または「糊料(物質名)」と記載。 | 「ゲル化剤(物質名)」または「糊料(物質名)」と記載。 | 2種類以上の多糖類を使用し「増粘安定剤」の目的で使う場合は「増粘多糖類」のみの表記が可能。 「ゲル化剤」、「糊料」の目的で使う場合は「安定剤(増粘多糖類)」のように用途名を付記。 |
増粘剤、安定剤、ゲル化剤、増粘多糖類の表示方法をまとめました。
増粘安定剤として使用し、2種類以上の多糖類を使用する場合は、「増粘多糖類」という一括表示が認められています。
簡略表示の意味合いを理解しておくと、ラベル表記が変わってもどのような成分が使われているのかを判断しやすくなりますよ。
その他食品添加物の表示方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:・食品衛生法に基づく添加物の表示等について(◆平成08年05月23日衛化第56号)(参照2025-10-24)
食品によく使われている増粘多糖類

増粘多糖類には、海藻由来や植物の種子から抽出された自然素材が多く含まれています。
一方で、化学的に加工されたセルロース系のものも存在。
それぞれの特性に応じて、食品の用途に合わせて使い分けられています。
ここでは、以下の代表的な種類を挙げ、それぞれの特徴と利用例を見ていきましょう。
- ペクチン
- カラギーナン
- カルボキシメチルセルロースナトリウム
- グァーガム
- キサンタンガム
ペクチン

ペクチンは果物、とくに柑橘類やリンゴなどに多く含まれる植物由来の多糖類です。
ジャムやゼリーで固形の形状を保つ性質を活かしてゲル化剤としてよく使用されます。
酸や糖度に応じてゲル化の仕組みが変わり、適度な弾力のあるゼリーがつくりやすいのが特徴です。
家庭でジャムをつくる際に、果物を煮詰めるだけでとろみが出るのはペクチンの作用が働いています。
参考:用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-10-24)
カラギーナン

カラギーナンは海藻の一種である紅藻類(赤い海藻)から抽出される多糖類です。
ゼリーや乳飲料、プリンなどに幅広く使われています。
特徴はゼリー状へのゲル化能力が強く、なめらかな舌触りを実現しやすいこと。
また、離水を抑制して品質を保ちやすくする働きも注目されています。
参考:用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-10-24)
カルボキシメチルセルロースナトリウム

カルボキシメチルセルロースナトリウムは、天然のセルロースを化学的に加工して得られる増粘剤です。
水によく溶ける性質があり、粘度をコントロールしやすいため多くの飲料やデザート、ソース類に用いられます。
とくに製造時の扱いやすさが評価され、液体の粘度調整に幅広く採用されている食品添加物です。
化学的に加工されているとはいえ、世界的にも使用が認められており、摂取基準を守ることで安全性が確保されています。
参考:用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-10-24)
グァーガム

グァーガムはマメ科のグァー豆の胚乳部分から抽出された多糖類で、その高い粘度と水分保持能力からドレッシング、アイスクリーム、即席めん類などさまざまなカテゴリで使われています。
特徴は、低濃度でも非常に強い粘度を発揮し、少ない添加量でもしっかりとしたとろみやコシを与えられる点です。
参考:用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-10-24)
キサンタンガム

キサンタンガムは微生物であるキサントモナス属の発酵によって得られる多糖類です。
ローカストビーンガム、グァーガムと併用することで、相乗的な増粘効果が期待できます。
使用される食品は、ソースやつくだ煮、レトルト食品などです。
参考:用途別 主な食品添加物 増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-10-24)
食品添加物の増粘多糖類の注意点と安全性
増粘多糖類に対しては、具体的にどの成分が使われているのか分かりにくい、体に悪いのではないかという不安の声もあります。
その注意点と安全性について見ていきます。
増粘多糖類の注意点とは

増粘多糖類による注意点は、アレルギー反応についてです。
件数はまれですが、実際に増粘剤カラギーナンによるアナフィラキシーの事例が報告されています。
とはいえ、食品衛生法などの規制をクリアし、安全上の問題はないと判断された上で使用されている物質です。
一般的には、増粘多糖類だけを大量に単独で摂取する状況は想定しにくいですが、注意をしましょう。
参照:ゼリー中に含まれていた増粘剤カラギーナンによるアナフィラキシーの1例|皮膚科の臨床61巻13号(2019年12月発行),(参照2025-10-24)
増粘多糖類の安全性とは

多くの増粘多糖類は、日本を含む各国の食品機関によって使用基準が定められており、適正量を守れば問題ありません。
食品の製造現場でも、製品が適切かつおいしく仕上がるように配合量が管理されています。
製品テストを経てから出荷されるため、安全性は高いといえるでしょう。
ただし、どの添加物にも言えることですが、過剰摂取は避けるべきです。
適量を守り、おいしく食べる範囲であれば、過度に心配する必要はありません。
以下の記事では食品添加物のデメリットについても解説しています。
ぜひ参考にしてください。
植物由来の増粘多糖類は安心?

多くの増粘多糖類が植物素材から抽出されており、その点で「化学的につくられた食品添加物より適切」と感じる方は多いかもしれません。
一方で、植物由来だからといって必ず安心というわけでもありません。
得意不得意や体質の差によってはアレルギー反応が起こる場合もあり、混ぜ合わせるほかの食品成分との相性にも注意が必要です。
食品添加物の増粘多糖類のメリットとデメリット

増粘多糖類は食感や品質を高めるなど多くのメリットがあります。
一方で、デメリットも存在するため、ここではその両面を詳しく見ていきましょう。
増粘多糖類のメリット

主な増粘添加物のメリットは以下の通りです。
- 食品の分離を防いで安定性を高める
- 多彩な食感を実現できる
- 幅広い食感を生み出すことができる
増粘多糖類には、食品の分離を防いで安定性を高める効果があります。
飲料やソース類でも成分が偏らず均一に保たれるため、見た目や味が向上。
さらには、多彩な食感を実現できる点も魅力です。たとえばソースのとろみを増したり、ゼリーのぷるんとした口当たりをつくるなど、メーカーが狙う食感に合わせて使い分けられています。
また、弾力のあるゼリーから粘度のあるスープまで、幅広いテクスチャを生み出せる柔軟性を持っており、アイスクリームなどでも離水を防ぐことでクリーミーさを維持しやすくなるのです。
結果的に食品の保存性や品質の安定にも貢献するため、メーカーや消費者の双方にとってメリットがあるといえるでしょう。
増粘多糖類のデメリット

増粘安定剤として使用し、2種類以上の多糖類を使用する場合は、「増粘多糖類」という一括表示が認められています。
そのため、実際にどの種類の多糖類がどの程度配合されているのかを簡単に把握できないケースも。
さらに、報告数は少ないですが一部アレルギー症状の発症も注意しなければいけません。
その他の食品添加物によるアレルギーについては、以下の記事で解説しています。
参考:・食品衛生法に基づく添加物の表示等について(◆平成08年05月23日衛化第56号)(参照2025-10-24)
参照:ゼリー中に含まれていた増粘剤カラギーナンによるアナフィラキシーの1例|皮膚科の臨床61巻13号(2019年12月発行),(参照2025-10-24)
食品添加物の増粘多糖類に関するよくある質問

最後に、増粘多糖類に関する疑問を一問一答形式でまとめます。
増粘多糖類にはがんのリスクがありますか?

増粘多糖類は食品添加物ですか?
増粘多糖類とは、複数の多糖類を組み合わせて粘度や安定性を保つ目的で使われる食品添加物の一種です。
食品表示法では、用途名とともに物質名を記載することが定められています。
増粘安定剤として使用し、2種類以上の多糖類を使用する場合は、「増粘多糖類」という一括表示が認められています。

増粘性多糖類のデメリットは?
増粘性多糖類の主なデメリットは、具体的な成分が分かりにくく消費者が不安を感じやすいこと、過剰摂取時に胃腸に負担がかかる場合があること、まれにアレルギーを引き起こす可能性があることなどが挙げられます。

参照:ゼリー中に含まれていた増粘剤カラギーナンによるアナフィラキシーの1例|皮膚科の臨床61巻13号(2019年12月発行),(参照2025-10-24)
増粘剤は体に悪いですか?
一般的な食事の範囲で使用されている増粘剤の量であれば、体に悪影響を及ぼすことは少ないとされています。
厚生労働省や国際基準でも、ADI(1日摂取許容量)が設定されているものはその範囲内では問題がなく安全性が認められています。
一方で、体質やアレルギーの問題で悪影響が出るリスクがあるとも言われているのです。
不安がある方は、摂取量を調整したり、表示を確認して特定の成分を避けるなどの対応をするとよいでしょう。

参照:ゼリー中に含まれていた増粘剤カラギーナンによるアナフィラキシーの1例|皮膚科の臨床61巻13号(2019年12月発行),(参照2025-10-24)
食品添加物の増粘多糖類をしっかり理解して賢い食生活を!

増粘多糖類は、食品業界にとって欠かせない存在であり、私たちの食卓に並ぶ商品を支える重要な要素です。
ただし、アレルギーのある方は、表示を確認して選ぶことをおすすめします。
日頃から食品表示を確認し、自分や家族に合った商品を選ぶことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
賢い食生活の第一歩は、正しい知識を身につけることです。
増粘多糖類についてもしっかり学び、安心して食品を楽しめるよう心がけましょう。
アイチョイスでは、食品添加物に頼らない商品をはじめ、原材料にこだわった食品を取り扱っています。
まずはおためしボックスを試してみませんか。









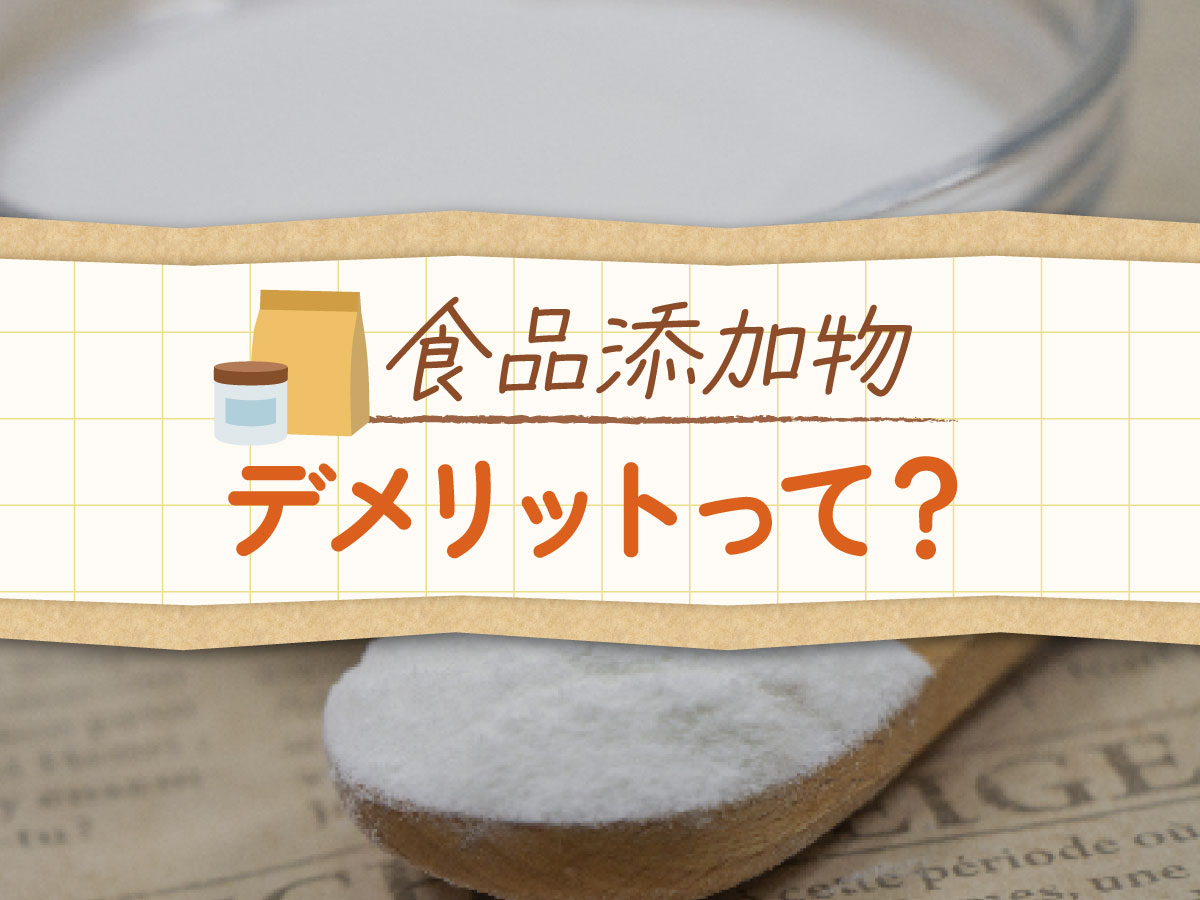
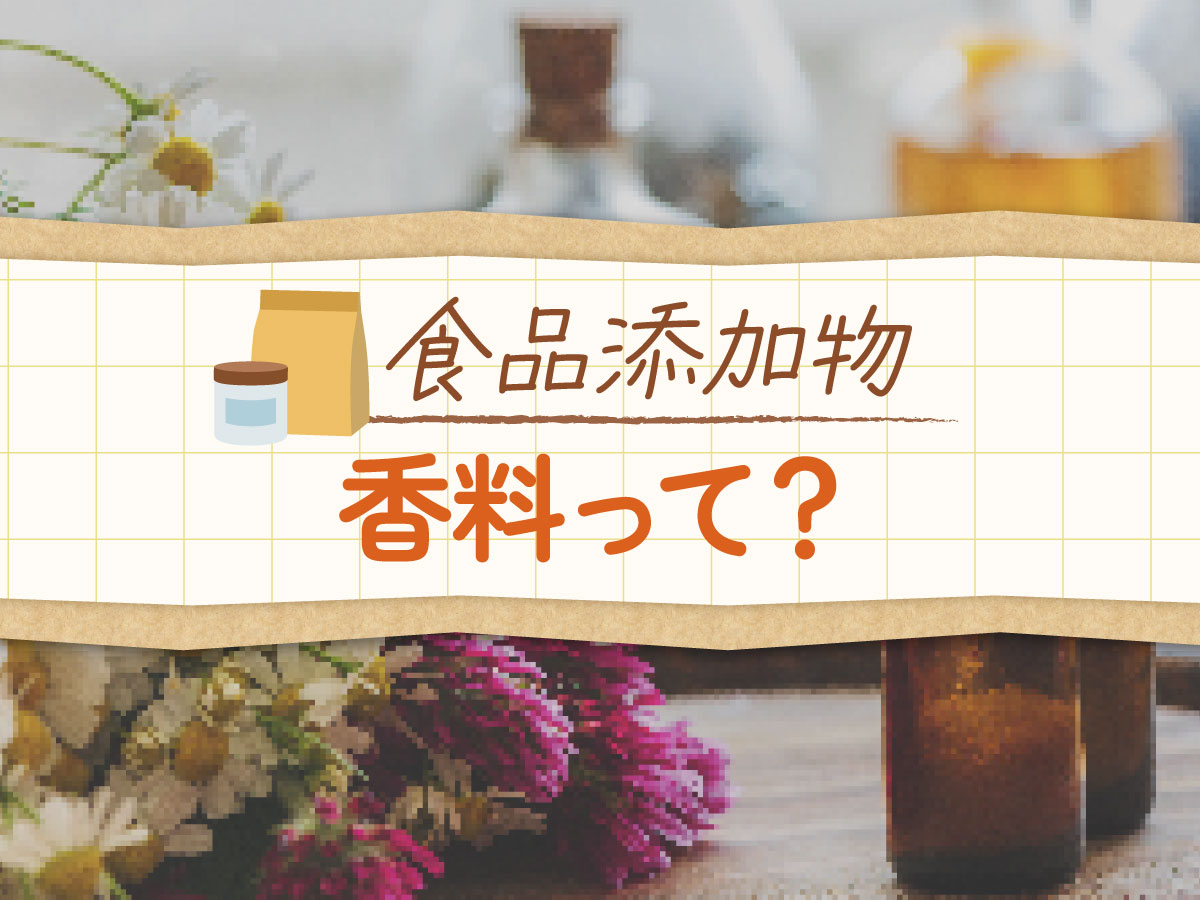
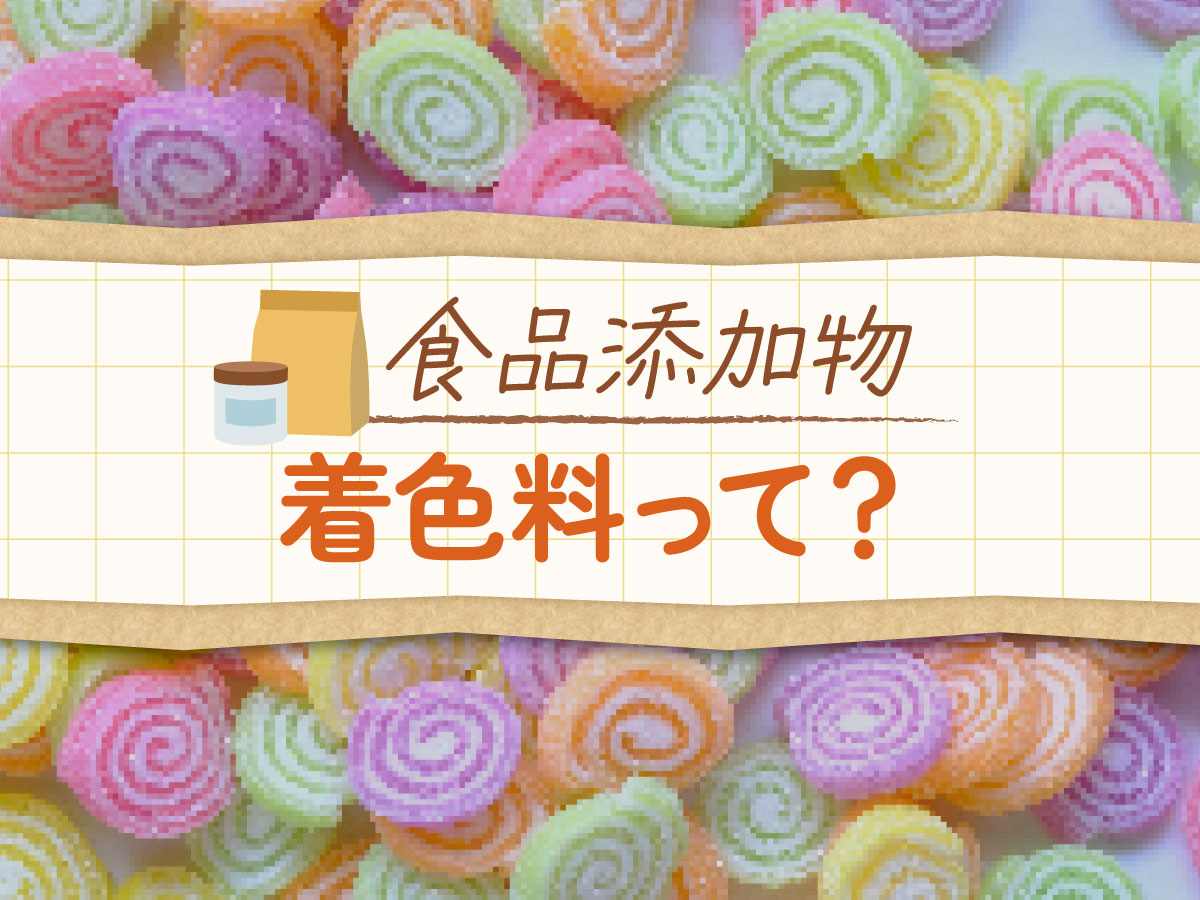
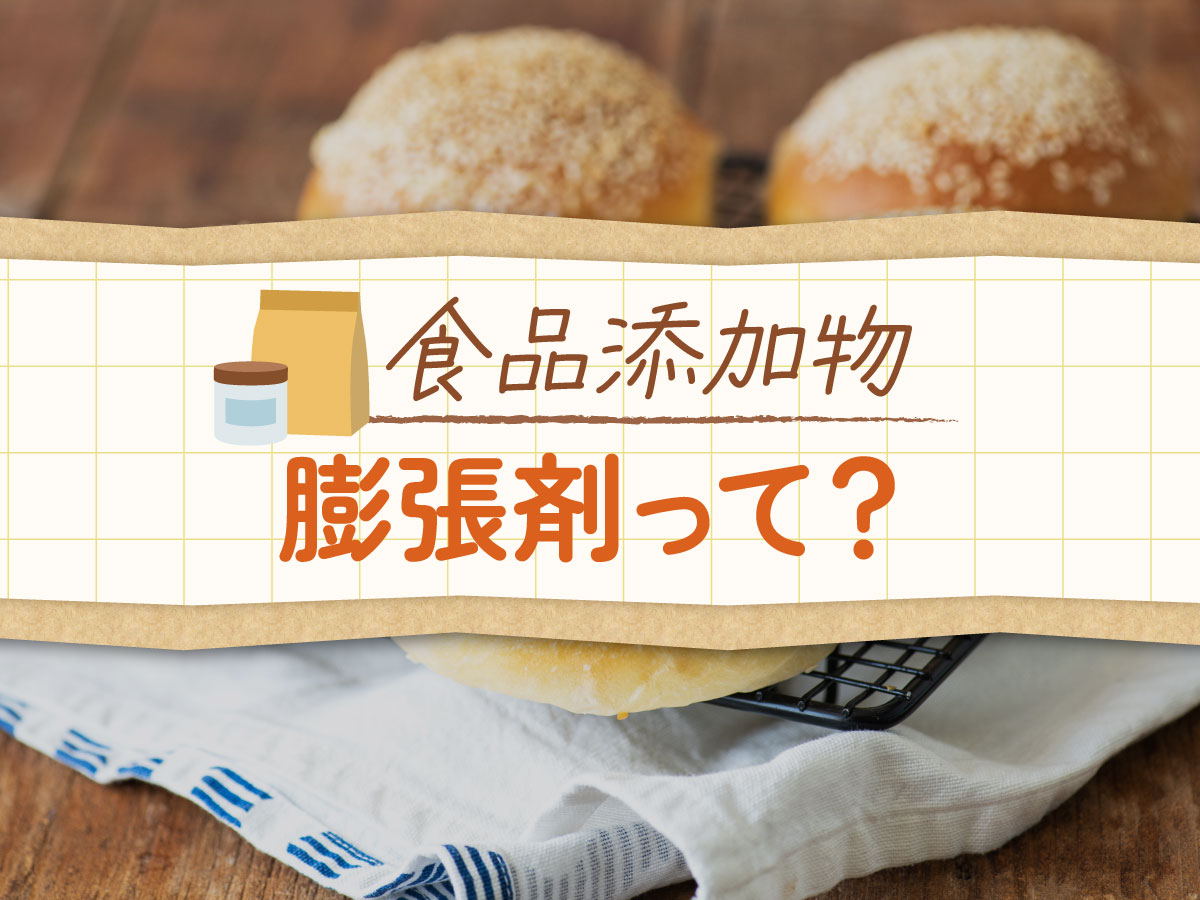
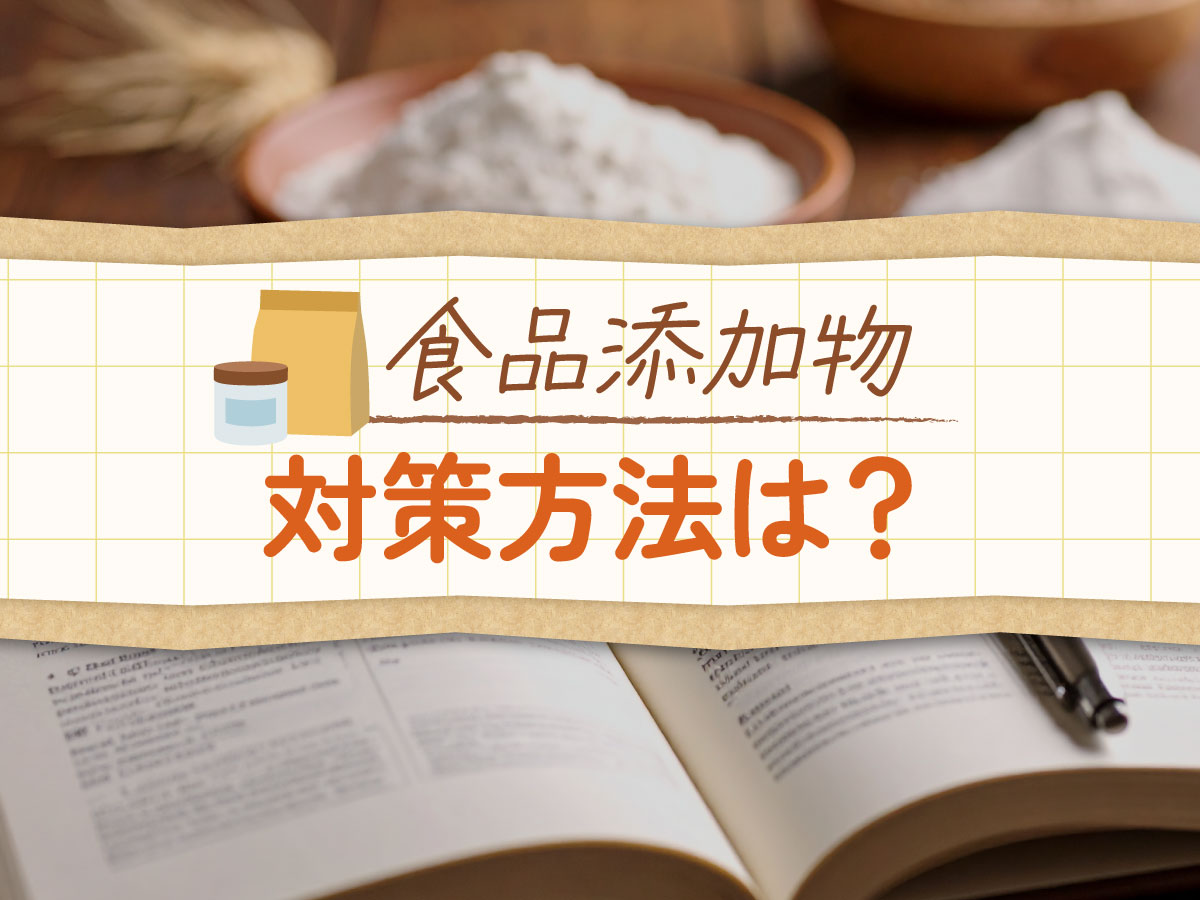



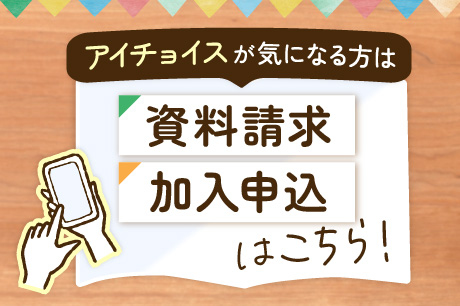




明確な健康被害の実例は確認されていません。
食品管理がなされているため通常の使用量程度では健康への影響に問題となることはほとんどないと言われています。