栗の名産地・小布施で農薬に頼らない栽培を行う、岡田農園に行ってみた!
長野県小布施町は「小布施の栗」として有名な、栗の産地です。
栗は害虫対策のため、収穫後に燻蒸処理を必須とする販売所があるほど、虫の被害に遭いやすいとされています。
そんな中、農薬に頼らない栽培を行う岡田さんは、燻蒸処理を行っていない貴重な栗をアイチョイスへ出荷。
栽培している品種ごとの特徴や、おいしさの秘密についてもインタビューしました!
目次
小布施の栗って?
江戸時代から続く栗の産地

長野県は栗の栽培面積が全国7位。
令和4年産の品種別でみると、長野県内で栽培面積が多い順に1位が銀寄、2位が筑波となっています。
長野県の中でも「小布施」は全国的に知られる栗の名産地です。
江戸時代には幕府への献上品とされていたほど。
小布施の街を歩くと、いたるところで栗スイーツのお店を発見。
ようかんやどら焼きなどの和菓子以外にも、モンブランやフィナンシェなどの洋菓子もありました。
町全体で「小布施の栗」を盛り上げている様子がうかがえましたよ。
参考:果樹品種別生産動向調査(栗)|e-Stat,(参照2025-08-22)
大きさと甘さが魅力の「銀寄」

粒が大きく、ホクホクとした味わいが特徴の「銀寄」。
江戸時代の大飢饉の際に、この栗が高値で飛ぶように売れたことから、「銀札(当時の紙幣)を寄せる」という意味で、「銀寄」と名付けられたそうです。
銀寄は青色のイガが特徴の中生種で、9月下旬~10月中旬に収穫します。
イガひとつにつき、大きめの栗が1~2つ入っていることが多く、数は少ないものの、立派な栗が目を引く品種です。
1本の樹から収穫できる量は「筑波」よりも少ないのですが、岡田さんは「銀寄」の味にほれ込んだ、エムエスケイ代表の畑さんの想いに共感し、「銀寄」の栽培を続けています。
小布施で栽培された「銀寄」のほとんどがスイーツ等の加工用に出荷されるため、あまり青果物として目にする機会はありません。
しかし、アイチョイスでは生栗の「銀寄」を展開しています。
栗の定番といえば「筑波」

全国的に広く普及しているのが、「筑波」です。
収穫量が多い点や、病気や天候に左右されにくい点が特徴で、イガ1つあたり3つの栗が入っていることが多いそう。
先端が少し尖っていて、その周りが少し白っぽい見た目です。
1959年に農林認定品種として登録された、古くからの品種なんだとか。
岡田農園に行ってみた!

お母様のご病気をきっかけに、もともとりんごを栽培していた畑を、栽培時の手間がかかりにくい栗の栽培に切り替えた、岡田さん。
現在は栗とぶどうの栽培を行っています。
収穫時に手間のかかる「栗」と、収穫前までが忙しい「ぶどう」を上手に組み合わせることで、作業の負担を分散させていました。
小布施の土地は栗栽培に適した土地だそう。
畑のすぐ近くを流れる松川が氾濫することで、酸性の水が畑に流れ込みます。
この氾濫が何百年も前から続いているため、土壌が酸性になっているんだとか。
栗は酸性土壌を好む性質があるため、この地域は栗の産地として有名のようです。

岡田さん
栗の栽培歴約20年の農家さんです。
葛飾北斎の天井絵「鳳凰図」はぜひ見てほしいと、観光スポットまでご紹介してくださいました。
「毎年この栗を楽しみにしています!」とのクチコミが多く、岡田さんの栗は組合員さんから大好評です。
低温熟成で糖度UP!

収穫直後の栗は、実はあまり甘くありません。
栗は熟成させることで、デンプンがアミラーゼ(酵素)の働きによって糖に変化し、甘くなるのです。
岡田さんが収穫した栗は、生産指導や生産者の取りまとめを担う「有限会社エムエスケイ」が、1か月ほど低温熟成させています。
低温熟成にもポイントが!
熟成期間中に20%も水分が蒸散されるため、カビを発生させないように管理する必要があるそうです。
水分が蒸散するということは、栗の重量も減ってしまうということ。
それでも、岡田さんは熟成してさらにおいしくなった栗を食べてもらいたいとの一心で、低温熟成にこだわって販売しています。
大切に1か月間貯蔵した後、組合員さんのもとへお届け。
「驚きのおいしさ」「なんといっても栗が甘い!」といったクチコミがあるのも納得ですね。
光がたくさん当たるように剪定

栽培するうえで心がけていることは、収量の確保だそう。
いいものをたくさん収穫するために、岡田さんはとくに剪定作業に注力しています。
栗は日当たりの良い場所を好む性質です。
木の枝が混み合っていると日が当たらない場所ができ、花の咲かない枝が多くなってしまうんだとか。
岡田さんは、毎年実施される講習会での学びと長年の経験から、最適なタイミングで剪定を行っています。
風通しが悪くなると、害虫が発生しやすくなったり、病気の発生にもつながったり。
剪定作業は、おいしい栗を収穫するために欠かせない作業のひとつです。
岡田さんに聞いてみた!
おすすめの食べ方は?

もえぞー
圧力鍋でゆでて、スプーンですくって食べますね。
他には定番ですが、栗ご飯ですね。

岡田さん
栽培していておもしろいと感じるところは?


もえぞー
栽培している中で一番おもしろいと感じるところはありますか?
栗が畑一面に、敷き詰めたように落ちているときですね。
きれいな栗を拾うのは楽しいですが、逆に虫がいそうな栗を拾うときは目をそらしたくなります(笑)。

岡田さん
組合員さんへのメッセージ

もえぞー
組合員さんへのメッセージをお願いします。
栗の郷として知られる長野県小布施町で栗を栽培しています。
モンブラン・お汁粉・アイスクリームなどさまざまなスイーツが販売されているので、ぜひ小布施にお越しください。
葛飾北斎の美術館で絵を見るのもおすすめです。

岡田さん
秋の味覚「栗」もあんしんできるものを

インタビュー後、もえぞーも実際に栗の収穫体験をさせていただきました。
靴の端でイガを踏みながら、トングを使って栗を取り出します。
ハリとツヤがあり、ぷっくりとした栗が収穫できました。
出荷の際はサイズ別に分け、さらに台の上に広げて虫の被害がないかチェックしているそうです。
クリシギゾウムシと呼ばれる害虫は、栗の実に穴をあけて産卵しますが、孵化した幼虫は果実内を食害。
そのため、見た目で判断することは難しく、選別はとても時間のかかる作業なんだとか。
収穫した栗の約60%が害虫の被害に遭っていることもあるそうですが、あんしんして食べられるよう、岡田さんの栗は農薬に頼らずに栽培しています。
一般的に行われる、収穫後の燻蒸処理も行っていません。
今年の秋は、おいしさだけでなく、あんしんにもこだわった栗を味わってみませんか。
編集担当もえぞー
2022年アイチョイス入協、30代、夫と2人暮らし。
家庭菜園歴8年目で現在、有機栽培に挑戦中です!
前職では農家さんを相手に野菜の栽培指導をしていました。
ナッツは塩茹でした落花生が大好き♪







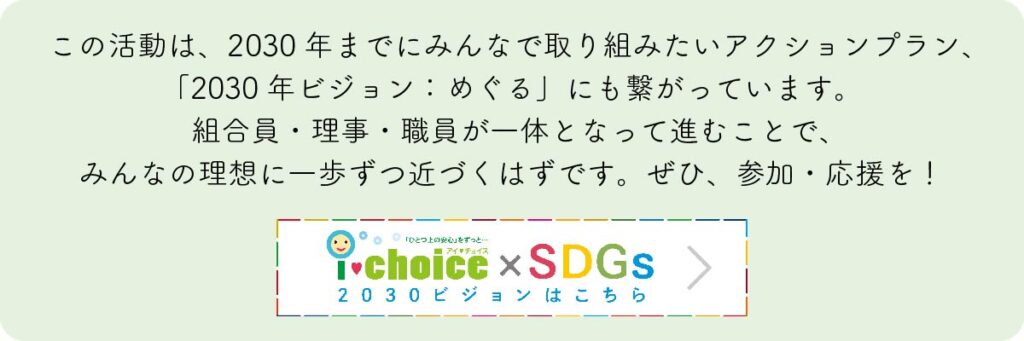









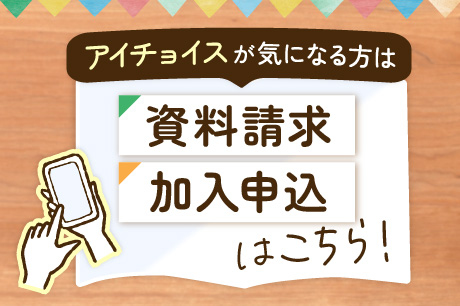




普段はどのようにして栗を食べますか?