農薬と食品添加物の違いと影響|残留農薬の基準値とは
食品を選ぶ際に、残留農薬や食品添加物が気になる方も多いでしょう。
農薬と食品添加物は本来異なるものですが、防カビ剤のように、同じ成分でも使用タイミングにより収穫前は農薬、収穫後は食品添加物と分類が変わることがあります。
本記事を読み、両者の違いや安全性を理解して、食の安全を考えるきっかけにしましょう。
目次
農薬と食品添加物の違い

農薬と食品添加物の違いを、以下の表にまとめました。
| 特徴 | 農薬 | 食品添加物 |
| 目的 | 作物の収量や品質を保つ | 食品の品質向上や保存性を高める |
| 規制法・管轄機関 | 農薬取締法(農林水産省)食品衛生法での残留基準(厚生労働省) | 食品衛生法(厚生労働省) |
| 表示ルール | 記載義務がない | 食品表示に記載する義務があるが、特定の場合には免除されることも。 |
農薬と食品添加物は目的や規制の仕組みが異なります。
農薬の目的は、虫の防除や雑草の除去によって作物を保護することです。
農薬取締法で登録・規制されていますが、食品中の残留について定めているのは食品衛生法です。
一方、食品添加物は加工・製造時に品質を保つためなどの理由で添加されます。
食品衛生法によって規格基準等が細かく設定されており、厚生労働省による厳しい検査も実施されているのです。
参考:農薬取締法に基づく規制の現状と今後について|農林水産省消費・安全局 農産安全管理課,(参照2025-09-05)
参考:食品添加物|厚生労働省,(参照2025-09-05)
農薬の定義

農薬は病害虫や雑草の被害を防ぐために使われます。
農薬取締法で定められたもののみが、農薬として使用可能です。
人の健康に影響を及ぼすことの無いよう、すべての農薬、飼料添加物、動物用薬品について、残留基準が定められており、基準を超えた作物は食品衛生法により、輸入や販売が禁止されています。
収穫後の食品のカビを防ぐポストハーベスト農薬は、「防カビ剤」としての目的で使われるものです。
海外では農薬とされていますが、日本では食品添加物として規制されています。
防カビ剤については、以下の記事で詳しく解説しているのでこちらも参考にしてください。
参考:農薬に関するよくある質問|農林水産省,(参照2025-09-05)
参考:食品中の残留農薬等|厚生労働省,(参照2025-09-05)
食品添加物の定義

食品添加物とは、食品の製造・加工または保存する際に、味や見た目、品質などをよくする目的で加えるものです。
食品添加物は食品衛生法第12条に定められ、厚生労働大臣の指定を受けた食品添加物(指定添加物)か、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物にあたるものが使用できます。
食品添加物はさまざまな種類や役割があり、表示方法もルールが定められているのです。
以下では、食品添加物の種類や用途、表示方法についても解説しています。
参考:食品添加物 |厚生労働省,(参照2025-09-05)
食品添加物の種類と用途例

食品添加物は以下の4つに分類されます。
- 指定添加物:厚生労働省から使用が認められたもの
- 既存添加物:国内で長年使用され、例外的に使用が認められたもの
- 天然香料:動植物から得られ香料として使用されるもの
- 一般飲食物添加物:一般の食品を添加物として使用しているもの
また、主な食品添加物には以下のようなものがあります。
| 代表的な食品添加物 | 内容・用途 | 使われている食品例 |
| 着色料 | 食品の色調をよくする目的で使用 | 明太子 醤油やソース アイスクリーム お菓子類など |
| 保存料 | 食品の腐敗を防いで保存性を高める | パン類 魚肉練り製品 チーズ ベーコンなど |
| 甘味料 | 食品に甘味をつける目的で使用 | 清涼飲料水 ガムやキャンディー お菓子類 乳製品など |
| 香料 | 食品の香り付けに使用 | 清涼飲料水 レトルト食品 栄養ドリンクなど |
| 調味料(アミノ酸) | 食材のうま味を強調するために使用 | 弁当 おにぎり お菓子 |
| 膨張剤 | 炭酸ガスやアンモニアを発生させて食品を膨らませる | クッキー ホットケーキ 蒸しパンなど |
| 発色剤 | 食品の色味を鮮やかにする 加工中に変色するのを防ぐ | ハム・ソーセージなどの加工肉食品 ピクルス・漬物など |
| pH調整剤 | 食品の pHを適切な範囲で保つために使用 | 加工食品 冷凍食品 お菓子・スナック類 |
上記の表に各食品添加物を解説した記事へのリンクを設置しています。
また、食品添加物の多い食品についての情報も別記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
参考:食品添加物 |厚生労働省,(参照2025-09-05)
食品添加物の表示例
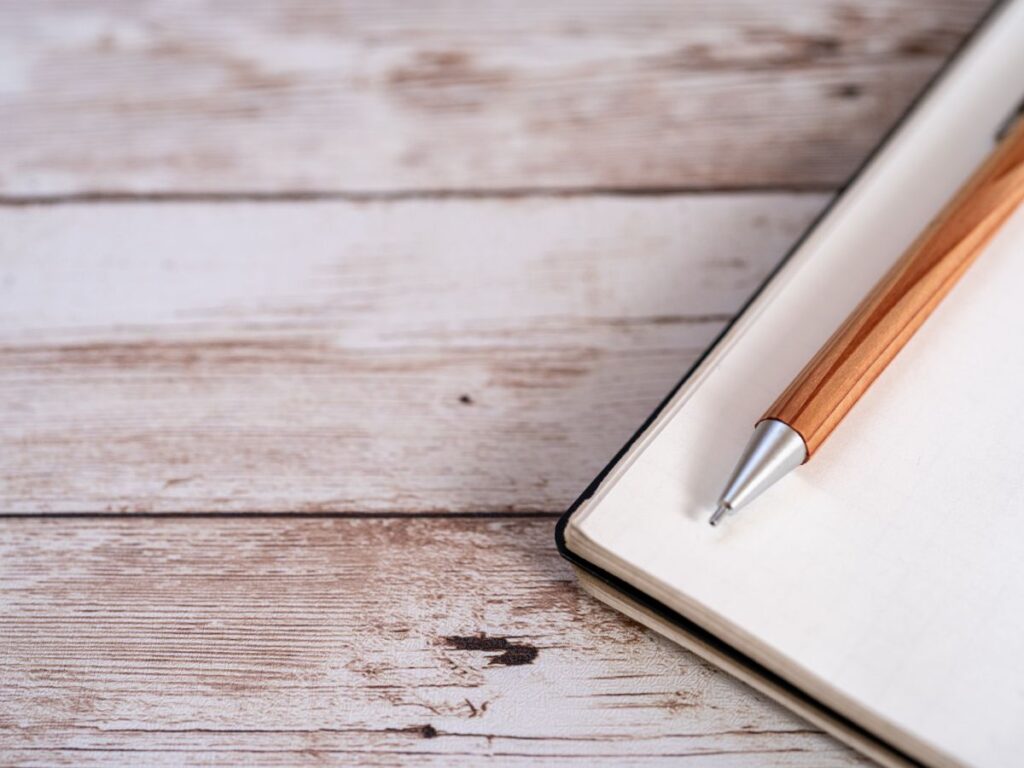
食品添加物の表示ルールを定めるのは、2015年4月に施行された食品表示法です。
食品添加物は、原材料と混同しないよう以下の3パターンで区別します。
- 原材料名と食品添加物欄を分けて表示
- 記号(「/」など)で区切って表示
- 改行・段で区切って表示
食品添加物は「炭酸水素ナトリウム」などの物質名で記載されるのが基本ですが、「重曹」のような簡略名で表示される場合も。
他にも、「着色料(カラメル)」のような「用途名併記」のパターンや、「かんすい」や「膨張剤(ベーキングパウダー・ふくらし粉)」のような一括名表示のケースもあります。
食品添加物の表示に関しては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
参考:早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版・事業者向け)|消費者庁,(参照2025-09-05)
食品添加物と農薬を規制するポジティブリスト制度
食品添加物と農薬にはそれぞれポジティブリストという規制制度があります。
このポジティブリスト制度によって、私たちの食の安全が担保されているのです。
ポジティブリストについて詳しくお伝えするために、以下を解説していきます。
- ポジティブリスト制度とは
- 食品添加物のポジティブリスト
- 残留農薬のポジティブリスト
ポジティブリスト制度とは
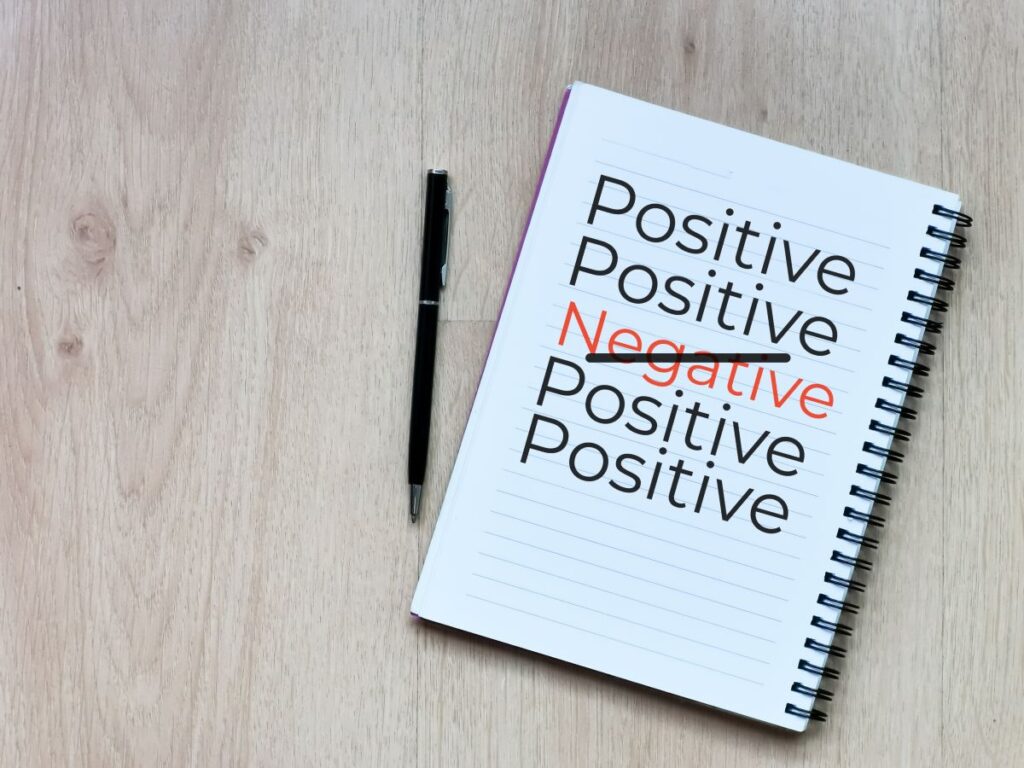
ポジティブリスト制度とは、あらかじめ国が安全性を評価し、安全性が確認された物質のみをリストアップして使用を認める規制の仕組みのことです。
ポジティブリストの目的は、食品の安全性の確保や使用可能な食品添加物を明確にすることにあります。
この制度によって、使用可能な物質が明示され、食品製造業者も消費者も安心して食生活を送ることができるようになりました。
一方で、ポジティブリストと対照的な規制法をネガティブリスト制度といいます。
使用や残留を禁止するものだけを指定し、それ以外は基本的に使用できるものとする仕組みです。
以下では、食品添加物と残留農薬のそれぞれのポジティブリストについて解説します。
参考:食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について|厚生労働省,(参照2025-09-05)
食品添加物のポジティブリスト制度

食品添加物は食品衛生法に基づくポジティブリスト制度によって規制されています。
食品添加物のポジティブリストでは、前述した以下4つの分類で規制され、指定された食品添加物のみが使用可能です。
- 指定添加物
- 既存添加物
- 天然香料
- 一般飲食物添加物
残留農薬のポジティブリスト制度

残留農薬のポジティブリスト制度は、食品中に残留する農薬等を規制するための仕組みで、2006年5月29日から日本で施行されています。
これは、食品安全委員会によりすべての農薬に対し残留農薬基準値が設定され、基準値を超えて残留した食品の販売などが禁止される制度です。
残留農薬基準値が個別に設定されている農薬と、0.01ppmが基準値として一律で設定されている農薬が存在します。
残留農薬の分類は以下の表で確認してください。
| 分類 | 内容 | 基準値の考え方 | 該当数 (導入時) |
| 残留基準が設定されているもの | 個別に残留基準が設定されている農薬等 | 農薬取締法に基づく基準、 国際・外国基準を参照 | 799品目 |
| 残留農薬が定められていないもの | 厚生労働大臣が一定量を告示 | 「人の健康を損なうおそれのない量」として一律0.01ppmを適用 | 残留基準設定外のすべての農薬等 |
| 厚生労働大臣が指定する物質 | 人の健康を損なうおそれがないことが明らかな物質 | 残留量に関わらず規制対象外 | 65物質 |
ポジティブリスト制度は、健康に悪影響が生じないよう残留農薬のリスクを管理するうえで、重要な制度です。
参考:食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について|厚生労働省,(参照2025-09-05)
食品添加物と農薬の摂取基準値
食品添加物と農薬の摂取基準は「リスク分析」に基づいて決められています。
以下では、リスク分析についてと、食品添加物・農薬等の摂取基準値について詳しく解説します。
安全性を測る食品のリスク分析

リスク分析とは食品の安全性の確保を目的として、食品安全基本法に基づいて定められました。
リスク分析は、以下3つの要素で構成されています。
- リスク評価
- リスク管理
- リスクコミュニケーション
リスク評価では、食品安全委員会が食品添加物や農薬などが人の健康に与える影響を科学的に分析し、ADI(1日摂取許容量)などの指標を設定します。
次にリスク管理では、その評価結果をもとに、使用基準や残留基準などの具体的な安全対策を検討・実施。
そして、リスクコミュニケーションでは、消費者、行政、事業者、専門家などが情報や意見を交換し、相互理解を深めることで、より効果的な安全対策につなげます。
リスク分析に関しては以下の記事でも解説しているので参考にしてください。
参考:食品安全委員会の役割 | 食品安全委員会 – 食の安全、を科学する,(参照2025-09-05)
食品添加物の摂取基準値

食品添加物の摂取基準値は、ADI(一日摂取許容量)という指標で示されます。
ADIは、人の健康に悪影響がないと推定される1日あたりの摂取量を表し、動物実験の結果に基づき安全係数が設定された指標です。
ADIは、各食品添加物ごとに基準値が異なります。
たとえば、食用赤色2号のADIは29mg/日、食用黄色4号のADIは440mg/日、ソルビン酸のADIは1465mg/日など(20歳以上の平均体重(58.6kg)における一日あたりの許容摂取量(mg/日))。
ADIは、動物実験で無毒性量が確認された量の1/100を基準に、毎日摂取しても安全な量として定められています。
ADIの表示は、体重1kgあたり1日に何mgまでという表記です。
使用基準を超えた場合や目的外に使用した場合は食品衛生法違反となります。
ADIについて、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
参考:参考:食品添加物の使用基準と成分規格|「食品衛生の窓」東京都保健医療局,(参照2025-09-05)
参考:一日摂取許容量(ADI)とは?|食品安全委員会,(参照2025-09-05)
農薬や残留農薬の摂取基準値

残留農薬については、「残留基準値」と呼ばれる、農薬ごとに定められた残留が許される上限量が設定されています。
残留基準が設定される農作物は主に以下の2パターンです。
- 国内で当該農薬が使用される農作物
- 国内では使用されないが、海外で当該農薬が使用される農作物(輸入品への対応)
残留農薬は、一日当たりの摂取量 (ADI:許容一日摂取量)と、24時間又はそれより短時間の間に摂取しても健康への悪影響がないと推定される量(ARfD:急性参照用量)をそれぞれ超えないように設定されます。
残留農薬の基準は、食品中の農薬が人の健康に悪影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて慎重に設定されているものです。
残留基準が設定されない場合、一律基準である0.01ppmが適用されます。
1ppmは、食品1kgあたりに含まれる農薬が1mgの濃度です。
国際基準があるものは、その内容も参照されます。
参考:食品衛生法における農薬残留基準について|厚生労働省医薬・生活衛生局,(参照2025-09-05)
食品添加物と農薬が気になる方は有機食品(オーガニック)がおすすめ

食品添加物と残留農薬は国内で厳しく管理されていますが、リスクが気になる方は有機食品(オーガニック)などを選ぶのも一つの方法です。
有機食品と謳えるものは、「有機JAS認証制度」にて、有機農産物やそれを原材料とした加工食品が厳格な基準を満たしているかどうかを第三者機関が検査・認証しています。
認証された商品には「有機JASマーク」が表示されており、食品選びの目安の一つです。
有機栽培では、化学合成された農薬の使用が禁止されているため、農産物に残留する農薬のリスクを大幅に抑えることができます。
さらに、有機JAS認証を受けた加工食品では、使用できる食品添加物の種類や目的が制限されており、化学合成添加物の使用は原則禁止です。
これにより、食品添加物の摂取量も抑えることができます。
有機野菜については、以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひご参照ください。
食品添加物と農薬に関するよくある質問

農薬は食品添加物ですか?

食品添加物中の農薬はポジティブリストの対象ですか?
食品添加物と農薬にはそれぞれ別のポジティブリスト制度が存在。
食品添加物は、食品衛生法にのっとったポジティブリスト制度によって規制されます。
残留農薬については、食品安全委員会がすべての食品に残留農薬基準値を設定して管理しているのです。

食品添加物と農薬の関係性を理解して安心な食生活を!

食品添加物や農薬についてリスクを感じる方もいますが、どちらも国内で定められたリスク分析に基づき管理されています。
食品添加物も農薬もそれぞれADIという1日の摂取基準値が定められており、安全性が確保されているのです。
しかし、食品添加物や農薬が気になる方は、有機JAS認証の商品を選ぶのもいいでしょう。
アイチョイスでは、有機JAS認証の商品や食品添加物に頼らない商品を取り扱っています。
もし、より安心安全な食品や食材を選びたいという方は、加入前にアイチョイスの商品を味わうことができる「おためしボックス」もご用意しているので、ぜひお試しください。








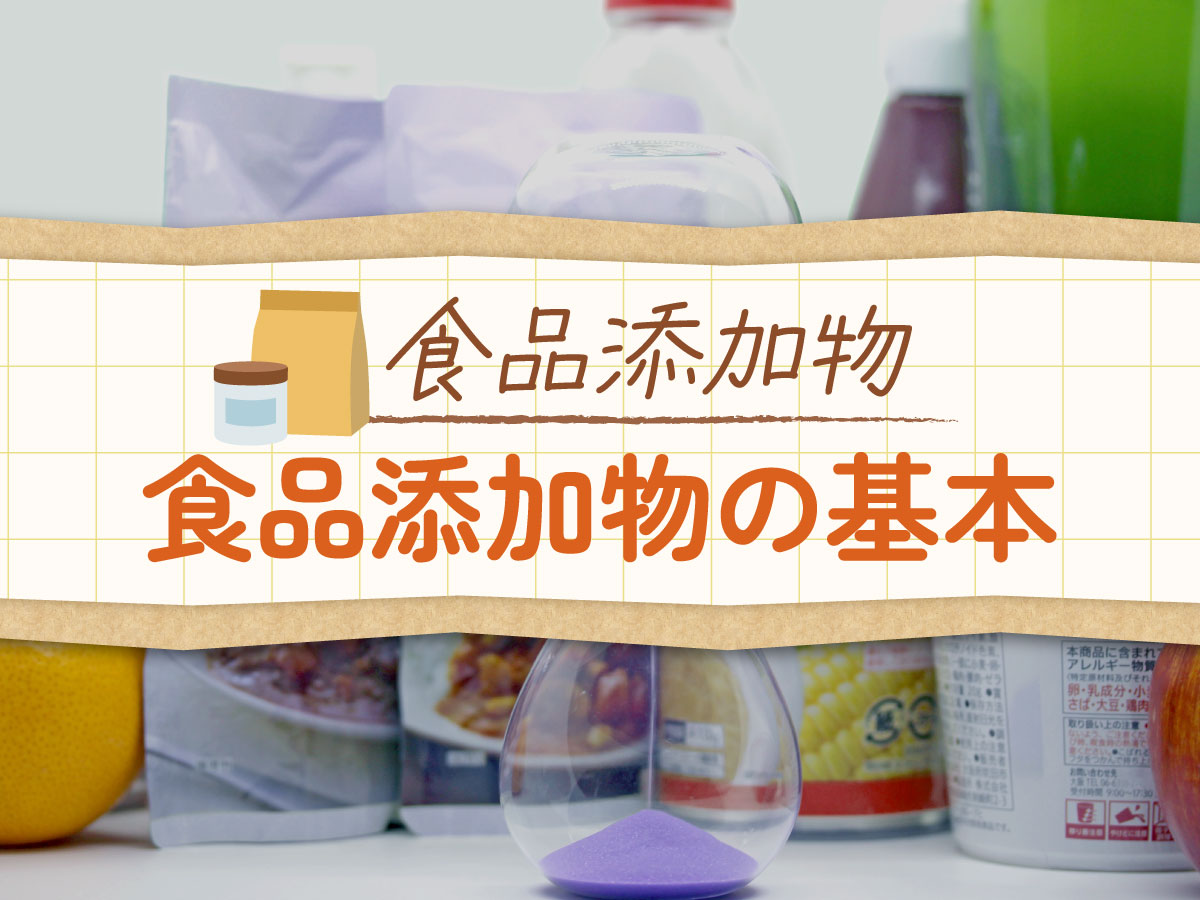

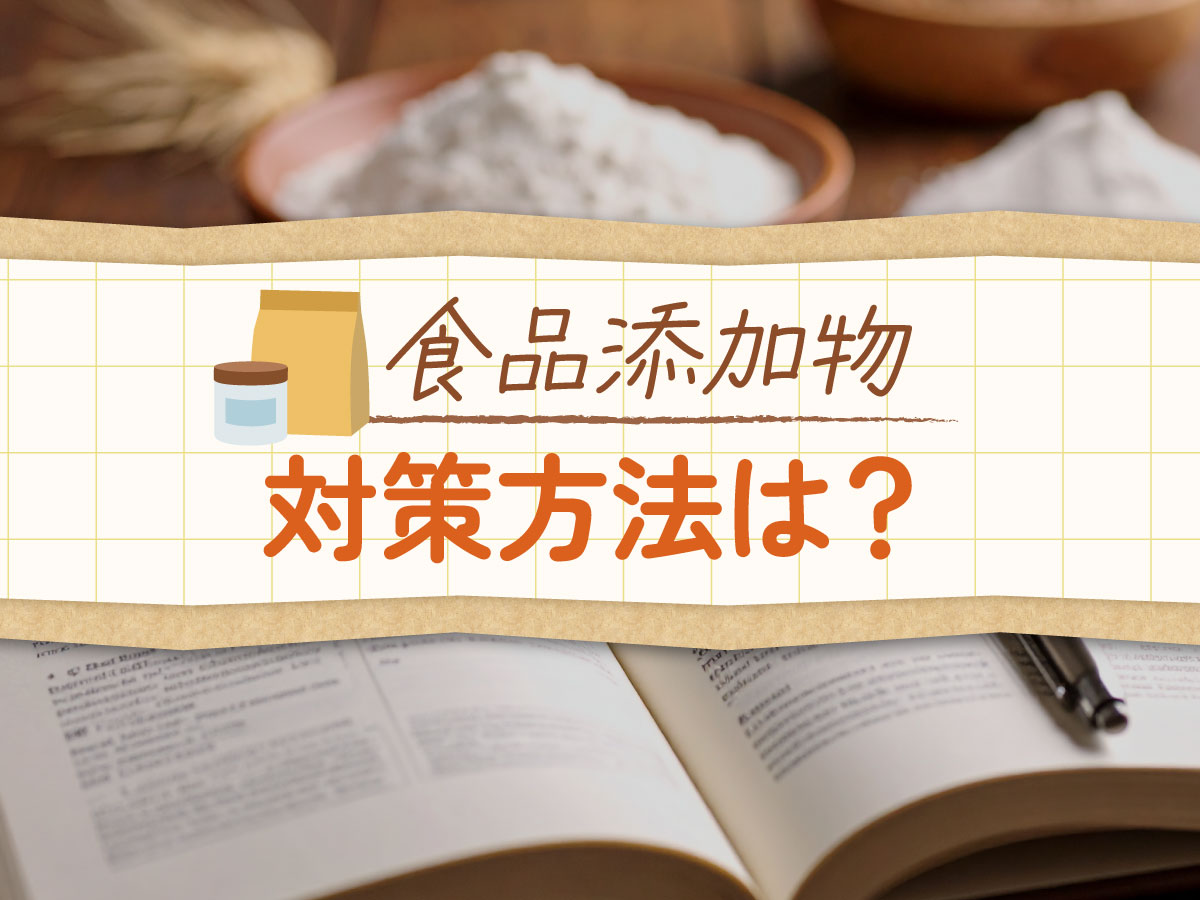
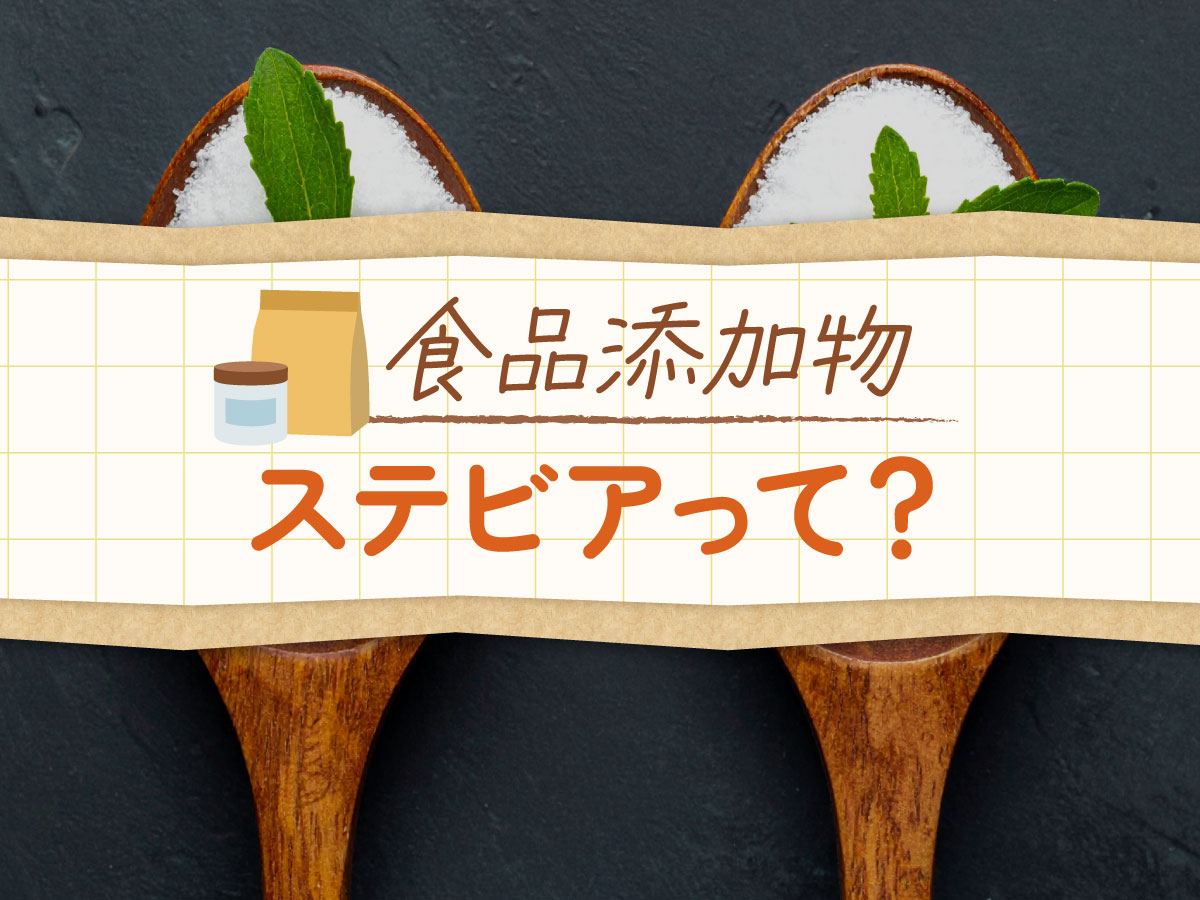





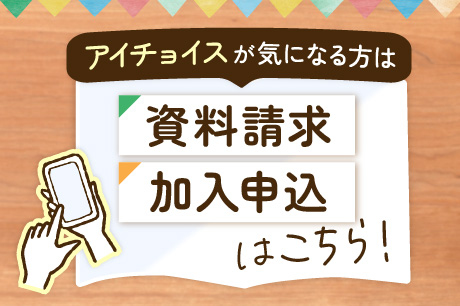




農薬は食品添加物ではありません。
ただし海外で生産された柑橘類やバナナなどに使用されるポストハーベスト農薬は、海外では農薬扱いですが日本では防カビ剤として食品添加物に分類されます。
防カビ剤については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご参照ください。